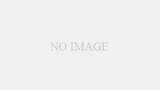2025年5月27日に、秘密漏えい疑いに関する第三者委員会の報告書が公表されました。
正式版は兵庫県のウェブサイトでも確認できますが、検索性・可読性を高めるために、全文の文字起こしも掲載します。
「秘密漏えい疑いに関する第三者委員会」とは
2024年度、兵庫県は、文書問題に関連する第三者委員会を3つ立ち上げました。(情報ソース:2025/2/12朝日新聞)
- 告発文書の内容について真偽の調査
- 週刊文春や立花孝志氏らによる県庁情報の拡散に関する情報漏洩の調査
- 前総務部長が公用パソコン内の私的情報を県議らに漏洩した疑惑の調査
当ページで取り扱う「秘密漏えい疑いに関する第三者委員会」とは、上記「3」の「井ノ本前総務部長が公用パソコン内の私的情報を県議らに漏洩した疑惑の調査」に関する調査結果報告書です。
委員会による記者会見
第三者委員会の調査報告書(全文文字起こし)
最終調査報告書(公表版)
秘密漏えい疑いに関する第三者調査委員会
委員長 弁護士 工藤涼二
委員 弁護士 中村真
委員 弁護士 李延壮
はじめに
1 当初調査の依頼
兵庫県の元西播磨県民局長が県から貸与されていた公用パーソナルコンピュータ(以下「公用パソコン」という。)内に保存していた、公務とは関係がないと思われる同局長のごく私的な情報が、令和6年3月25日に人事当局により発見され、以降、総務部職員局人事課において同公用バソコン本体と併せて厳重に保管されていたにもかかわらず、同年7月25日付け週刊文春の報道記事(以下「本件報道」という。)により、同私的情報が兵庫県の職員により外部に漏えいされた疑いが生じたことから、客観的かつ信頼性の高い調査を行うため、兵庫県及びその組織・職員から独立した中立・公正な弁護士として兵庫県弁護士会から推薦された3名の委員から構成される当委員会は、同年10月8日、兵庫県より依頼を受け、以後、元西播磨県民局長の私的情報の漏えいの有無及び漏えい者の特定などの調査にあたってきた。本報告書は、その調査結果をまとめたものである。
なお、本調査は、あくまで紙に印刷された資料による漏えいにかかるものであり、その他の態様による漏えいは対象としていない。
また、委託内容及び調査期間等に鑑み、本調査では前記濡えいの有無・ 漏えい者の特定等の事実調査を中心としており、再発防止策の提言は含まない。
2 追加調査の依頼
当委員会は、令和7年1月27日付けで報告書を提出したが、その後、E(井ノ本)氏から弁明書が県に提出され、その中でE(井ノ本)氏は重要な部分についてこれまでの供述を変更するとともに、新たな事実についての主張をするに至った。当委員会は、それらの点について県から追加調査の依頼を受けたので、今般、鋭意追加調査を実施した。
本調査報告書は、その調査結果をも併せて報告するものである。
3 留意事項
追加調査依頼書では「本県人事課が聴取した同職員の供述や『弁明書』では、今回の漏えい行為の動機となるべき事情等、本県人事課が懲戒処分に関する判断を行うにあたり重要な供述がなされており、その真偽を確認する必要があるのではないかと思料します。」 「弁明書及び弁明書の訂正申立書の内容等を踏まえた追加調査を行っていただき、同追加調査内容も踏まえた調査報告書を改めてご提出いただきますよう依頼します。」とあるが、当委員会の調査は、懲戒処分の一環として(ないしそのために)行われたものではないことを付言しておく。
すなわち、①当委員会の調査は懲戒処分を目的とするものではなく、②追加調査報告も、弁明書記載の事実の存否・主張の適否について当委員会の調査の結果を基に報告・見解の表明を行うものであるので、③県においても、当委員会の調査結果と県が行う懲戒処分を明確に区別いただく必要があることに留意されたい。
目次
調査の結論…6頁
結論に至る理由
第1 前提となる事実等
1 当委員会の構成等…7頁
2 本調査に登場する関係者…9頁
3 調査の端緒…10頁
4 私的情報の保管状況…11頁
5 週刊誌「週刊文春」7月25日の報道内容…11頁
6 「秘密」について…12頁
7 「漏えい」について…12頁
第2 調査の概要
1 元県民局長の公用パソコンに保存されていた私的情報の内容及び同パソコンの保管状況の確認…13頁
2 アンケート調査とその結果…13頁
3 事情聴取の実施及びその内容…14頁
4 当委員会の開催状況…14頁
第3 認定事実及び判断
1 端緒…15頁
2 私的情報の管理状況について…15頁
3 「緑ファイル」の処理状況について…19頁
4 調査対象者について…22頁
5 E(井ノ本)氏について…22頁
6 F(原田)氏について…28頁
7 開示資料の同一性についての疑問について…29頁
8 漏えいの動機ないし目的について…30頁
9 他の議員に対する漏えいの可能性について…31頁
10 E(井ノ本)氏の指摘する「他の情報の出所」について…33頁
第4 省略…34頁
第5 E(井ノ本)氏の新主張について
1 新主張の概要…34頁
2 従前の主張にかかる供述内容の確認…35頁
3 新主張についての検討…35頁
4 新主張(1)のうち「知事ないし元副知事の指示」の有無について…36頁
5 新主張(1)のうち「正当業務行為該当性」について…39頁
6 新主張(1)のうち「外部通報該当性」について…40頁
7 新主張(4)「公務の運営に重大な障害を生じさせていない」について…42頁
第6 まとめ…42頁
調査の結論
令和6年4月1日時点で兵庫県総務部長であったE(井ノ本)氏は、少なくとも、
1 令和6年4月19日16時30分頃、 T(迎山)県議会議員に対し、同議員の所属会派(甲(ひょうご県民連合)会派)控室内において、元県民局長の私的情報を紙に印刷した資料の一部を提示し、併せてその内容の一部を口頭で述べるなどして秘密を濡えいした
2 令和6年4月22日の前頃、S(山口)県議会議員に対し、同議員の所属会派(乙(自由民主党)会派)の幹事長室横の会議室内において、元県民局長の私的情報を紙に印刷した資料の一部を提示し、併せてその内容の一部を口頭で述べるなどして秘密を漏えいした。
3 令和6年4月中旬までの間に、U県議会議員に対し、同議員の所属会派(乙(自由民主党)会派)の幹事長室横の会譲室内において、元県民局長の私的情報を紙に印刷した資料の一部を提示し、併せてその内容の一部を口頭で述べるなどして秘密を漏えいした
と認められる。
結論に至る理由
第1 前提となる事実等
1 当委員会の構成等
(1) 当委員会の構成及び兵庫県との利害関係がないこと
当委員会の構成は、以下のとおりである。
委員長 工藤涼二(くどう法律事務所 弁護士)
委員 中村真(方円法律事務所弁護士)
委員 李延壮(神戸海道法律事務所弁護士)
なお、当委員会の上記構成員は、いずれも兵庫県より委員となる弁護士の推薦の依頼を受けた兵庫県弁護士会において、調査対象と目される関係者との利益相反関係がないことを確認した上で選任されたものであり、兵庫県及びその職員並びに本調査の対象者等関係者と事実上ないし法律上の利害関係を有しない。
(2) 当委員会の趣旨・目的
令和6年7月17日、後掲の記事が掲載された週刊文春令和6年7月25日号において、兵庫県職員が秘密を漏えいしたと疑われる旨の報道がなされた。兵庫県は、その事態の重要性に鑑み、客観的かつ信頼性の高い事実調査を行うため、令和6年10月8日、前記秘密漏えいの事実の存否・内容を客観的かつ中立公正な形で確認することを目的として、兵庫県から独立した中立・公正な弁護士のみで構成される「秘密漏えい疑いに関する第三者調査委員会」を設置した。
当委員会が当初に委託された事項は、以下のとおりである。
① 週刊文春令和6年7月25日号に掲載された兵庫県職員が秘密を漏えいしたと疑われる事案(以下「調査対象事案」という。)に関する事実関係の究明、把握、調査、認定
② 前記①に関する報告書の作成
③ 前記① ・②に関連する事項その他当委員会が必要と認める事項
(3) 調査対象事案の概要
添付の「週刊文春令和6年7月25日号の記載の整理(情報ソースごと)」記載のとおりである。
(4) 当委員会の独立性
当委員会は、その独立性を確保し、客観的かつ信頼性の高い調査を実現するため、兵庫県より調査の委託を受けるに当たり、当委員会の活動、独立性について、兵庫県作成の「秘密漏えい疑いに関する第三者調査実施要綱」及び日本弁護士連合会の2021年3月19日付「地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針」の規定、並びに各組織の不祥事における第三者委員会の調査事案に共通する一般的な内容として同指針が前提とする日本弁護士連合会の2010年7月15日付作成・同年12月17日改訂の「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に従い、概要、以下の事項を合意した。
① 起案権の専属
調査報告書の起案権は、当委員会に専属する。
② 調査報告書の記載内容
当委員会は、調査により判明した事実とその評価を、兵庫県に不利となる場合であっても、調査報告書に記載する。
③ 調査報告書の事前非開示
当委員会は、調査報告書提出前に、その全部又は一部を兵庫県に開示しない。
④ 資料等の処分権
当委員会が調査の過程で収集した資料等については、原則として、当委員会が処分権を専有する。
⑤ 利害関係
兵庫県と利害関係を有する者は、委員に就任することができない。
2 本調査に登場する関係者
〔県関係〕
(1) A(渡瀬)氏(元西播磨県民局長。令和6年3月末での自己都合退職届を提出していたが、7項目の「告発文書」を作成して各所に送付したことから退職が留め置かれ、総務部付とされたのち、同年5月7日付けで停職3月の懲戒処分を受けた。なお、同年7月7日に自死された模様。以下「元県民局長」という。なお、以下では、説明の便宜上A(渡瀬)氏の姓を「A(渡瀬)氏」と置き換えて表現している部分がある。)
(2) 齋藤元彦氏(第53代・54代兵庫県知事。以下「知事」という。)
(3) 片山安孝元副知事(令和6年7月31日に副知事を辞職した。以下「元副知事」という。)
(4) D(小橋)氏(令和5年度末時点は総務部長。令和6年4月1日に理事に昇任したが同年8月1日付けで総務部付に降任。)
(5) E(井ノ本)氏(令和6年4月1日より総務部長。同年8月19日付けで総務部付となる。)
(6) F(原田)氏(産業労働部長)
※ なお、前記(2)から(5)の4名につき、週刊文春では「この”四人組”は、みんなもともと人事課出身。…(略)…兵庫県庁では知事以下五人を『牛タン倶楽部』と陰で呼んでいます。」と記載されている。
※ 今回の調査によっても、知事とこれら4名のグループの呼称についての確認はできなかったが、4名の人事記録によれば、確かに同じような時期に、総務、人事関係の組織に所属していた模様であり、互いの人的関係も相当程度濃密であったことがうかがわれる。
(7) G(井筒?)氏(総務部。以下の役職名省略。以下同じ。)
(8) H(上田)氏(総務部)
(9) I(副課長?)氏(総務部)
(10) J氏(総務部)
(11) K氏(総務部)
(12) L氏(総務部)
(13) M氏(総務部)
(14) N氏(総務部)
(15) O氏(総務部)
(16) P氏(総務部)
〔県議会関係〕
(1) Q(岸口)議員(丙(維新の会)会派。文書問題調査特別委員会(以下「百条委員会」という。)の副委員長)
(2) R(増山)議員(丙(維新の会)会派)
(3) S(山口)議員(乙(自由民主党)会派)
(4) T(迎山)議員(甲(ひょうご県民連合)会派)
(5) U議員(乙(自由民主党)会派)
(6) V(内藤?)議員(乙(自由民主党)会派)
(7) W(竹内)元議員(甲(ひょうご県民連合)会派。百条委員会の委員であったが、令和6年11月18日付けで県議会議員を辞職した。)
3 調査の端緒(元県民局長の私的情報存在判明の経緯)
(1) 元県民局長の「告発文書」が契機となって知事の指示により開始された同文書の作成者特定の調査により、令和6年3月25日に元副知事及びH(上田)氏が西播磨県民局に赴いて持ち帰った元県民局長の使用していた公用パソコン内に、元県民局長のごく私的な情報を内容とするデータ類(以下「私的情報」という。)が多数保存されていることが判明した。
(2) なお、その際、同公用パソコンにUSBメモリー1基が接続されていたが、これは元県民局長の私物であったため、その場で取り外されて元県民局長に引き渡された。
4 私的情報の保管状況
(1) 令和6年3月25日、西播磨県民局にて回収された元県民局長の使用していた公用パソコン内に存在した私的情報をコピーし、H(上田)氏が県人事課共有フォルダの人事担当フォルダ内の「【副課長のフォルダ】」内に「【A(渡瀬)氏PC】」との名称のフォルダを新設し、その中にコピーしたデータを保存した。この際、H(上田)氏が公用パソコンから USBメモリーと自身の公用パソコンを用いてコピー・保存の作業を行い、USBメモリー内のデータは作業後消去した。なお、令和6年3月中にこの「【副課長のフォルダ】」内に移された私的情報のデータにアクセスできたのは、総務部職員局人事課所属の内の20名の職員だが、その中で「【副課長のフォルダ】」内に当該情報が保存されていたことを実際に知っていたのは、H(上田)氏、J氏及び元副知事のみであった。G(井筒?)氏は、令和 6年3月25日に県人事課により公用パソコンが回収された日から4、5日後に同パソコン内に私的情報のデータが存在したことを認識していたが、少なくとも同月中は同パソコンから「【副課長のフォルダ】」にデータが移されて保管されていることを認識しておらず、当委員会の調査時点までの間にも、G(井筒?)氏が自らデータそのものを確認したことを裏付ける資料はない。
(2) 令和6年4月以降も上記20名の職員は「【副課長のフォルダ】」にあるデータを閲覧できる状態にあったが、同年9月11日に別のフォルダに移し替えたので現在は閲覧できない。
5 週刊誌「週刊文春」7月25日号の報道内容
その内容は、添付の「週刊文春(令和6年7月25日号)の記載の整理(情報ソースごと)」のとおりとなる(以下「本件記事」という。)。
6 「秘密」について
(1) 地方公務員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされており(地方公務員法34条1項第1文)、この義務に違反して秘密を洩らした者は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金刑に処せられるとされている(同法60条2号)。
(2) この場合における「秘密」とは、 「一般的に了知されていない事実であって、それを了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるもの」であるとされている(行実昭和30年2月18日自丁公発第23号)。また、それは、単に本人が主観的に秘密とすることを欲する事実であれば足りるものではなく、客観的に見て本人の秘密として保護に値するものでなければならないとされている。
(3) 本件における「元県民局長の私的情報」は、その内容からして正に個人情報といえるから、前記の基準による保護されるべき「秘密」に該当するものであると解される。なお、新聞報道等によれば、令和7年3月18日付けで、県人事課において、元県民局長の私的情報は非公開情報と決定された模様である。
7 「漏えい」について
(1) 「漏えい」については、地方公務員法34条では「漏らす」の用語が、現行刑法では「漏示」の用語が使用されているところ、「漏らす」とは、「当該職員以外は了知していない事実、あるいは一部の特定の者しか了知していない事実を、広く一般に知らしめる行為または知らしめるおそれのある行為の一切をいう」とされている(学陽書房鹿児島重治著「逐条地方公務員法」第34条の解説)。また、「漏示」とは、「不知の第三者に告知すること」(前掲注釈刑法)すなわち「秘密をまだ知らない他人に告知すること」をいうとされている。
(2) さらに、両者とも、その方法には制限はなく、口頭で告知すると、書面によって告知するとにかかわらないとされ、かつ、人の秘密を記載した書面を放置したままで、他人の閲読に任せておくなどのように「不作為による漏えい」もこれに該当すると解されている。
(3) また、 「漏えい」は不特定多数の者に対して行った場合は当然であるが、特定の個人に対する場合もさらに伝達されるおそれがあるので「漏えい」したことになると解されている(前記「地方公務員法」34条。前掲「注釈刑法」 134条)。
(4) これらの点からも、これらの用語の間には実質的な差異はないと解され、県からの依頼書にも「漏えい」の用語が用いられているので、本報告書においては「漏えい」を用いることとする。
第2 調査の概要
1 元県民局長の公用バソコンに保存されていた私的情報の内容及び同パソコンの保管状況の確認等
(1) 当委員会は、令和6年10月8日、県人事課の2室隣のA会議室において、元県民局長の使用していた公用パソコン内に保存されていた私的情報の内容につき、後述の「ドッチファイル」に編綴された紙に印刷された資料により、その概略の開示を受け、また同公用パソコンが人事課内のロッカーに保管されていることを確認した。
(2) また、令和6年12月10日、県人事課のすぐ隣のB会議室において、私的情報がどのようなフォルダ名で保存されているか等を、実際に立ち上げられた元県民局長の公用パソコンの画面で確認した。
(3) 令和6年12月10日、元県民局長公用パソコンの保管状況及びデータの保存状況について、 I(副課長?)氏及びM氏から説明を受け、確認した。
2 アンケート調査とその結果
(1) 当委員会は、私的情報のデータにアクセスできた可能性のある別紙「元西播磨県民局長が作成した私的文書の管理状況」 (※本報告書においては省略) 3ページ目の「※1」に記載の職員(後日直接事情聴取が予定されているG(井筒?)氏 ・H(上田)氏・J氏・K氏を除く。)に対し、アンケート調査を実施した。
(2) それによれば、結論として、対象職員の中で本件私的情報にアクセスし、紙に打ち出したり、外部に流出させたりしたと認められるものはいなかった。
3 事情聴取の実施及びその内容
当委員会は、関係者からの事情聴取を実施するに当たり、前提となる事実を確認する意味からも、まず総務部職員局人事課等所属職員から聴取を開始し、その後、県議会議員や週刊文春で指摘されていると推測される職員から事情を聴取することとし、その途上で現れた事実関係の疑問点などを確認するため、適宜、人事課関係者から再事情聴取を行った。その具体的な状況は、次のとおりである。
(1) 当初調査
令和6年10月24日から同年12月24日にかけて、人事課職員11名、県議会議員6名及び元副知事など計18人から述べ24回にわたり、事情を聴取した。
(2) 追加調査
E(井ノ本)氏に対し書面照会したほか、令和7年3月4日から令和7年3月18日にかけて、知事及び元副知事など計4人から事情を聴取した。
(3) なお、W(竹内)元議員に対し、令和6年12月6日午後5時34分の電子メールで、また12月20日付けの同元議員事務所宛の郵送書面で、調査協力依頼を行ったが、何の応答もなかった。その後、同元議員は、令和7年1月18日、死亡されたため、聴取は実施不能となった。
4 当委員会の開催状況等
(1) 当初調査
令和6年10月8日から令和7年1月21日まで、計19回にわたり、委員会を開催し、鋭意調査検討した。
(2) 追加調査
令和7年2月24日から令和7年3月28日にかけて、計6回にわたり、委員会を開催し、鋭意調査検討した。
第3 認定事実及び判断
1 端緒
元県民局長の「告発文書」が契機となって知事の指示により開始された同文書の作成者特定の調査により、令和6年3月25日に元県民局長の使用していた公用パソコンに元県民局長のごく私的な情報が保存されていることが判明した(前記第1の第3項記載のとおり)。
2 私的情報の管理状況について
この私的情報が、以後、どのように管理されてきたかは、人事課作成の「元西播磨県民局長が作成した私的文書の管理状況」に記載されたとおりであるが、同資料及び上記事情聴取によれば、これまでに判明している限りで以下のように紙に印刷されて関係者に交付されたことが認められるところ、「週刊文春」 7月25日号による報道がされるまでの間におけるそれらの資料の取り扱いは次のとおりであったと認められる(すべて令和6年)。
(1) 3月26日(火)
H(上田)氏が元県民局長の公用パソコン内の私的情報のうち、 「※フォルダ名省略」内のファイルを印刷して保管した。なお、人の目に触れてはいけないため、H(上田)氏は、自分のパソコンを使用してB会議室内で行った。
また、H(上田)氏は、「※フォルダ名省略」には(※省略)というものが含まれており、文書の作成を誰かと一緒にした証拠になる可能性があると思ったので打ち出したが、私的情報にかかる文書は、単にそのような事実があったとして何かの証拠になることは考えられなかったので、打ち出さなかった。したがって、この資料中には元県民局長の私的情報は含まれていなかったから、本調査の対象にはならない。
(2) 3月下旬から 4月上旬頃
元副知事からの指示により、H(上田)氏は、公用パソコン内の私的情報(「※フォルダ名省略」を含む。)を1部印刷して同元副知事に届けた。
元副知事は、その量につき、「紐付き封筒にいっぱいになる感じ。かなりの枚数。ダブルクリップで留めていた。かなりある。普通の封筒には入らない位。立体型の封筒に入ってきた。」と供述しており、また「部屋に置いとったらマズいなと思ったので、4月の早い時期にシュレッダーした。職員に見せたらマズいなと思ったので自分でやった。」と説明している。なお、副知事室内にシュレッダーがあることは、他の複数の職員の供述により認められる。
(3) 4月1日
H(上田)氏は、調査にあたる職員に対し、告発文書と、本件私的文書のうち「※フォルダ名省略」及び公用メールの一部をコピーして配布した。ただし、これは、本項(1)に記載した印刷物を利用したものであったから、A(渡瀬)氏の私的情報にかかる文書は含まれていない。したがって、やはり本調査の対象にはならない。
(4) 4月中旬頃
ア E(井ノ本)氏は、H(上田)氏に対し、私的文書のうち「※フォルダ名省略」フォルダ内のファイルを印刷して持ってくるように指示した。これを受けてH(上田)氏は、考査担当のN氏に、全部ではなくてよいので私的な文書の内容が分かる資料を用意するように指示した。N氏は、自らの判断で、「※フォルダ名省略」フォルダから適宜抜粋し、A会談室で、勤務時間外に、マスター用1部を片面印刷で、その他の4部は両面印刷で計5部印刷し、これらをいずれも緑色の厚綴じフラットファイル(以下「緑ファイル」という。)に綴ったうえで、E(井ノ本)氏、G(井筒?)氏、H(上田)氏、I(副課長?)氏に両面印刷のファイル各1部を手渡し、残りのマスター用1部を人事課内の鍵付きロッカー内に保管した。
イ ところが、後述のとおり、令和6年7月25日付け週刊文春で元県民局長の私的データにかかる本件記事が掲載されたことから、緑ファイルの保管状況を確認することになり、G(井筒?)氏がE(井ノ本)氏に確認したところ、E(井ノ本)氏は、当初、緑ファイル受領の事実を否認していた。このことは、G(井筒?)氏の供述からも認められる。
ウ この点について検討するに、N氏は、緑ファイルをE(井ノ本)氏に届けた時のことについて「E(井ノ本)氏から、最初のページのほうにある記号の意味について聞かれたので、答えたところ、E(井ノ本)氏が『※省略 』と言った」ということを、戻ってH(上田)氏に『目の前で見られて、記号の意味を聞かれました』と報告した。」と供述しているところ、H(上田)氏も「N氏がE(井ノ本)氏に持って行ったときに、二人の間であったやりとりについては、課に帰ってきたN氏から『E(井ノ本)氏から聞かれたのでそういう説明をしておきました』と聞いた記憶はある」と、N氏の前記供述と整合する供述をしているところからして、N氏の前記供述の信用性は高いというべきである。
エ したがって、E(井ノ本)氏は、緑ファイル1冊を受領していたと認められる。
オ (私的情教の具体的内容に閉わるため省略)
カ この「緑ファイル」については、G(井筒?)氏は令和6年5月7日の後まもなく溶解処分した、H(上田)氏は同年4月中にシュレッダー処理したと供述しているところ、本件で現れた各資料から、これらの供述を覆すに足りるものはない。
また、I(副課長?)氏は、同月下旬に自分のロッカーに移して以降触っていない。これまで処分しなかった理由について同氏は「みんなが処分しているとは知らなかったので。」と説明している。E(井ノ本)氏に関しては後述する。
(5) 6月17日
N氏とO氏は、百条委員会への提出書類の検討のために、公用パソコンの私的文書の、a懲戒処分に関する資料(「告発文書」に記載されていた7項目の事実確認を含む。)及びb公用パソコン内の資料を、提出用・保存用として、執務時間外にA会謡室でO氏の助力を得て各2部印刷し、2冊の「ドッチファイル」(厚さ各10~15cm程度)に綴った。すなわち、2セットで計4冊となるところ、これらは、公用パソコンと同じ人事課内の鍵付きロッカーに現在も保管されている。
(6) 6月21日から同月28日頃
I(副課長?)氏、L氏及びO氏は、6月21日、県の特別顧問である弁護士の事務所に、上記「ドッチファイル」1セット(2冊)を持参し、同弁護士が内容を確認するために預けたが、いずれも同月28日に返還されており、この間、同事務所から外部に搬出されたことをうかがわせる資料はない。
(7) 6月18日から7月上旬頃
D(小橋)氏の執務室において、複数回、G(井筒?)氏、H(上田)氏、I(副課長?)氏、L氏、M氏、N氏及びO氏が集まり、百条委員会への提出資料の協議をする際、「ドッチファイル」1セット(2冊)を持参しているが、これはその都度持ち帰っている。
(8) 7月8日
県議会会議室で開催された百条委員会委員長及び副委員長との同委員会への提出資料の打合せの際、「ドッチファイル」2冊(a、b)を持参したが、提示したのは懲戒処分に関する資料(a)のみであり、いずれも打合せ終了後に持ち帰っている。なお、県側の出席者は、G(井筒?)氏、H(上田)氏、I(副課長?)氏、L氏及びO氏の5名であった。
(9) 7月 10日
県議会会議室で開催された百条委員会委員長及び副委員長との同委員会への提出資料の打合せの際、「ドッチファイル」2冊(a、b)を持参したが、提示したのは懲戒処分に関する資料(a)のみであり、いずれも打合せ終了後に持ち帰っている。なお、県側の出席者は、G(井筒?)氏及びH(上田)氏の2名であった。
(10)7月16日
乙(自由民主党)会派控室内会議室で開催された百条委員会委員長との提出資料の打合せに、 H(上田)氏及びI(副課長?)氏が出席したが、「告発文書」7項目の事実確認に関する資料のみを持参し、私的文書に関する資料は持参していない。
(11) 7月18日
百条委員会へ資料を提出したが、 「告発文書」7項目の事実確認に関する資料のみであり、私的文書に関する資料は提出していない。
3 「緑ファイル」の処理状況について
(1) 「週刊文春」7月25日号の記事内容によれば、元県民局長の私的情報の漏えいがあったとされるのは令和6年4月なので、この時点で存在していた紙に印刷された資料が問題となるところ、前項に記載のとおり、この時点で存在していたのは「緑ファイル」 5部のみであり、「ドッチファイル」2セットは作成されていないので、以降、もっぱら「緑ファイル」のみについて検討する。
(2) 5部の「緑ファイル」については、うち1部(片面印刷のマスター資料)は、人事課内のロッカー内に現在も保管されている。また、H(上田)氏はシュレッダー処理し、G(井筒?)氏は溶解処理したと認められることは前記認定のとおりである。また、I(副課長?)氏は、ざっと目を通した後、自席の鍵付きの保管場所に入れていたが、4月下旬くらいに人事課内の鍵付きのロッカー内に移しており、外部には持ち出していない。
(3) E(井ノ本)氏は、「緑ファイル」の処置につき、当委員会の調査において、次のとおり、人事課に返したと供述した。
- 「フラットファイルは、いつも機密情報を保管するのに使うロッカーに入れて保管していた。」
- 「フラットファイルは、 1週間から10 日ほどして人事課に返したと思う。人事協議の資料は紙で来るので、いつも見たら返して溶解している。誰に返したかは覚えていないが、他の案件の資料を持ってきてくれたときに、封筒に入れて返していると思う。」
(4) しかしながら、令和6年7月に「週刊文春」の報道があったことから「緑ファイル」の保管状況を確認することになり、G(井筒?)氏がE(井ノ本)氏に「緑ファイル」の所在を確認した際、E(井ノ本)氏は「緑ファイル」受領の事実を否認し、総務部長室でE(井ノ本)氏とG(井筒?)氏が探したが見つからなかったという経緯がある。
一方、E(井ノ本)氏は、当委員会に対しては、この姿勢を覆し、同年11月26日に行われた事情聴取において、「緑ファイル」を受け取った事実を認めるに至った。【供述の変更1】
(5) このように、重大な点について大きな変遷があることに加え、「緑ファイル」は、その内容からしてその取扱いについては細心の注意が必要であることはE(井ノ本)氏も当然認識していたはずであるから、返還するに際しても信用のおける限られた職員に預けるのが普通と考えるべきところ、「人事課の若い担当の職員に返したが、誰に返したかは覚えていない」というのは不自然で容易に採用しがたい説明である。
また、一般職員からすれば人事課のラインにおいて明らかな上席者に位置する E(井ノ本)氏が、氏名の分からないような「若い」「担当の人」に「緑ファイル」を渡したとすれば、その職員は、当然、「緑ファイル」を独断で処理したりせず、例えばH(上田)氏やI(副課長?)氏等のようなしかるべき権限のある上司に渡すか、報告してその指示を仰いだはずである。
ところが、I(副課長?)氏は「E(井ノ本)氏から緑ファイルを返された記憶はない。他の職員に返されたこともない。もし緑ファイルが返されていたら、人事課のロッカーで保管されているはず。他の職員が受け取っていれば報告が上がる。」と返還の事実を否定しており、今回事情聴取した人事課所属の職員の誰もE(井ノ本)氏から「緑ファイル」の返還を受けたことを認めるものはいない。
(6) ただし、E(井ノ本)氏は、当委員会に対し、「文春の記事が出た後、総務部長室で、G(井筒?)氏と一緒に、机の周りでファイルを探したことはある。G(井筒?)氏に対して、ファイルを受け取った記憶がないとは言っていない。ファイルはもらったが返したと記憶しており、そう言ったと思う。もしあったら困るので、全部開けて探した。」と供述する。
しかしながら、G(井筒?)氏は、「『でも部長、Nが持って行ってますよね。ありませんか?』と聞いたら、E(井ノ本)氏は慌てた感じで、『※省略』と引き出しや書棚を開けてみたり、「緑ファイル」の確認を始めた。『ないですか?』と聞いて一緒に探したがなかった。
『※省略』と。『おかしいですね、担当は渡したと言ってますから。僕も同じものをもらっているし。』と。そんな会話をしたのははっきり覚えている。」と明確な記憶に基づいて供述しており、E(井ノ本)氏から「ファイルはもらったが返した」というようなことを言われたとは供述していない。したがって、E(井ノ本)氏のこの供述は、前記G(井筒?)氏の供述と整合せず、信用性に乏しいと言わざるを得ない。
(7) したがって、この点に関するE(井ノ本)氏の供述は採用しがたいところ、その他本件で取り調べた全資料によっても、同部長に手渡された「緑ファイル」が処分されたことを認めるに足りるものはない。よって、少なくとも令和6年4月時点では、「緑ファイル」は存在していたと判断するほかはない。
4 調査対象者について
(1) 以上の点を踏まえて検討を進めるに、「週刊文春」7月25日号の記事には、次のように記載されている。
① 人事課を管轄する総務部長が、大きなカバンを持ち歩くようになった。中には大きな二つのリングファイルに綴じられた文書が入っており、県職員や県議らにその中身を見せて回っていたようです(同記事22頁2段目)。
② リングファイルの中身は、押収したPCの中にあったX(渡瀬)氏の私的な文章。どうやらその文章は、四人組によって、県議や県職員の間に漏れていたようです。事実、私もこの四月に産業労働部長から文章の内容を聞かされました(同 22頁3段目)。
③ 「(産業労働部部長が)もしアイツ(X(渡瀬)氏)が逆らったら、これの中身、ぶちまけたるねん」(同22頁3段目)
(2) これらによると、元県民局長の私的情報を漏えいした疑いがあるとして報道されたのは、個人名は伏されているものの、その役職名から判断して、E(井ノ本)氏及びF(原田)氏であると推認できるので、まずこれら2名に関する調査結果について、以下に述べることとする。
5 E(井ノ本)氏について
(1) 令和6年11月22日(金)に実施された事情聴取において、T(迎山)議員は、 E(井ノ本)氏から私的情報を見せられた経緯について、要旨、次のように供述している。
ア 4月19日の夕方16時30分頃、会派の控え室に一人でいたときに、両手に大きいファイルが2つか3つ持ってE(井ノ本)氏が入ってきた
イ 自分とE(井ノ本)氏は割と親しく、忌憚なく話をする関係だが、自分のデスクの横の簡単な応接セットのところで、E(井ノ本)氏から「これ、見てくださいよ」「ほんまたまったもんちゃうで、(※省略)。A(渡瀬)氏はなにやっとるんやという感じ。こんな人間が作った文書信用できるわけないやろ。(※以下省略)」ということを言われた。
ウ 一瞥して、事実かどうかは分からなかったが、A(渡瀬)氏の私的情報が日記のような形式でずっと記述されているようだった。
エ 自分もわけが分からなかったので、驚きながら頁をめくって見ていた途中でも、E(井ノ本)氏が「こんなことも書いている」と指摘して見せてきたりした。自分はそれが事実かどうか分からないので、 「嘘ではないか、そんなわけがないのでは」という趣旨の発言をしながら見ていた。
オ 実際見せられたファイルは、10センチほどの厚さでA4の紙がぎっしり入っているファイルである。
力 全部は見ていない。さーっと見て、それが事実であったら、自分が持っているA(渡瀬)氏達のイメージとあまりにもかけ離れてたので、信じられないと言った。E(井ノ本)氏は、「※発言内容省略」と言っていた。
キ その内容が衝撃だったのと、E(井ノ本)氏の立場でその文書を自分に見せた行為自体がまずいのではないかと思った。
(2) また、T(迎山)議員と同一日に事情を聴取したS(山口)議員も、要旨、次のように供述している
ア 日付は覚えていないが、令和6年4月22日の前、E(井ノ本)氏が話があると訪ねてきたので、乙(自由民主党)会派の会議室で会った。アポイントは取っていなかった。
イ E(井ノ本)氏は、「A(渡瀬)氏のパソコンからこんなものが出てきました、見て下さい」と言い、ファイルを開けて見せてきた。
ウ 自分は目が悪いので、よく見えず、「何ですか」と聞いたところ、E(井ノ本)氏は「(※省略)日記です。ちょっと(※省略)日記なんです。」と答えた。「(※省略)などの記載がある」と説明を受けた。
エ 2列のエクセルで、左側に漢字で■■と書かれていた。E(井ノ本)氏から、「(※省略)おるんですわ。」と言われた。「■■」というのは、■■■■の■■氏のことだというのもE(井ノ本)氏から説明を受けたと思う。
オ E(井ノ本)氏とは、幹事長として、仕事上頻繁に付き合いがあったが、プライベートな関係はない。
力 このとき見せられたのは、200枚から300枚くらいのファイル。カラーの写真はなかった。
(3) さらに、令和6年12月20日に行われた事情聴取においてU議員も、要旨、次のように供述している。
ア 4月の中旬頃までのことであるが、元県民局長の私的情報であることを前提として、ファイルを開いて(文書を)見せられたことはある。
イ 自分に見せたのは、E(井ノ本)氏である。
ウ 日付は覚えていないが、乙(自由民主党)会派の執行部の控え室に、E(井ノ本)氏が訪ねてきて「ちょっと」と話があるとのことだったので、幹事長室の横にある大会議室の幹事長室側の応接セットのソファーに移動した。限られたメンバーで話をするときに使う、仕切られて音の漏れないスペースなので、内密の話と思って移動した。
エ 自分とE(井ノ本)氏と二人のみ。大会議室には誰もおらず、執行部の控え室には執行部の議員、女性職員がいた。
オ このときは、E(井ノ本)氏はアポイントは取っていなかった。自分が県庁にいることは、分かる。個人ではなく、県議団の執行部に何かの報告で立ち寄った後、声を掛けられた。
カ E(井ノ本)氏は、二つのファイルを持っていた。報告の際にも持っていたファイルかは記憶が定かでない。ファイルの色の記憶はないが、硬い表紙の分厚いファイル。
キ 会話までは覚えていないが、E(井ノ本)氏が「こんなことあるんですよ」と言って、ファイルの一部を開いたと記憶している。
ク 開かれたファイルには、日付と横に書く欄。そこに(※省略)という記述があった。手書きではなく、(エクセルかは分からないが)パソコンで作った資料。
ケ 元県民局長個人の情報であるという前提だったように思うが、自分はすごくびっくりし、本当にそこが出所か分からないので、すぐに席を立った。
(4) 以上のとおり、前記3名の議員は、いずれもE(井ノ本)氏から、元県民局長の私的情報について口頭での説明を受け、紙に印刷された資料を提示等されたと供述しているのに対し、E(井ノ本)氏は、令和6年11月26日に行われた当委員会の事情聴取において「県会議員に私的文書のファイルを見せて回ったことはない。そのように言われているとしても、その内容は虚偽である。」と供述してこれを否認していた。
(5) そこで、これらの相対立する供述の信用性について検討するに、仮にE(井ノ本)氏が前記3名の議員のところに赴いたこともなく、元県民局長の私的情報について県謙会議員に見せたことがなかったとすれば、前記3人の議員(T(迎山)議員、U議員、S(山口)議員)は、いずれも事実に反した供述をしたことになる。しかも、それらの供述の内容は、①E(井ノ本)氏が一人で、②各議員の所属する会派の控室等にいる各議員に対し、③アポイントを取ることなく訪れ、④(厚いファイルかどうかは差異があるが)手持ちの資料を机の上においてこれを開示して見せ、⑤その中身の概要を説明した、⑥3名の議員が見たとする内容も、手書きではなくパソコンで作成されたと思われる日記のような形式で、⑦その作成者の私的情報の内容が記されていた、というように骨子においてほぼ共通しているところからして、 3名の議員において事前に意を通じて上記供述を行った可能性もあることになる。
しかしながら、兵庫県議会で違う会派に所属する議員であるT(迎山)議員と他の2名の議員が、その当時において、たとえ知事に対する立場に共通するものが多少あったとしても、意を通じてそのような虚偽の事実を創作する積極的あるいは合理的な理由は乏しいと考えるのが相当であるし、これまでに当委員会が取り調べた中に「意を通じていた」ことをうかがわせる資料や事情はない。
また、特にT(迎山)議員の供述は、前掲のとおり、日時、場所、E(井ノ本)氏の発言内容、それに対するT(迎山)議員の応答、私的情報の内容、それを見てのT(迎山)議員の印象など、具体性や迫真性に富んでいて流れも自然であり、創作されたものと認めることは困難というべきであるところ、これと骨子において共通する他の2名の議員の供述も、程度の差はあれ、同様の評価をすることができるものである。
(6) 加えて、E(井ノ本)氏は、当委員会において百条委員会における供述とは異なる証言をしている。すなわち、E(井ノ本)氏は、令和6年10月25日の百条委員会において、元県民局長の私的情報を打ち出した資料を所持した事実は認めたものの、これを第三者に見せたかという質問に対しては、「守秘義務違反と評価される違法行為はしていない」としつつ、「守秘義務違反行為をしたか、していないかということを証言すること自体が手がかりとなって守秘義務違反の責任を問われる可能性が生じる」との理由で証言を拒んだ模様であるが、当委員会における事情聴取においては、供述を拒むことなく、第三者に見せたことを明確に否認している。【供述の変更2】
(7) これらの供述について検討するに、 前記前段の「秘密保持義務違反はしてないが、供述は拒否する。」の「秘密保持義務違反はしていない」というのは、本件においては、正に「だれにも見せていない。漏えいしていない」ということを意味するとしか解されないところであるし、「百条委員会のときと異なり、当委員会に対して『誰にも見せていない』 と言えるのは、当委員会がA(渡瀬)氏の私的情報の内容を承知しているからだ。」との弁明は、合理的な理由とはいえず、説得力に欠けるというほかはない。これらの供述は、E(井ノ本)氏の供述全体の信用性に関する当委員会の評価を何ら高めるものではなく、むしろ逆に不信を強めるものであるといえる。
(8) 以上のところから、当委員会は、当委員会の事情聴取におけるE(井ノ本)氏の供述は信用性に乏しいと言わざるを得ず、採用することは困難であると判断した。そして、当委員会は、T(迎山)議員、U議員及びS(山口)議員の供述に基づき、E(井ノ本)氏は、少なくとも、これらの3名の議員に対し、元県民局長の私的情報にかかる紙に印刷された資料を提示ないしその一部を口頭で伝えるなどして、元県民局長の私的情報を漏えいしたと認めるのが相当との結論に達していた。
(9) しかるところ、E(井ノ本)氏は、令和7年2月に代理人弁護士の作成した弁明書を提出し、「前記3名の議員に面会し、元県民局長の私的情報の概要を、情報共有の意図で、口頭で伝えたことはある。ただし、具体的な資料は開示してはいない」と、それまでの供述をさらに大きく変え、当委員会の認定した前記3名の議員への面会を認めるに至った。しかも、これはE(井ノ本)氏の単独の判断によるものではなく、「知事及び元副知事の指示によるものである」としている。【供述の変更 3】
当委員会が、これらの点について追加調査の依頼を受けたことは本報告書の冒頭の「はじめに」で述べたところであり、その調査の結果は「第5」において後述する。
6 F(原田)氏について
(1) 週刊文春の記事には、「リングファイルの中身は、押収したPCの中にあったX(渡瀬)氏の私的な文章。どうやらその文章は、四人組によって、県議や県職員の間に漏れていたようです。事実、私もこの四月に産業労働部長から文章の内容を聞かされました」と記載されている。
(2) しかし、F(原田)氏は、当委員会に対し、「A(渡瀬)氏の私的文書があることを最初に知ったのは、3月25日、副知事がA(渡瀬)氏のところに調査に行って、帰ってきてから連絡があり、A(渡瀬)氏の私的文書が出てきた、日記みたいに書いてあった、と聞いた」と供述するものの、「私的文書の具体的な内容は全く見ていない。■■(白川?)に話を聞かなければならない、■■(白川?)のパソコンを調べなければならない、人事上の調査をしなければならないということで、(■■(白川?)から)話は聞いたが、私的文書の中身は見ていない。」「E(井ノ本)氏から私的文書を打ち出した紙を見せられたことはないし、預かったこともない。E(井ノ本)氏が私的文書を持っていたことは知らなかった。」「週刊文春からインタビューを受けた。文春7月25日号の記事を読んだが、記事の『ぶちまけたる』との記載は、自分はぶちまける物を持っていないのでぶちまけられない。 『これの中身』と記載されている『これ』については、一切持っていない。」と供述して、元県民局長の私的情報を所持していたことはないと主張する。
(3) この点に関しては、H(上田)氏も「F(原田)氏が緑ファイルのデータに触れるということはなかったはず。」と供述しているところ、現在までの調査資料中に、F(原田)氏が印刷された元県民局長の私的情報を所持していたと認めるに足りるものはない。
(4) ただし、H(上田)氏は、F(原田)氏が元県民局長の私的情報を知っていたかどうかについて、「私的ファイルが見つかったことは、(H(上田)氏は)副知事に報告した。百条委員会では、F(原田)氏は『副知事からそうした資料があるという話を聞かされた』とはっきり説明していたようだ。F(原田)氏は、■■(白川)さんの上司にあたるので、 ■■(白川)さんを退職させるかさせないかという話は(関与の有無を確認してからになるので)、退職を止めますよという話は当然F(原田)氏にも副知事なりから入っていたはず。その理由として、こういうの(元西播磨県民局長の私的ファイル)が見つかっているという話はF(原田)氏は聞かれていたと思う。百条委員会で、F(原田)氏は最初『人事課の職員に見せてもらった』と述べたので人事課から事実が異なると猛抗議したところ、翌日の百条委員会でもう一回呼ばれて『副知事から聞かされた。』と訂正された。」
さらに、F(原田)氏自身も、「百条委員会では、人事課の職員から聞いたと述べた。文書を見たのではなく、話をしたということ。その後、副知事から聞いたと訂正したが、それは、3月25日に副知事から聞いたこと((※省略)であること、日記みたいに書いてあること)を証言した。」と、私的情報の(少なくともその)概要につき、認識していたことを認めている。
(5) 以上のとおりであって、F(原田)氏が、元県民局長の私的情報の(少なくともその)概要を認識していたとは認められるものの、私的情報に関する印刷物を所持していたと認めるに足りる資料はなく、また、同部長が、元県民局長の私的情報を県職員に漏えいしたと認めるに足りる十分な資料はないから、当委員会としては、その事実を認定することは困難というほかはない。
7 開示資料の同一性についての疑問
(1) なお、前記3名の議員のうち、T(迎山)謙員は、E(井ノ本)氏が持参した資料について、前述のとおり、具体的に供述している。また、U議員のファイルの厚さにかかる供述、すなわち、聴取時に当委員会委員長の持参していた厚さ5cm程のハードカバーのケースの「ほぼ倍くらい」との供述も、ほぼT(迎山)議員のそれと一致しているところ、これらはフラットファイルに綴じられた「緑ファイル」とは整合しない。これに対し、S(山口)議員は、「自分の認識は紙ファイルである。ファイルの色は緑色と記憶しているが、あいまいである。」と供述しており、これは「緑ファイル」と整合するようである。
(2) これらの齟齬については、確定的に判断することはできないものの、前二者の供述がかなりの程度一致しているのに対し、S(山口)議員は自らも記憶があいまいであるとしているので、E(井ノ本)氏が同じ資料を持参したとすれば、ハードケースによる厚い資料を提示したと考えるのが相当といえるが、前記S(山口)議員の供述からすれば、E(井ノ本)氏が「緑ファイル」をその時点まで保持していた可能性も否定できない。
(3) ただし、前記3名の議員のいずれもE(井ノ本)氏から紙に印刷された資料を見せられたという点では共通しているところからすれば、そのいずれにせよ、E(井ノ本)氏が紙に印刷された元県民局長の私的情報の一部を提示したことについては変わりはなく、この点は当委員会のE(井ノ本)氏の漏えい行為にかかる前記認定に何ら消長をきたすものではない。
8 漏えいの動機ないし目的
(1) 当委員会の前記認定に影響を与えるというものではないが、E(井ノ本)氏がこのように元県民局長の私的情報を漏えいした動機ないし理由について検討するに、この点に関しては、「E(井ノ本)氏は何をもってそういうことをしたかという理由が分からない。何か理由があって人に見せる、その理由が僕は分からない。」との V(内藤?)議員の供述もあったが、私的情報の提示を受けた3名の議員からは、次のような供述が得られている。
① S(山口)議員「E(井ノ本)氏が私的文書を見せたのは、告発文書を書いた人物のバックグラウンドを知らせる趣旨と思う。」
② T(迎山)議員が聞いたE(井ノ本)氏の発言「こんな人間が作った文書信用できるわけないやろ。」
③ U議員「E(井ノ本)氏がどういうつもりで見せたのかは聞いていない。自分が思ったこととしては、こういうことをやっている人のいうことが信用できるのか、ということだと思う。」
(2) これらの供述からすれば、前記3名の議員は、E(井ノ本)氏の漏えいの動機ないし目的について「元県民局長の私的情報を暴露することにより、その人格ないし人間性に疑問を抱かせ、ひいては告発文書の信用性を弾劾する点にあった」と捉えていると理解されるところ、これは一定の説得力があると評価できるものである。
(3) ただし、E(井ノ本)氏は、前記のとおり、当委員会における聴取時の主張を大きく変更し、令和6年4月下旬頃に前記認定の3名の議員に面会し、口頭で元県民局長の私的情報のごく一部の概要を説明した限度でその事実を認めるに至り、同時に、それが知事ないし元副知事の指示によるものであると主張するに至ったことは、すでに指摘したとおりである。これは、重要な論点と思われることから、当委員会は、必要と思われる追加調査を実施した。その結果は「第5」において詳述する。
9 他の議員に対する漏えいの可能性
(1) さらに敷衍すれば、E(井ノ本)氏に関しては、前記3名の議員のほかにも元県民局長の私的情報を提示したのではないかとの伝聞供述が得られている。前記3名の議員は、E(井ノ本)氏から提示を受けた当時、それぞれ所属する会派の役員であり、 E(井ノ本)氏の動機ないし理由が前記認定のとおりであったとすれば、当然、他の会派の役員である議員にも提示していても不自然ではないと思われる。T(迎山)議員も「私だけに見せるはずはないので、順番にしかるべき人に見せていって、『あ、T(迎山)ちゃんおるわ』とついでに見せに来た感じ。」と供述している。
(2) 具体的な議員名として、T(迎山)議員は「噂レベルで、本人には確認していないが、乙(自由民主党)会派のS(山口)さん、V(内藤?)さん、そして丙(維新の会)会派のQ(岸口)さんで、私(T(迎山)議員)が見せられたということがまことしやかに議会の中で噂になっていた。」と供述している。このうち、T(迎山)議員とS(山口)議員は、前記のとおり、E(井ノ本)氏から提示されたことを認めている。
(3) ただし、V(内藤?)議員は、「乙(自由民主党)会派の会派の総会が定例的にあるが、そのときに某議員が全員がいる前で、『私的文書を見た議員がいる』と。『それはV(内藤?)議員です』と、こう言われた。・・・私は即座に『ありえません。見た記憶はない』とはっきり言った。」と供述し、その事実を否定している。この点については、調査を尽くすも漏えいの事実を裏付ける具体的根拠が見当たらず、E(井ノ本)氏からV(内藤?)議員への漏えい行為を認めることはできないというほかはない。
(4) また、Q(岸口)議員(及び同会派のR(増山)議員)も、丙(維新の会)会派に属する議員に対する漏洩はなかったことを、週刊文春の本件報道以後に開かれた会派の総会で確認したと供述して、やはりこれを否定しているので、本件における各資料のうち、同供述を覆すに足りるものがない以上、E(井ノ本)氏から同議員への漏えい行為があったと認定することは困難である。
(5) ただ、週刊文春の本件報道によれば、「六月ごろから、今度は維新会派の県議たちの間にも私的文章が流出したようだ(※増山県議は否定)。すると、維新の岸ロ実県議と増山誠県議が、百条委員会の場でX(渡瀬)氏のPCに入っていた全てのファイルを公開するよう強く主張し始めた」(週刊文春22頁4段目)とされている。この点についてのQ(岸口)議員の説明は、「私とR(増山)委員は、人事課の調査資料を見ないと、 A(渡瀬)氏の尋問などできないので、全部資料として提出すべきだと主張した。この時点では、プライベートな情報がどの程度のものか知らなかったので、確認した上で、不要なものは外したらよいという趣旨だった。すべて出せと言ったのは、資料を包括的に出して欲しいということ。」「7月8日以降の理事会の多数決で、丙(維新の会)会派は開示を求めたが、丙(維新の会)会派以外の会派は開示に反対した。私は、まったく資料を確認せずに委員会に入るのはおかしい、必要かどうかは人事課ではなく、委員に判断させるべきと主張した。」というものであるところ、これらの供述は相応の合理性を有するものともいえるから、前記週刊文春の記事のみをもって、同会派の議員が元県民局長の私的情報の提示を受けていたと短絡することもできない。
(6) また、新聞報道等によれば、Q(岸口)議員は、当委員会の事情聴取が行われた昨年11月19日より前の時点において、自らがZ(立花)氏に元県民局長の私的データの一部が記載された書面を交付したか、または他の者がこれを交付する席に同席していたことを認めるに至った模様である。さらに、Q(岸口)議員と同じ会派に所属し、百条委員会の委員でもあったR(増山)議員も、百条委員会における元副知事の証言の秘密録音をZ(立花)氏に提供したことを認めるに至った。
(7) これらは、両議員の当委員会に対する供述の信用性に大きな影響を与える事情である。しかしながら、このことをもって両議員の供述が事実に反するものであるとまでいうことはできないから、これらの事実を踏まえても、両議員がE(井ノ本)氏から元県民局長の私的情報を聞いていたと認定することはできないというほかはない。
なお、当委員会は上記両議員に対して、なぜ当委員会の事情聴取の際にそのことを告知しなかったか等につき、照会文書を発送したところ、両議員からその点を弁明する回答が得られた。
10 E(井ノ本)氏の指摘する「他の情報の出所」について
(1) E(井ノ本)氏は、当委員会の事情聴取において、元県民局長の私的情報の出所として「元県民局長のUSB及びW(竹内)元譲員がもうひとつの情報の出所だと思う。」と供述し、「なぜW(竹内)元議員だと思うか」との質問に対しては、「野党で唯一の告発文書の送付先であり、W(竹内)元議員と元県民局長が頻繁に連絡を取り合っていたということは聞いていた。」と説明している。
(2) しかし、「野党」の中で唯一の告発文書の送付先であったことから直ちに同議員が元県民局長の私的情報を漏えいしたと結論付けることはできないし、たとえ元県民局長と同議員が頻繁に連絡を取り合っていたとしても、やはりそのことから漏えいの事実を認めることは困難である。さらに、告発文書の送り先であったり、頻繁に連絡を取り合う間がらであったとすれば、W(竹内)元議員があえて元県民局長のプライバシーに関わる情報を同人の意に反して公表するような行動をするとは思われないから、一層、同議員が情報の出所であると認めることはできない。
(3) また、元県民局長のUSBメモリーは、前記認定のごとく、令和6年3月25日時点で本人により回収されているところ、本人があえて自らの私的情報を外部に発信することは考えにくいし、これまでの調査によっても同USBメモリーから元県民局長の私的情報が漏えいしたと認めるに足りる資料はない。
(4) したがって、E(井ノ本)氏の前記供述は採用できない。
第4 ※省略
第5 E(井ノ本)氏の新主張について
1 新主張の概要
人事課によると、E(井ノ本)氏は、代理人弁護士作成の令和7年2月14日付け「弁明書」を人事課に提出し、その中で、当委員会に対する供述を大きく変更し、当委員会が認定した3名の議員と、昨年4月中下旬頃に面会したことを認め、大要、次のように主張するに至った模様である(なお、同弁明書提出に先立って行われた人事課による事情聴取においても同様の趣旨の供述を行っている模様である。)。
(1) E(井ノ本)氏は、上司(知事及び元副知事)の指示に基づき総務部長の職責として正当業務(議会調整業務を含む。)(2つの外部通報【注】、正当な理由・違法性阻却事由)を行ったにすぎない。知事や副知事からの指示があった場には D(小橋)氏も同席していた。
【注】いわゆる告発文書と元県民局長の私的情報が記載された文書に係る通報を指す。
(2) 元県民局長の私的情報は「秘密」として保護するに値しない。
(3) (E(井ノ本)氏から元県民局長の私的情報の開示を受けたとする)3名の議員の証言等は信用性に欠け、誇張、虚偽、邪推をもってE(井ノ本)氏の正当業務行為を守秘義務違反にすり替えているので、E(井ノ本)氏の行為等は、「職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし」たとは評価できない。
(4) E(井ノ本)氏の行為等によって懲戒処分指針に定める秘密漏えいの懲戒事由である「公務の運営に重大な障害を生じさせた」とは評価できない。
2 従前の主張にかかる供述内容の確認
E(井ノ本)氏は、前記3名の議員に対する面会について、当委員会における事情聴取に際しては、乙(自由民主党)会派控室に挨拶に行ったことはあるかもしれないが、その他の会派の議員控室に行ったことはなく、元県民局長の私的情報について話したこともないとして強く面会の事実を否認していた。
3 新主張についての検討
(1) E(井ノ本)氏は、3議員と面会したことを認めるに至ったが、あくまで元県民局長の私的情報のごく概要を口頭で説明したに過ぎず、私的情報が印刷されたファイル等を持参したことはなく、それを提示したことはないとしているにしても、このような大きな変遷は、当委員会のE(井ノ本)氏の供述に対する信用性をさらに減少させる方向に働く事情となるものと評価せざるを得ない。
(2) 新主張(1)については、重要な論点であるので、項を改めて検討することとする。
(3) 新主張(2)(「元県民局長の私的情報は「秘密」として保護するに値しない」)については、当委員会としても、第1の第6項に記載のとおり、元県民局長の個人情報であり、地方公務員法上保護されるべき「秘密」に該当すると解するのが相当と考えるものである。なお、前述したように、令和7年3月18日付けで、県人事課において、元県民局長の私的情報は非公開情報と決定された模様である。よって、E(井ノ本)氏のこの新主張は採用できない。
(4) 新主張(3)(3議員の供述は信用性がない)との点についても、当委員会としては、今回のE(井ノ本)氏提出の弁明書記載の新主張及び人事課の事情聴取に対する供述の趣旨を踏まえて再検討しても、概要、「E(井ノ本)氏がそれぞれの議員控室を一人で訪れ、紙に印刷した元県民局長の私的情報を見せた(見せようとした)」との前記3議員の供述の信用性は揺るがないから、E(井ノ本)氏のこの点の新主張についても採用できず、調査の認定を変える必要はないことに一致した。
4 新主張(1)のうち「知事ないし元副知事の指示」の有無について
(1) E(井ノ本)氏が、3名の議員に対し、一定の漏えい行為をしたことについて知事ないし元副知事の指示があったか否かについては、E(井ノ本)氏もこれまでその旨の供述をしてこなかったことから、調査の対象事項となってこなかったが、今般、次のように主張を変え、人事課による事情聴取や弁明書において、それに沿う供述をするに至った。
「令和6年4月4日か5日頃、E(井ノ本)氏が、D(小橋)氏同席の席上で、知事に対し、元県民局長の公用パソコン内に、元県民局長の私的情報にかかる大量の文書等があることが分かったなどと報告したところ、知事は、E(井ノ本)氏に対し、要旨、『そのような文書があることを、議員に情報共有しといたら』と指示した。」
(2) そこで、当委員会は、①E(井ノ本)氏に指示したとされる知事、②その場に同席していたとされるD(小橋)氏、③知事の前記指示に同調したとされる元副知事から、それぞれ事情を聴取した。
(3) まず、知事からの指示があった時に同席していたとされるD(小橋)氏は、令和7年3月4日に行われた事情聴取の際、「昨年4月上旬ごろ、元県民局長の私的情報の件を含めて知事に報告した際、いろいろな案件がある中で、その私的情報があったということも含めて根回しというか議会の執行部に知らせておいたらいいんじゃないかという趣旨と理解できる知事からの発言があった」「(私的情報の)中身全部持っていけと、そんなことじゃなくて『(私的)情報があるということは情報共有しておいたら』と言われたんだなと思った」と、E(井ノ本)氏の新主張に沿う供述をして、知事からの指示があったことを認めている。また、その後、知事からそのような指示があったことを副知事に報告した際には、「副知事が『そらそうやな。必要やな。』という発言があったと思っている」とも供述している。ただ、知事からは、誰とどのように情報共有をしておくというような具体的なことはなかったとのことであった。
(4) 以上の供述からすると、D(小橋)氏としては、知事からE(井ノ本)氏に対し「元県民局長の私的情報そのもの」を取り上げて県議会と情報を共有しておくようにとの指示があったものではないが、他の重要審議事項と併せて「元県民局長の私的情報」の内容についても議会の執行部に「根回し」をしておくようにとの指示があったと理解したことがうかがわれる。
(5) 一方、知事は、令和7年3月6日に行われた当委員会の事情聴取において、概要、次のように述べて、この事実を否定している。
「昨年4月に入ってから、元県民局長のパソコン上に今回の問題となっている文書の作成以外に(※省略)などの私的情報があったという一連の報告はあったと思うが それを聞いてその処理に関して何か指示をしたことはないE(井ノ本)氏に、そういった情報を議会の執行部に共有しておいた方がよいとことを発言したこともない。
ただ、例えばどこの自治体でもあるように、予算とか大学無償化とかの政策に関することで議会との情報共有を指示することもあるが、今回はそういったことについて議会筋と情報共有をしておくようにというような指示をE(井ノ本)氏にしたこともない。
E(井ノ本)氏は、総合調整の窓口である総務部長として、独自の判断で議会側との情報共有(いわゆる根回し)をしたものと思う。」
(6) 前記D(小橋)氏の供述からすれば、知事が当時の多くの懸案事項と区別せずに議会の執行部との情報の共有を指示したため、E(井ノ本)氏が「元県民局長の私的情報についても情報共有しておくように」との指示と受け取った可能性もあると考えられるところ、知事は、前掲のとおり、本件については、その点も含めて全面的に否定し、「E(井ノ本)氏が総務部長として自らの判断で議会執行部に元県民局長の私的情報の共有を行ったものである」との趣旨の供述をする。
(7) そこで、これらの相対立する供述の信用性を検討する必要があるが、D(小橋)氏は、週刊文春でも(そのような呼称が実際に用いられていたかはともかくとして)「牛タン倶楽部」とか「四人組」と報じられたように、E(井ノ本)氏とは親しい関係にあり、令和7年2月以降は、職場も同じ部屋で過ごしているということからすると、両名が意を通じて同内容の供述をしている可能性も否定できないが、そのことを裏付ける客観的資料はない。また、これとは逆に、多数の懸案事項がある中で、知事が総務部長であるE(井ノ本)氏に対し、事項を特定せず、一般的に議会筋との情報共有を指示することがあってもおかしくはないと思われるにもかかわらず、前掲のとおり、本件についてはそういった一般的なパターンでの情報共有指示すら否定する知事の供述には不自然さも否めない。
(8) 当委員会は、令和7年3月18日、元副知事から再度事情聴取を行い、知事からの指示の有無等に関して確認したところ、元副知事は、次のように、D(小橋)氏及びE(井ノ本)氏の供述に沿う供述をした。
「自分は知事から直接の指示を受けたことはない。 しかし、昨年4月上中旬頃、おそらくはD(小橋)氏からだと思うが、『知事からE(井ノ本)氏に対し、元県民局長の私的情報について議会と情報共有しておくようにとの指示があった』と聞いたので、特に反対もせず、E(井ノ本)氏において『根回し』をするように指示した。ただし、根回しすべき具体的な会派や、共有すべき私的情報の具体的内容については何も指示しておらず、E(井ノ本)氏の判断に任せ、その後、特段の報告も受けていない。」
(9) 以上のとおり、D(小橋)氏及び元副知事の供述が、時期及び内容においてE(井ノ本)氏のこの点に関する新主張とほぼ一致しているところからすれば、これらの供述の信用性を否定することはできないと評価するのが相当であり、これと整合しない知事の前記供述は採用することが困難というべきである。
したがって、当委員会としては、E(井ノ本)氏は、知事からの指示及びこれと同調する元副知事の指示により、元県民局長の私的情報について、議会の各会派のうち乙(自由民主党)会派及び甲(ひょうご県民連合)会派の執行部に対し、「根回し」の趣旨で前記認定の情報開示(漏えい)を行った可能性が高いと判断せざるを得ない。
(10) ただし、知事及び元副知事も、E(井ノ本)氏が議会に「根回し」するに際して、口頭にとどめるか、何かの資料を、どの程度開示するかなどについては具体的な指示をしていないと認められるから、それらについては総務部長であったE(井ノ本)氏の判断によったものと認めるのが相当である。
5 新主張(1)のうち「正当業務行為該当性」について
(1) E(井ノ本)氏は、知事及び元副知事の指示によって「根回し」の意図で「漏えい」行為をしたことから、これを「正当業務行為」であると主張する。
(2) しかし、その点は、知事及び元副知事の前記指示自体の違法性が問題となることはあっても、E(井ノ本)氏の濡えい行為の違法性阻却事由には該当しないと解するのが相当であるから、当該行為が正当業務行為となることはなく、E(井ノ本)氏がそのような漏えい行為をするに至った背景事情にとどまるというべきである。
6 新主張(1)のうち「外部通報該当性」について
(1) E(井ノ本)氏は、自身の3名の議員に対する提示行為が公益通報者保護法第2条3項1号、第3条3号「へ」等に該当すると主張する。
この点、E(井ノ本)氏の主張によれば、3名の議員に私的情報の資料は提示しておらず、単に口頭で説明したにすぎないことになるが、当委員会としては、前述のとおり認定したE(井ノ本)氏の前記提示行為を前提に検討を進めることとする。
(2) 公益通報者保護法上定められている公益通報となるためには、以下の要件を満たす必要がある(同法2条)。
①法定の者による通報であること
②通報者の役務提供先における事実に係る通報であること
③不正の目的による通報ではないこと
④法定の内容に係る通報であること
⑤現在性または切迫性があること
⑥法定の通報先への通報であること
⑦通報であること
(3) 以上①~⑦の要件は、通報をした時点を基準に判断されることになるが、このうち1つでも欠く場合には、当該通報は公益通報には該当しないこととなる。まず「④法定の内容に係る通報であること」の要件について検討することとする。
ア 公益通報対象事実はいずれかの法令に定める罰則違反行為でなければならないという前提があるところ、この点に関して弁明書では、「他の職員に対する、(※罪名につき省略)(不同意性交等罪?)の疑いを想起させるものである。同刑法違反は、通報対象行為である。」とされている。
イ しかしながら、示された情報からすると記載されている事実が本当にあったかどうかを読み取ることは困難ではなかったかと思われる。
ウ すなわち、当委員会としては、審議の結果、抵触することが疑われるいずれの犯罪についても、構成要件に該当しないとの判断に達した。
エ 弁明書において、E(井ノ本)氏は、4つの理由を挙げて「元県民局長が人事権を背景として、(※罪名につき省略)(不同意性交等罪?)を生じさせたと信ずるに足りる相当の理由があった。」と主張するが(9頁)、本件においてはそれを採用するに足りるだけの資料は見当たらない。
オ また、公益通報対象事実となるためには、少なくとも構成要件の一部が黙示的にでも主張されている必要があるが、本件ではおよそ、E(井ノ本)氏の指摘する刑法上のいくつかの具体的犯罪の構成要件の一部が示されているとは認められず、情報自体からそのような構成要件該当事実がうかがわれるとも言えないので、やはり通報対象事実ではない(通報対象事実がない)と言わざるを得ない。
(4) 以上によれば、E(井ノ本)氏の前記行為は、公益通報者保護法における「通報」の上記4の要件を欠くから、その余の要件について検討するまでもなく、公益通報には該当しないことに帰する。
なお、弁明書では、「告発文書の対象者(E(井ノ本)氏を含む。)に対する名誉毀損、侮辱、信用毀損」「E(井ノ本)氏らに対する虚偽告訴、私企業及び兵庫県に対する偽計業務妨害)」が通報対象事実に当たるとされているようであるが、これはいわゆる告発文書に係る主張であるから、当委員会の調査対象の範囲外である。
7 新主張(4)「E(井ノ本)氏の行為等によって懲戒処分指針に定める秘密漏えいの懲戒事由である「公務の運営に重大な障害を生じさせた」とは評価できない。」
についても、当委員会に委託された調査範囲を超えるものである。
第6 まとめ
以上のとおりであって、当委員会がこれまでに取り調べたすべての資料及びその他の事情を総合しても、これまでに認定したもの以外の漏えい事実を認定することはできない。よって、調査の結論に記載したとおり、報告する。
ただし、当委員会としては、E(井ノ本)氏の漏えい行為は、知事及び元副知事の指示のもとに行われた可能性が高いことに加え、口頭でその概要を抽象的表現で述べるとともに、紙に打ち出された資料の一部を提示するにとどまっており、これを実際に交付するなどのことはしておらず、しかも、開示を受けた3議員側が目を背けるなどして消極的に対応したことから、その私的情報の概要は把握できても、具体的内容を現実に認識したとまでいえるものではないことは留意されるべきであると考えるものである。
以上
週刊文春(令和6年7月25日号)の記載の整理(情報ソースごと)
1 県職員
(1) 「この”四人組”は、みんなもともと人事課出身。二〇一三~一六年に当時総務官僚だった齋藤知事が宮城県に出向していたころ、東日本大震災の復興関連で、兵庫県も職員を派遣することが多かった。するとこの四人組と齋藤知事は仲良くなり、いつも仙台でつるんでいた。兵庫県庁では知事以下五人を『牛タン倶楽部』と陰で呼んでいます」(22頁1段目)
(2) 「人事課を管轄する総務部長が、大きなカバンを持ち歩くようになった。中には大きな二つのリングファイルに綴じられた文書が入っており、県職員や県議らにその中身を見せて回っていたようです」(22頁2段目)
(3) 「リングファイルの中身は、押収したPCの中にあったX(渡瀬)氏の私的な文章。どうやらその文章は、四人組によって、県議や県職員の間に漏れていたようです。事実、私もこの四月に産業労働部長から文章の内容を聞かされました」(22頁3段目)
(4) 「(産業労働部部長が)もしアイツ(X(渡瀬)氏)が逆らったら、これの中身、ぶちまけたるねん」(22頁3段目)
※明記はないが「県職員」の説明と考えられる。
(5) 「X(渡瀬)さんの秘密を暴露することで、X(渡瀬)さんの人間性を貶め、告発文書の信頼性を下げるのが狙いでしょう」(22頁4段目)
2 県OB
(1) 「知事になった齋藤は、『牛タン倶楽部』のメンバーを側近として重用。同時に『根回しは嫌い』を公言し、県庁職員とのコミュニケーションを拒み、四人組への依存を深めていくばかり。敵対的と見なされた者は次々と排除された。最近は、齋藤に意見できる職員は誰もいなくなっていた」(22頁1段目)
(2) 「しかし、知事が勢い任せに『嘘八百』と口にしてしまったことで、県はあの文書を『嘘八百』と結論づけるための内部調査しかできなくなった」(22頁2段目)
3 (総務部長から私的文書を見せられた)ある県議
「総務部長がどういうつもりで見せたのか分かりませんが、見せられた瞬間『これはまずい』と思いました。X(渡瀬)さんに関する極めてプライベートな内容だった」(22頁3段目)
4 自民県議
(1) 「虚偽答弁や答弁拒否をした場合に罰則を科せられるなど強い権限を持つ百条委員会を片山副知事は極度に恐れていた。議会運営委員会や自民党執行部に対し『辞職しますから、百条だけは勘弁してください』と懇願する様子を多くの人が目撃している」(22頁4段目)
(2) 「六月ごろから、今度は維新会派の県議たちの間にも私的文章が流出したようだ。すると、維新の岸口実県議と増山誠県議が、百条委員会の場でX(渡瀬)氏の PCに入っていた全てのファイルを公開するよう強く主張し始めた」(22頁4段目)
5 百条委員会理事
「X(渡瀬)氏は弁護士を通じてプライバシーに関わる資料については委員会で開示しない、もしくは適宜マスキングするなどの配慮をするよう要請しました。委員会としてはプライバシー権保護及び内部告発者保護の観点から要請を受け入れる方向でしたが、維新の岸口県議と増山県議はこれにも最後まで反発していました」(22頁5段目)
6 県関係者
(1) 「昨年11月の阪神・オリックス優勝パレードの件でしょう。万博を見据えた大阪維新の肝いりイベントでした。告発文書には『必要経費を補うため、信用金庫への県補助金を増額し、それを募金としてキックバックさせた』旨の告発がある。実際、昨年のパレード開催直前に県の十二月補正予算で、信用金庫への補助金の財源となる『中小企業経営改善・成長力強化支援事業』について、担当部局は当初一億円で予算要求したが、副知事の指示で四億円に増額したんです」(23頁1段目)
(2) 「副知事の増額指示があまりにも急だったので、知事査定には間に合わなかった。齋藤知事には一億円の要求資料のまま『現在積算作業中です』と説明してやり過ごした。そしてその直後、片山副知事はパレードの寄付金を無事に信用金庫から集めきった」(23頁2段目)
(3) 「ある県職員の自殺です。告発文書には『パレードを担当した課長はこの一連の不正行為と難しい調整に精神が持たず、うつ病を発症した』旨記されていますが、この課長は告発文書が公になった後の四月二十日に自死しています」(23頁3段目)→亡くなった課長の父親「この件については俺はわからへんからな」(23頁2段目)
7 兵庫県職員労組の関係者
「実は、県は担当課長の死自体を認めていません。だからご遺族は公務災害の申請もしようがない。県は『遺族の意向で公表しない』と言っていますが、ご遺族へのお見舞金も、直属の上司であった総務部長が集めないよう言っているらしい」(23頁2段目)
8 産業労働部長
(1) 「週刊文春さんだよね。いろんな情報持ってはると思うんですけど、彼が自分の命を絶ってまで守りたいプライバシーって何なんでしょうね。なんか見せてもらってないんですか?」(23頁4段目)
(2) 「(ご存じなんですか?に対して)心当たりはね。あの人のことずっと昔から知ってるんで、こういうことなのかなって想像はできますけど」(23頁4段目)
9 若者・Z世代応援等調整担当理事
「(告発文に)書いてあることは事実ではない。私自身はそう思ってます」(23頁4段目)
10 総務部長
「(X(渡瀬)氏の極めて私的な文章を県議に注進して回るなどした)事実はな
い」(23頁4段目)
11 岸口実議員
「中身を見ないと、何が書いてあるのか判断つかないじゃないですか。確認しないとわからないものを見せてくれと言ったんです。疑惑の真相を知るためには、本来は幅広く調査をすべき」(23頁5段目)
12 片山安孝元副知事
(1) 「(X(渡瀬)氏のプライバシーが流出している件について)そういうのが出てるの?」(23頁5段目)
(2) 「亡くなった理由は、百条委に召喚されることが苦になったからだと僕は前から言ってます」(23頁5段目)
13 齋藤元彦知事(書面回答)
「(百条委員会の無力化を狙う維新県議らの動きを止めなかった不作為がX(渡瀬)氏の死を招いたのではとの質問に対し)私は関与しておりません。私としては、現在行われている各調査において、真実が明らかになることを期待しております」(23頁5段目)
以上