2024/12/25 百条委員会の概要
議題
| 議題 | 証人・参考人 | |
|---|---|---|
| 1 | 参考人招致 | のぞみ総合法律事務所 結城大輔弁護士 |
| 2 | 証人尋問 | 片山安孝元副知事 |
| 3 | 証人尋問 | 斎藤元彦知事 |
資料
議事録(公式)
2024/12/25 百条委員会の内容
参考人招致(結城大輔弁護士)
動画
議事録(文字起こし)
○委員長(奥谷謙一)
それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
次は、参考人招致であります。
本日は、本委員の調査のため、公益通報者保護についてご講演をいただくため、大変お忙しい中にもかかわらず、のぞみ総合法律事務所の結城大輔様にお越しをいただいております。
まず、私のほうから結城様のご経歴について簡単にご紹介させていただきます。
結城様が所属されておりますのぞみ総合法律事務所は、内部通報、公益通報について、消費者庁とともに共同で講演、セミナーを行われるなど、企業の公益通報者保護法への対応を支援されております。
その中で、結城様は公益通報制度を専門とされており、多くの企業支援の実績を有されるとともに、数々の書籍、論文を執筆され、講演会の講師も多数務められております。詳細につきましては、お手元に経歴をお配りしておりますので、ご参考にお願いいたします。
それでは、結城様よりご講演をいただきたいと思います。講演終了後には、質疑並びに意見交換の時間を取りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、結城様、よろしくお願いいたします。
○参考人(結城大輔)
おはようございます。弁護士の結城と申します。本日はよろしくお願いいたします。
ただいまご紹介いただきましたとおり、私は、のぞみ総合法律事務所という法律事務所に所属している弁護士でして、1998年の弁護士登録以来、こういった内部告発、名誉毀損、不正や不祥事の調査、公益通報者保護法関係、内部通報関係、こういった案件を多数取り扱ってきております。
今日テーマになっている公益通報者保護法という法律は、2004年に成立をして、2006年に施行された法律ですけれども、成立当時から、この法律、非常に重要だということで、いろいろ研究をしたり、共同で執筆や書籍を出したり、消費者庁と連携しながら、説明会、あるいは企業の社内規程のモデル案をつくったり、説明会をしたりと、こういったことを続けてきております。
本日なんですけれども、そういった公益通報や内部通報の実務に携わっている立場から、今回の文書問題に関して、その事案自体の調査、そういったところに関与する立場ではないものの、実務的な感覚や公益通報者保護法についての私としての理解に関して、見解、コメントを申し述べさせていただきたいというふうに思っております。
こういった事案において最も重要なのは、事実関係をしっかりと調査をして把握することだというふうに考えております。その意味で、現在、こちらの百条委員会、委員会の皆様のほうで続けていらっしゃる努力、あるいはこれから報告書をおまとめになるという段階というふうに理解しておりますが、その努力について、非常に重要なものというふうに考えておりますし、敬意を表しております。少しでも私の本日のお話がお役に立てるものであることを願っております。
なお、私が所属している組織、団体の見解を代表したり調整したりしているものではなく、本日申し上げることは、私個人としての見解であるということだけ、念のため冒頭に申し上げておきます。
公益通報者保護法の話に入る前に、少し内部通報そのものの意義や重要性についてお話をさせていただければというふうに思っております。私は、ACFE JAPAN、日本公認不正検査士協会という協会の理事を務めておるんですけれども、こちらアメリカに本部があるACFEという団体の日本の支部なんですが、こちらの団体で、2年に一度、企業、その他の組織における不正・不祥事に関する調査を行って、その結果を発表しています。
このACFEの調査報告書で、組織の不正を発見する手段として、何が機能を発揮しているかという問いが、毎回必ずあるんですけれども、必ず1位になっている、2位の内部監査を大きく引き離して1位になっているのが通報です。英語ですと、Tipsというふうに書かれているんですが、情報提供、事情を分かっている人からの情報提供をもとにして、不正や不祥事、そういったリスク情報を把握して対応するということが、非常に重要な意味を持っているというデータがいつも出ております。
日本においても同様の状況でして、公益通報者保護法を管掌している省庁は消費者庁なわけですけれども、消費者庁、何度かこれまで内部通報に関する実態調査を行っていまして、こちらに掲げているのは平成28年、2016年の消費者庁の実態調査の報告書の中で、企業ですけれども、社内で不正を発見する端緒として何があるかという問いについて、やはり内部通報が1位になっているというデータが出ていました。
去年から今年にかけても、消費者庁は同じように民間事業者、企業の内部通報の対応についての実態調査を行いまして、その中でも不正発見の端緒としては、内部監査を大きく引き離して、内部通報という答えが出ていたというデータが、今年発表されております。
このように内部通報、すなわち組織の中、企業の中で、何らかの不正、リスク情報について実態を分かっている人からの情報提供、これがきっかけとなって、対応がスタートできる。
こういった不正発見の端緒として重要な意義を持っている内部通報ということが、世界でも日本でも認識されているので、例えば、先ほど私が申し上げたACFEという団体では、経営者や管理職が取り組むべき不正対策、五つの柱があるというふうに発表している。2016年に発表している宣言があるんですけれども、こちらの中でも、五つのうちの一つが内部通報、通報制度を導入する、こういったものの重要性というものが指摘をされているところです。
一方、内部通報という制度なんですけれども、こういった重要性は認識されているものの、実際に通報制度がうまく使われるかというと、非常に難しい面があるというのも事実です。
例えば、企業などで大きな不正や不祥事が起きますと、いわゆる第三者委員会、調査委員会といったものが組織されて、その調査の結果が公表されることがあるというのが、日本では不正・不祥事対応の原則として確立してきているわけなんですけれども。私もそういう仕事をすることがありますし、あるいは私が関与していない案件でも、そういった報告書が公表されると検討しているというような状況ですが、かなりの数の事案において、例えば企業、特に大きな企業であれば、内部通報制度といったものは整備はされている。しかし、当該事案において、不正や不祥事の通報が内部通報制度にされましたかということになると、されてないんですと、活用されませんでしたといったことが報告されているケースが多いです。
なぜ内部通報制度が活用されなかったのかということになると、例えば通報者、誰が通報したかという秘密を守るというふうな制度設計、社内ルールになっているものの、やっぱり誰が通報したかということは分かってしまうんじゃないか、不利益な取扱、通報したことを理由に、それに対する報復、そういったことをしてはいけないというルールにはなっているものの、やはり裏切り者扱いされて、何らかの報復や不利益な取扱を受けるんではないか、こういった不安の声というのが、非常に強いという現実があります。
このことは、消費者庁の調査、これ、先ほど申し上げた調査とはまた別に、同じ時期に消費者庁が去年から今年にかけて行っていた、今度は就労者1万人アンケートという内部通報制度を利用する側に対する調査の結果として、勤務先で重大な法令違反を知った場合に、勤務先等に通報、相談をするかどうかという問いに対して、相談、通報するという問いも6割あった一方で、多分しない、絶対しない、こういった答えも約4割あったという調査結果が出ています。
その理由ですけれども、最初に通報する先として勤務先以外を選んだ理由として、勤務先に相談、通報しても適切な対応が期待できない、不利益な取扱を受けるおそれがある、やはりこういった声というものが現実に上がってきているということになります。
こういった内部通報制度は重要なんですけれども、それに対して、なかなか心理的な抵抗、不安感があって、活用されないという現実を踏まえて、消費者庁は公益通報者保護法という法律、あるいはそれ以外のガイドライン、その他の取組を通じて、何とかこの制度に対する信頼性を向上させて、こういった不正や不祥事、その他のリスク情報を組織が早く把握をして、対応していけるように変えていくべきだという取組を続けてきているというのが、一般に理解されています。
公益通報者保護法という、今日、一つの大きなテーマですけれども、こちらの法律、2004年に成立して、2006年に施行されました。そして、ご案内のとおり、2020年、令和2年に大きな抜本的な改正がされて、2022年、2年前に改正された法律が施行されて、今に至っていると、こういう状況です。
改正された今の公益通報者保護法ですけれども、どんな改正をされたかというと、一言で言えば、公益通報者の保護を強化して、よりこの制度が信頼されるものにしようと、こういう趣旨の改正でした。どういうことかというと、例えば、消費者庁の資料なわけですけれども、ちょっと字が小さくて恐縮ですが、2番というところに公益通報と書かれていて、労働者、退職者、役員がと書かれている、退職者、役員、こういった方々は、2020年の改正前には公益通報者に含まれていなかったんですが、範囲が拡大をされていたり、あるいは4番のところ、通報先と保護の条件ということで、通報先として、事業者、内部、組織の中から事業者の中に通報する以外にも、行政機関とか、報道機関等の第三者とか、こういった通報先、幾つか種類があるんですけれども、こういった行政機関や報道機関等の第三者に対する通報について、どんな場合に通報者が保護されるかという、この保護要件に関して、2020年の改正で、それぞれ少し緩和がされて、保護されやすくなっていると、こんな改正がされました。
そして、5番のところに書かれている事業者の体制整備義務ということで、これが大きな改正の一つのポイントだったわけなんですけれども、事業者、すなわち企業、行政機関、こういった組織は、内部通報についていろんな体制を整備しなければいけないと。これまでは、この改正までは、公益通報に対して、それに対する報復のようなことをすると無効になるよ、してはいけないよと、これは書かれていたものの、じゃあ、どんなふうに通報に対応するか。
ここの部分の取組は、それぞれの組織の自主的な取組に任されていたという状況なんですが、先ほど申し上げたような不安の声、あるいは実際に通報がされない不正・不祥事事例が積み重なっていることなどを受けて、そこ自主的な取組では足りないねと。法律で義務を課して、組織はこういった対応しなければいけないと、こういう体制の整備の義務を課しました。
具体的には、ここに幾つか書かれていますが、内部への公益通報に対応するために必要な体制の整備、窓口を設置する、あるいは対応する担当者を従事者として指定する、こういった義務付けがされて、従事者として指定された人が情報を漏らすと、誰が公益通報したかという情報を漏らすと、刑事罰がある、体制整備義務を課された事業者が体制整備をしていないということになると、各種の行政措置が取られるということがあると、こういった規定が置かれたわけです。
これが2020年の改正、2022年に施行された法律なんですが、少し時系列を年表的に、いま一度整理してみます。2004年に公益通報者保護法が成立して、2006年に施行されたというふうに申し上げましたが、そもそもどういう時期だったかということを振り返ってみますと、日本では、食品偽装の事件、リコール隠しの事件、そういった多くの消費者、国民に影響を与えるような不祥事があって、ただ、それがなかなか企業、組織として対応できなかったというような問題があって、一方、世界を見ると、例えばアメリカでは、2001年や2002年、エンロン事件、ワールドコム事件と言われるような、世界を代表するような超大企業が、会計不正等の不正を行っていて、それが内部告発者の告発によって判明をして、逮捕されたと、破綻をしていくというようなことが起きたわけなんですけれども。
アメリカではこういった事案を踏まえて、サーベンス・オクスリー法(SOX法)という法律の中に、公益通報者、内部告発者を保護する規定が置かれ、そんなアメリカの動きなどを見ながら、日本もそういった告発者、内部通報、内部告発をする人を一定の限度で保護する法律が必要ではないかと、そんな議論がされて、この公益通報者保護法の成立に結びついたと、こういう流れがございます。
2006年の施行の当時は、独禁法の課徴金減免制度、いわゆるリニエンシーと言われる、自主申告すると、その分、課徴金、行政上の制裁が免除されたり、減刑されるというような制度が同時にスタートしたり、2018年には、刑事訴訟法の改正を踏まえて、協議合意制度、日本版司法取引なんて言われていますが、自主的に他社の犯罪に関する情報を提供すると、提供者の刑が軽減されたりするというような制度が始まったりして、当局に対して情報提供して、当局は情報提供を受けて捜査や調査をする、こういった制度というものが公益通報者保護法以外にも幾つか始まってきていると、こんな状況になります。
そして、先ほど申し上げたとおり、公益通報者保護法が改正されて、通報者の保護が強化されていると、こんな状況になっています。
当局への情報提供を促したり、保護をして、そこから調査をしていくという手法は、日本だけの傾向ではなくて、いろんな国で同じような取組がされています。すなわち、組織の中での不正とか不祥事というのは、どんどん複雑化していて、例えば調査当局、監督当局が立入検査で乗り込んでいって、そこで正確な情報を把握して、そこに対して権限を行使していく、調査・捜査をしていく、責任追及していくというのは、もちろん大事な機能ですし、今でも行われるものの、非常に難しくなっているということで、状況を分かっている、情報を分かっている人からの情報提供を受けて、それをきっかけに調査・捜査をしていく、あるいは組織として自ら対応していく、こういったことの重要性というのが非常に高まってきているというタイミングです。
もう一つ、私がこのスライドで申し上げたいことがありまして、2004年に公益通報者保護法が成立する前の時点では、一体、内部告発や内部通報、どんなふうに取り扱われていたんだろうというお話です。
実は法律ができる前から、正当な目的で内部告発をしたんであれば、それは保護すべきだという議論がありまして、実際そういう裁判例も幾つも出ていました。そこでの議論をベースに、公益通報という一定の内容の通報に関しては、法律で保護をしようということになったんですが、公益通報者保護法の対象である公益通報についての保護以外に、それ以外の保護の部分はどうなったのかというと、実は内部告発者の保護といったものは、法律が成立する前、施行される前からあったし、それはその後も実は続いていますというような理解がされるべきだというふうに考えています。
どういうことかというと、例えば、今いろんな組織で公益通報、あるいはそういったものを含めた内部通報制度を設けていますが、かなり多くの割合が、パワハラ、セクハラ、いわゆるハラスメント通報が多いというデータが出ています。ハラスメント通報の中には、刑法犯に当たるような、公益通報に当たる内容もあれば、刑法には当たらない、なので、公益通報には当たらないんだけれども、ハラスメントは違法行為ですし、それは通報として受け付けますよと、こういった内容がたくさん含まれているわけですね。
そうすると、公益通報に当たらないから、ハラスメント通報した通報者の保護は軽くていいのか、企業の実務でいうとそういう発想はなくて、公益通報に当たる場合、もちろんちゃんとやります。でも、公益通報に当たらないハラスメント通報が来たら、それはそれで大事な通報として取り上げて対応していくという、そういう発想がありまして、それは内部告発者でも、内部通報でも、こういった公益通報に当たる、当たらないにかかわらず、保護していくというのが非常に重要だと、こんなふうに理解しておくべきだというふうに考えております。
ちょっと総論的なお話を申し上げましたが、ここから具体的な公益通報者保護法に関しての幾つか論点、今回の文書問題に関連すると思われる論点を少し取り上げていきたいというふうに思います。
一つは、公益通報の該当性、今、公益通報に当たるかどうかだけで判断すべき問題ではないんだというふうに申し上げましたが、とはいえ、公益通報に当たるかどうかというのが、法律が適用されるかどうかというスタート地点としては、確かに論点として重要なので、ここから入っていきたいというふうに思います。
公益通報者保護法の第2条1項は、先ほどの消費者庁の資料にもありましたが、公益通報の定義について、幾つかの要件、項目を立てています。労働者、退職者、役員が、不正の目的でなく、役務提供先における通報対象事実が生じ、または、まさに生じようとしている旨を役務提供先、行政機関、またはそういった発生、被害の拡大防止に必要なものに対して通報することと、これが大きなポイントということになっています。
この1番から6番の要件の中でいうと、まず、今回一つの論点になっているのが、2番の不正の目的でなくという要件だというふうに理解されます。不正の目的について、少し申し上げたいというふうに思います。
条文を見ると、同じ公益通報者保護法の第2条第1項にはこんなふうに書かれています。
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的でなく、そういった不正の目的でないことが公益通報に当たるための要件として必要だと、こういう条文になっています。
まず、一つ言えるのは、公益通報という名前、公益についての通報なんだという法律の名前になっているわけなんですけれども、第2条第1項の不正目的のところの文言を見ると、専ら公益を図る目的といった、そういった規定のされ方はしていないということになります。
実はほかの法律、すなわち刑法なんですけれども、第230条の2という名誉毀損に関する条文には、専らという文言が使われていまして、名誉毀損的な表現をしたときに、表現行為の目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合、こういった専ら公益のための表現行為で、ほかの要件を満たすと、形式的には名誉毀損に当たりそうでも、名誉毀損には当たらないで、表現行為者は保護されると、こういう条文が刑法にはあるんですが、刑法と同じ専らという言葉は使われていないと、こういうことです。
どういうことかというと、例えば公益通報者、通報する立場の人からすると、かなり多くの事案で、いろんな目的が併存してたり、混じり合ったりしてたり、あるいは感情が交じり合ったりしています。ここに少し書いたもので言うと、交渉を有利に進めようとする目的であったり、事業者に対する反感であったり、そういったものがあって、そうすると、こういった幾つか目的があって、必ずしも公益的な、いろんな方の共通の利益などに該当しなくても、自分個人のための利益みたいなものがあったり、あるいは相手に対する何か感情みたいなものが入ってたりすることはあり得るものの、それを全て不正というのはおかしい、あるいは専ら公益目的じゃないので、公益通報者保護法で保護しないというのは、あまりに厳し過ぎると、こういう発想、議論がありまして、専らという要件は課されていないということになります。
では、ただ実際どんな事案が不正の目的があるとされ、どういう事案が不正の目的がないとされるのかという、この条文に関して、例えば最高裁の判例があって、こういうふうになっていますというような状況では実はありません。裁判例は、地裁、高裁でいろいろあるものの、固まった最高裁判例があるわけではないというような状況です。
ただ、例えば高等裁判所の判例で、こんなのがありますよということを一つご紹介として記載しましたけれども、労使交渉を有利に進める、通報者にとって、使用者側との労使交渉があって、それを有利に進めようという目的、意図というのはうかがわれなくはないと、そういう目的があったようにも認められる。
ただし、不正の目的でないことというのは、目的が専ら公益を図ることにあったと認められるような場合ではなく、例えば不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的がなければ足りると。上記のような意図があるから、交渉を有利に進めようといった意図があるからといって、不正の目的があったとすることはできないと、こんな裁判例があったりするのは参考になるのかなというふうに思っております。
もう一つ、不正の目的を判断する際に考えられることとして、次のスライドに書いたのは、通報を受け付けたとき、通報がされた時点、ここだけで不正の目的の有無を判断するというのは難しい場合もあるということを書きました。
公益通報に当たるかどうかというのは、公益通報した時点が、それが通報行為に当たるかどうかなので、その後の事情によって、通報への該当性、すなわち不正の目的があったかどうかが変わるわけではないんですけれども、とはいえ、通報を最初受け付けた段階では、目的が何なのかとか、何を通報してきているのか、よく分からないことも現実にはたくさんあります。
このスライドに書いている案件受領、通報者への確認、客観資料の確認、関係者ヒアリング、被通報者ヒアリング、事実認定、処分や是正措置等と書いているのは、例えば企業でも、いろんな組織で通報に対応する際の最も標準的な流れを例示しているんですけれども、最初に案件が来たときには、通報内容、それが電話であれ、文書であれ、メールであれ、曖昧なことというのは非常に多くて、そうすると、いろいろ内容を確認しないと、何を通報してきているのか、何のために何を言ってきているのかよく分からないことというのはたくさんあります。
そうすると、一番多いパターンとして、受け付けた後に、通報者にいろいろ確認をして、確認をする中で、こういう内容を指摘してきているのねと、こういうことを希望しているのねと、こういうことが分かってくる。そういったことを分かってくると、これは何らか誰かを引きずり降ろそうとしてやっているんじゃなくて、そういったみんなの利益になるようなことを考えて言っているのね、あるいは、いや、それは違うんじゃないか、だんだん判明してくるということがあるので、通報時点で不正目的を判断されるものの、実際にはこういった調査を進めていく中で、そこが分かってくるという事案がたくさんあるということになります。
もう一つ、不正目的の関係でいきますと、少し関係する論点として、公益通報かどうか、該当するか判断する際に、いわゆる真実相当性、これが関係するかどうかという論点があるというふうに考えます。すなわち、先ほど1番から6番まで公益通報の要件として整理をしましたが、その要件の中には、通報対象事実、刑事罰があるような行為、あるいは行政罰、過料の制裁があるような行為、そういった行為が今生じているんだ、発生しているんだ、あるいはまさに生じようとしているんだ、こういう内容を通報する、告げること、これが条文上、公益通報の定義になっているんですけれども、実際そういう事実があるのかどうか、あると信じたのかどうか、それについて合理的な根拠があったのか、正当な理由があったのか、これを真実相当性というわけですが、これも公益通報の要件になるのかどうか、公益通報と認められるか、該当性判断する際に、その要件となるのかどうかという問題意識ですね。
これ結論とすると、真実相当性は、公益通報に当たるかどうかという判断の際には要件になっていません。これは法律の条文上明らかで、先ほどの公益通報者保護法の第2条第1項を見ると、第2条第1項の中に、事実であることを告げなきゃいけない、事実でなかったとしても、それをちゃんと信じるのに正当な理由があったことを告げなきゃいけない、それで初めて公益通報にあたるんだよという書き方されていなくて、第2条の条文は、ここに書いてあるとおりです。
ただし、真実だと信じていたかとかいうことは、その後の保護要件、すなわち実際公益通報に当たると言われた通報者について、その通報を法律によってを与えるのかどうかと。この部分を判断していく際には出てくる要件なので、該当するとなった後の次の問題と、こういうことが、条文上、第2条、第3条という整理がされているので、条文の解釈として明らかです。
ところが、1点ややこしいのが、先ほど述べた不正の目的との関係が、実は少し関係してくるように思っていて、というのは、例えば、通報者が何の根拠もなくて、臆測でいろいろ物を言ってきていますと。真実でないことも知っていますと。でも、こういうことを言い続けて、あの人を引きずり降ろしてやろうと思って、仮に通報したとしますと、となると、これは、いわゆる不正の目的が認定されるようなケースなんですけど、そういう事案は、恐らく真実相当性もないわけで、両方が当たらないという話になるんですが、真実相当性の議論に行く前に、不正の目的という論点のところが、公益通報に該当するかどうかでは論点になってくると。これは法律の立てつけということになっています。
なので、真実だと信じて通報していたのかどうかという論点は、公益通報に当たるかどうかというとこで考える際には、不正の目的にとまで言えるのかどうかという、こんなふうな考え方をしていくということになります。
先ほど申し上げたとおり、特に最初の通報の段階では、何を通報してきているのかとか、どんな目的なのかというのは、はっきりしない場合もたくさんあって、真実相当性みたいなところも、いろいろ調べていくと、後で分かってくるという話になってくるので、その結果、不正の目的だったんだというような話になれば、そもそも公益通報ではないとなりますし、不正な目的ではないので、公益通報に当たるけど、保護されるのかどうかというところが論点になるようなケースも多数あると、こういう状況です。また後で、ちょっとこの論点、もう一度触れたいと思います。
続いて、2番目ですけれども、組織幹部からの独立性確保というお話があります。これは法律上どこに出てくるかというと、2020年の改正、2022年に施行されている今の公益通報者保護法の中には、先ほどのとおり、体制を整備しなきゃいけないという、体制整備義務が課されました。その体制整備義務の具体的な内容は、消費者庁の指針で定めるとされていて、その指針の中に、こういった項目が出てきます。
紫の四角の中が指針の中身なんですけれども、内部公益通報の受付窓口で受け付ける内部公益通報に係る公益通報対応業務に関して、組織の長、その他の幹部に関係する事案については、これらの者からの独立性を確保する措置を取ると、こういう規程がされていて、指針の中身なんですけれども、指針が法律の中身になっていると、こういう立てつけです。
指針に関しては、消費者庁が、もう一つ、指針の解説というものを出していまして、指針はこういう意味ですよというような解説がされています。その指針の解説を見ると、この項目というのは、組織の長、すなわち企業で言えば経営幹部、行政で言えば行政の組織の長、そういった幹部が主導、関与する事案に関しては、当然その幹部はいろんな影響力行使できる立場なので、公益通報に対応する業務、受け付けたり、調査をしたり、処分をしたり、是正措置を取ったりというところに、何らか影響力を行使して適切に行われないと、そういった事態を防がなきゃいけないということで、これらの者からの独立性を確保する措置を取る必要があるということを定めています。
指針の解説には、どういうことをすれば、法的義務になっている指針を守れるかというところの考え方、取組の具体例も記載されていまして、この項目に関して言うと、企業で言えば、社外取締役、監査機関といったものへ報告をする、あるいはそこからモニタリングを受ける、あるいはそういった監査機関、事業者の外部に窓口を設置する、こういったようなことで独立性を確保するというようなことが例として指摘されています。
なお、指針解説を見ると、こういった独立性確保に関しては、受付段階だけではなくて、受付の後の調査、是正措置、こういったことに関しても確保する必要があるというようなことが解説されています。
続いて、利益相反の排除に関しても見ていきたいと思います。
指針の第4―1(4)という項目では、先ほどの内部通報の窓口で受け付ける公益通報の業務に関して、事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置を取ってくださいと、こんな規定が指針に書かれていて、法的義務になっています。これについての解説として、事案に関係する人、そもそも誰が事案に関係する人かというところが、指針解説脚注24に書かれているんですが、公正な公益通報対応業務の実施を阻害する者ということで、典型的には法令違反行為の発覚とか調査の結果で、実質的に不利益を受ける者と、こういった人を事案に関与させると、いろいろ影響力を行使したりして適切な対応がされない可能性があるので、その担当から外す、そういった対応が必要ですよということが書かれているわけです。
もう一つ、個別の論点として、不利益取扱、範囲外共有、通報者探索を禁止する、あるいは防止する、こういった項目についても見ていきたいと思います。
同じく指針の第4―2(1)というところを見ると、労働者とか役員などが不利益な取扱を行うことを防ぐための措置を取らなきゃいけない。そういった不利益取扱を受けてないか把握する措置を取って、把握した場合は救済回復の措置を取る。そういった対応、不利益な取扱が行われていたら、行った人に対していろんな事情を考慮して、懲戒処分、その他適切な措置を取る必要があると、こういったことが指針に書かれていて、法的義務になっていると、こういう状況です。
不利益な取扱というものに関して言うと、そもそも公益通報者保護法が成立したときから、法律の中に、こういった公益通報を理由とする解雇、その他の不利益な取扱というものはしてはいけない、しても無効になるよという条文が置かれていて、当然今もその条文あります。
今回の体制整備として、事業者、企業でも、行政機関でも、こういった体制を整備してくださいねということが、指針で義務付けられたと、こういう状況になっています。
不利益な取扱としては、例えば、下に書いてある解雇、懲戒処分といった処分みたいなものもそうですし、処分以外の事実上の嫌がらせ、仕事をさせない、行事に参加させない、そういったものも含めて、不利益な取扱ですよということが、指針、解説の中で明示されていると、こういう状況です。
もう一つ、指針第4―2(2)で書かれているのは、範囲外共有とか探索の防止、通報者探しをしないようにしなければいけないということで、範囲外共有というのは、公益通報者を特定させる事項、誰が公益通報したのかという情報を必要最小限の範囲を超えて共有してはいけないよという話です。範囲外に共有するということなんですけれども、こういうことはしない、通報者を探そうとしてはいけないと、こういったことが指針に書かれています。
公益通報をしたことが他者に知られる懸念があると、どうしてもちゅうちょしてしまうという、冒頭申し上げたようなところがあるので、これを守っていきましょうと。こういうことが規定されているわけです。
不利益取扱の防止、範囲外共有、通報者探索の防止、これに関して、一つ論点として指摘をしたいのが、組織の中に対する内部への公益通報について、こういった措置を取らなければいけないというのは争いないところだと思うんですけれども、行政機関、報道機関等の外部、第三者に対する、いわゆる2号通報とか3号通報と言われる、これらに対しても、こういった体制整備をしなければいけないのかどうかというところです。
結論からすると、これは2号や3号通報に対しても、こういった体制整備が必要だというのが消費者庁のスタンスで、明確にそれが出されています。どういうことかというと、指針の中でいうと、第4―2のところに、公益通報者を保護する体制の整備として、先ほどの不利益取扱の防止や範囲外共有や通報者探索の防止ということが書かれているんですが、第4―1や第4―3の表現と違って、第4―2のところだけは、公益通報者を保護する体制というふうに書かれていて、内部公益通報、内部への公益通報の体制整備じゃなくて、一般の公益通報という表現になっています。
実際、この指針を解説している指針解説、消費者庁が出している指針の解説の中に、こういった行政、その他の第三者、報道機関等の第三者に対する通報についても、不利益取扱の防止や範囲外共有、通報者探索の防止もする必要があるんだということが書かれています。
もちろん指針解説は、指針そのものではないので、法的な義務をそのまま構成するものではないという立場の解説なんですが、現状、法律を管掌する消費者庁として、明確に体制整備義務についての指針は、ここは2号通報、3号通報にも課されるんですよということを明示しているので、例えば、今後、消費者庁が何らか行政処置をかけていくという場合は、消費者庁は当然このスタンスでかけてきますし、仮に何かもし裁判で問題になったときに、2号通報、3号通報にも不利益取扱防止等の体制整備義務があるのかという問題になると、恐らく裁判所は指針解説の中身も踏まえて判断していくことになると思うので、これ、私個人としての感覚や見解ですけれども、こういった2号通報、3号通報についても、不利益な取扱の防止等の体制整備義務というのが課されていると。
すなわち、誰が当局に告発したんだ、誰がメディア等に告発をしたんだということを社内で、組織内で探そうとしたり、あるいはそういったことをした人に対して、通報を理由とする不利益な処分を課したり、何らか事実上の不利益な取扱をすると、ちゃんと体制整備義務が課されていないという、違法状態ですよねと。改善してくださいという話になっていくだろうというのが私の考え方です。
一つ、概念図で整理しておきたいと思いまして、図を入れました。左側に青い四角で内部通報、右側に黄色い四角で内部告発というふうに書きまして、組織や社内の中、会社の中で、事情分かっている内部者がいますと。この方が組織内部へ通報していく。これ問題じゃないかという指摘をしていくのが、いわゆる内部通報ですねと。
一般に内部告発と言われている行為は、中から外に対して、これはおかしいじゃないかということで、行政、メディア、こういったところに出していく。外に出していくものが内部告発ということで、大きく二つに分けて考えることができます。
今述べてきた公益通報者保護法というのは、実は大きな四角よりは小さな四角になっていて、公益、すなわち法律は、刑事罰があるような行為、行政罰があるような行為について通報することを公益通報と定義しているので、全体の四角よりは、小さい赤い四角が公益通報になりますと。ただ公益通報の中にも、中に言っていくものもあれば、外に言っていくものもあるというのが立てつけになっていまして、中に言っていくのが、いわゆる1号通報と言われたり、内部公益通報と言われたりするもので、外に言っていくものが2号通報と言われる行政機関、3号通報と言われるメディア等に対する通報、こういったことになっているわけです。
2020年の法改正で、先ほど少し申し上げた、従事者を指定してください、従事者について守秘義務がありますというのは、左側の内部公益通報の中でも、窓口をつくって、窓口で対応する人を従事者に指定してくださいね、守秘義務がありますねというのが定められていて、プラス窓口でいろいろを行っていく通報への対応について、例えば、原則としてちゃんと調査しなければいけない、利益相反排除しなきゃいけない、いろんなことが書かれていますと。
なんですけれども、右側、2号通報や3号通報にも、今申し上げた不利益取扱の防止、範囲外共有の防止、通報者探索の防止、ここに関しては右側の2号通報、3号通報のほうも、法改正で体制整備の義務が課されていると、こういうふうに考えているのが、今の消費者庁のスタンスと、こういうふうになっています。
ということで、これ、全体見てくると、公益通報とは、あくまでも真ん中の部分なんですけれども、外の白い部分、先ほど申し上げた、例えば刑法犯には当たらないようなハラスメントの事案とか、数でいうと、この白い部分、たくさん世の中にはありまして、これも非常に重要だということになっているので、冒頭申し上げたことの繰り返しにはなるんですが、公益通報、もちろん非常に重要なことで、この法律を踏まえて、法律の違反にならないように対応していく必要があるんですが、同時に、外の白い部分になったからといって、対応をおろそかにしていいとかということでは全くなくて、これはこれで非常に重要なテーマとして取り扱っていくのが必要ですねと、こんなふうに考えております。
さらに、この後、スライドでは公益通報者保護法に関連して想定されるご質問、あるいは聞かれることがあるご質問について、幾つか論点的に取り上げていってみたいというふうに思っております。
まず一つ目ですけれども、今申し上げた3号通報、メディア等、第三者に対して通報していくものですけれども、3号通報として保護される要件について、こういう理解で正しいかというようなご質問がありますと。労働者、退職者、役員が役務提供先について、そういった勤務する企業、組織について、通報対象事実が生じ、または、まさに生じようとしている等、信ずるに足りる相当な理由があり、通報の目的が不正の目的でなく、3号通報先へ通報することと理解しているんだけど、これがあれば保護されるということでよいかと、こういうご質問を受けました。
先ほど申し上げたとおり、このご質問で言うと、公益通報にそもそも当たるかという話と、当たった上で、法律上の保護が受けられるかどうかという話が少し混じったような質問になっているかなというふうに理解をしています。すなわち、公益通報に該当するかどうかというところでいくと、③に書かれている通報対象事実が生じ、または、まさに生じようとしている旨を通報すれば、公益通報には該当するというのが、該当性のところの要件なので、信じるに足りる相当な理由があるかどうかという部分は、公益通報に該当するかどうか、該当したとなったら、その後で保護されるかどうかという論点のとこで出てくる話なので、公益通報に該当する場合に、公益通報者が保護されるか否かというところで、信じるに足りるかどうかと。法的にはこういった二段階に分けて整理をしています。
仮に真実相当性がない。例えば、根拠として、必ずしも十分じゃなかったというふうになった場合は、不正の目的とまでは言えないので、公益通報には当たるけれども、真実相当だというふうに信じるとこまでいかなかった。なので、例えば社内に、組織内に通報しているんだったら、それはこの法律で保護は得られるんだけれども、外部に持っていくには、そこまでの 保護は法律では与えられないよというような話があったりします。
続いて、二つ目のご質問ですけれども、3号通報に当たる場合に、通報先でないものが不正の目的や信ずるに足りる相当な理由がないとして、公益通報に当たらないと判断することができるかと、こういうご質問をいただきました。
3号通報、組織の中から外の第三者に対して通報していった場面を考えて、そうすると、通報している相手は組織外の例えば報道機関等の第三者ですねと。その上で、通報を受けた者じゃないんだけれども、そこで公益通報に当たらないと判断することがあり得るかどうかと、こういう話です。場面を具体的にイメージしたいと思うんですが、例えば組織の中から、職員、何らか事情を知った職員などがいて、その方がメディア等の外部に公益通報を行っていた場合、こういう場面ですね。
そうすると、そもそも組織としては、先ほどの体制整備義務、外への通報でも体制整備義務を負っているので、不利益な取扱、誰がこういった通報したんだということで、例えば通報者を探そうとしたりしてはいけないし、何らか通報者が分かったときに、誰が通報者かということを必要最小限の範囲を超えて範囲外に共有してはいけないし、通報したことを理由に不利益な取扱をしてはいけないと、そういう一般的な防止の措置を取る義務はそもそもありますねと。
続いて、3号通報を受けたメディア等の外部の人が、その後どう対応していくかというと、通常は、通報を受けると、それですぐ報道するんじゃなくて、当該組織、企業、行政機関等に取材をかけますと。そうすると、これ、こんな情報提供があったんだけど、事実なのかというような取材が来て、それで今度は組織のほうが、外からそういう取材が来たんだけれども、実際どういう事実関係だったのかというのを調査していくということになりますと。
事実調査を行った結果、通報者に不正の目的が認められるというふうに判断する場合というのがあり得ますと。例えば、先ほど少し申し上げたとおり、何らの根拠もなくて、臆測で、いろいろ言っているというふうに仮になった場合に、これは先ほどの限定的に解釈される不正目的というのがあっても、限定的に見たとしても、これ不正目的ですねという判断されることというのはあり得て、そうすると、この場合は、通報を受けた立場ではない組織ですけれども、調査をした結果、当該組織が公益通報に当たらないというふうに判断、結論づけるということは、これはあり得るということになります。
ただし、ご質問の中の通報先でないものが公益通報に当たらないと判断する、不正の目的ということで判断することができるかということ、これはあり得るというのがお答えだというふうに思います。
ただし、先ほど申し上げたとおり、不正目的というのは、非常に法律上、限定的に、厳格に理解されているので、慎重にここは認定する必要はありますけれども、あるかないかと言えば、あり得るということになります。
一方、信じるに足りる相当の理由があるかどうかというところについてですけれども、組織内で、今のような取材を受けた後に調査をした結果、通報者は、根拠は十分じゃなかったんじゃないかというふうに認定されるケースというのは、これは不正目的とは違って、こういう事案は結構たくさんありますと。そうなった場合は、公益通報に該当することには変わりはない。ただし、法律上の第3条以下に書かれている、例えば解雇等の処分は無効だよ、法律上、不利益な取扱を、事実上の不利益取扱等含め、これは無効になるよといった法律上の保護は、その者は受けないと、こういう状況になります。なぜかというと、外部への通報の保護要件を満たさないからということです。
ただ、これ注意しなきゃいけないのが、真実相当性が足りない、具体的な根拠が足りませんでしたとなったときに、翻って考えて、懲戒処分していいんですねと、こういうふうに反対解釈はしてはいけないというのが、一般に法律的に言われていることで、もちろん懲戒処分などされる場合もあり得るんですけれども、法律上の保護がないからといって、直ちに自動的に処分をしていいというふうには考えられなくて、先ほどのとおり、内部告発で、もともと法律できる前から保護されていたエリアもあるし、いろんな状況を考えたときに、どこまで法律の保護がないからといって、保護しなきゃいけないのかというのは、かなり微妙な問題で、実務的にも非常にここは慎重に企業でも現場でも取り扱っているところということになります。
場合によっては、これは不正目的とまでは言えないけれども、やっぱりいろいろ問題だというふうになることもありますし、処分等はできないということもあって、結構ここは慎重に判断すべきところだというのが実務的な感覚です。
続いて、質問の3、通報対象事実の調査結果が判明する前に、範囲外共有、通報者探索、不利益取扱をすることが許されるのかと、こういうご質問がありました。
これは通報対象事実について、当然いろいろ調査をしていくんですけど、その調査の結果が出る前に、こういった取扱をすることはできるのだろうかということです。お答えとしては、こんなふうに書いてみました。公益通報の事案に関して言うと、受付段階、調査段階、是正措置等、こういった一連の対応のプロセス全てを通じて、不利益な通報を理由に、何らか不利益な取扱をしたり、通報者が誰かという情報を必要最小限の範囲を超えて共有したり、通報者を探したり、こういうことをしてはいけないというふうになっていて、こういったことをしないように体制整備しなきゃいけないというのが組織に義務付けられているので、これに違反すると、体制整備義務違反の状態になってしまうわけですね。
なので、調査結果が判明する前に、こういった扱いをすることというのは許されないし、また仮に調査結果判明して、たとえ通報者が指摘している事実関係は認められない、いろいろ調査した結果、ここの部分は事実じゃなかったというようなことになったとしても、通報者に対して、当然に不利益取扱をしていいのか、誰が通報したかということを必要最小限の範囲を超えて共有していいのかというと、そうではなくて、そこは、たとえ認められなかったからといって、その部分のこういう扱いをしていいというわけにはならないんですよ。なぜかというと、範囲外共有の防止、通報者探索の防止、不利益取扱の防止というのは、組織にこういった体制を整備してくださいねというふうに課されている義務なので、これはこれで体制整備しなきゃいけないと。
一方、個別事案で、その通報者が保護されるかどうか、処分が無効になるかどうか、懲戒処分等が無効になるかどうか、そういったところを解釈する際には、真実相当性、実際事実だったのか、それを信じた根拠があったのか、ここを見ていくわけなんですけれども。体制ちゃんと整備しなきゃいけないですよねというのは、これは組織に課されている対応の義務なので、ここ議論を混ぜてはいけないということになります。
質問の4、うわさ話や臆測をもとにした通報というのが、不正目的ありと認められるのかどうか。今回の文書問題でも一つの大きな論点として位置されているというふうに理解しています。
また、不正の目的ありとまでは認められなくても、真実相当性がないと判断されるのかどうかというところです。ここについては、こんなふうに整理をしてみました。まず、うわさ話とか臆測をもとにしているケースというのも、結構、内部通報の現場ではいろいろあります。うわさ話や臆測をもとにしていると、それだけで、例えば不正目的ありというふうに認定されているかというと、そうではないという理解です。
というのは、繰り返し申し上げているとおり、不正の目的という法律の条文、非常に限定的に捉えられているのと、現実に通報の現場というのを考えたときに、いろんな事情、いろんな目的、感情が併存していることが多いというようなことをもろもろ考えたときに、単純に不正目的ありと認定されるケースって非常にまず狭い。うわさ話、臆測をもとにしているからといって、それだけで不正目的ありとなるケースというのは、なかなかないのかなというふうには思います。
うわさとか臆測以外に、何ら具体的にその根拠がないですというふうになった場合は、不正目的の要件じゃなくて、真実相当性のところで、これは真実だと信じたことについて、正当な理由、合理的な根拠があったのかというと、ここは違うんじゃないのというふうに判断される可能性は十分あるねというふうに思います。というのが二つ目のところに書いてあることです。
現実には、うわさ話とか臆測というものでも、例えば、伝聞ですと、直接自分が見聞きしたことじゃなくて、人から聞きました、うわさ話もいろんな人がいろいろ言ってますとなったときに、本当に状況によるというふうに理解されていて、ここに供述の信用性の評価次第というふうに書きましたけれども、どんな立場の人が、どういう根拠に基づいて、どういう指摘をしているのかということによっては、信用できるねということもあり得るし、場合によっては、それは信用には足りないねというふうになることもあり得るので、一概にうわさ話や臆測だからアウト、セーフというふうには言えないというのが、この事案についての認定の実務的な感覚かなというふうに思っております。
質問の五つ目ですけれども、メディア等に3号通報をしたという後に、内部公益通報、1号の通報がなされたという事案について、公益通報者保護法の適用関係はどう整理されるのかと。実際、今回の事案に関しても、3月中に、まず最初、メディア等に対して文書で、いわゆる3号通報に当たるような通報がされて、その後、中の組織内の通報窓口、公益通報の窓口に通報がされましたというふうになったときに、3号通報、1号通報、両方出てき得ると。これについて、法律との適用関係でいくと、どう整理されるのかということをちょっと整理してみました。
まず、初めの組織の外、メディア等に対する通報の時点で、そもそも組織、兵庫県なら兵庫県という組織として、不利益な取扱や範囲外共有、通報者探索防止という体制整備義務に違反しないように、そもそも体制整備、ちゃんと整えてなきゃいけないですし、個別の事案についても、それにのっとって運用しなければいけないというのが、まず外部への通報のタイミングで出てきますねと。プラス、続いて、内部に対して公益通報がされましたという時点で見たときに、そうすると、外部への通報の場合にかかってくる上の三つの体制整備だけではなくて、内部に関してということになると、通報者特定情報、誰が公益通報したのかという情報を知っている人は、ちゃんと従事者指定を受けていますか、組織の幹部から独立性確保されていますか、事案に関係する者は関与しないという利益相反、排除できていますか、原則として、必要な調査ちゃんと行っていますか、事案が事実だと認められる場合には、是正措置等を取っていますかと。こういったことが指針の中で定められている対応義務なので、こういったことがちゃんとされているかどうかというのを見ていくということになります。
プラス、内部への公益通報の対応を通じても、外部にも課されていた不利益取扱や範囲外共有、通報者探索防止と、こういう体制整備は、これは同じく内部への通報についても課されているので、こういったところもしっかり守られているかというのが見られてくると、こんなふうになるわけです。
もう一つ、いろいろ今これ論点見てきましたけれども、今回の一連の文書問題について、おまえの考え方はどうなんだというふうに問われたときに、こんなふうに整理ができるのかなというふうに見ています。実際、私自身が今回の調査、事案について、何か調査に加わったり、あるいはやり取りをしたりという立場ではないので、あくまでも公表されている情報、報道されているものを見た、それ限りでのコメントになってしまうので、確定的なことは申し上げ難い立場ではあるものの、例えば、こんなふうに考えてますということを少し申し上げてみたいというふうに思います。
まず、公益通報に当たるかどうか、この法律が適用されるかどうかというのは、それだけでは決まらないよと申し上げたものの、とはいえ、これはこれで一つ大きな重要な論点なので、ここをちょっと考えてみると、不正の目的ありと言えるのかどうかという、ここは一つ大きな論点ですねと。
一言で、この点についてコメントをすると、慎重に判断しないといけない論点だということなので、いろいろ調査をした結果、最終的に、全く何の根拠もなく臆測だけで誰かをおとしめようとして言っているんであれば、不正の目的ありとなる可能性はあり得るものの、いろいろ調査した結果、そうではないと。例えば、これはおかしい、いろんな状況に基づいておかしい、兵庫県をよくしよう、そういう目的で言っているのだとすると、不正の目的ありとまでは言えないんじゃないかというのが一般的な見方だというふうに見ています。
仮に、不正の目的があるかどうかというところ、ちょっと一旦通過したとして、今回の事案でいうと、そもそも通報対象事実、文書の内容が、例えばパワハラみたいなものが入っていて、これ刑法には書かれてませんねというふうになると、公益通報という内容にそもそも当たらないという部分があるのは確かで、一方、収賄したんじゃないかみたいな話になると、これ刑法に入ってくる話なので、内容によって公益通報に当たるような内容もあれば、当たらない内容もあって、これ不正目的どうかと関係なく、中身の問題ですね。両方入ってきているという事案だなというふうに思っています。
ここは、少なくとも一部に関して公益通報に当たるような内容があって、不正目的ではないというふうにもし認定されれば、法律が適用されるという前提で見ていく必要があるし、最終的に、いろいろ調べた結果、不正目的、すなわち何の根拠もなくて、何にも公益的なことじゃなくて、これは法律が予定しているような不正目的だともしなれば、法律の適用がないというケースもあるし、いずれにせよ、ハラスメントみたいな部分に関して言うと、法律の適用というのは難しい部分ということになってくるんだろうと、こんなふうに見ています。
仮に公益通報に該当しないとなったときに、どういうふうに考えるのかということなんですけれども、法律上の不利益な取扱、通報者探しの禁止、そういったとこは公益通報に該当しなければ、法律上の義務というのは当たってこないので、それは当たってきませんねとなるんですけれども、一般的な企業、組織の対応している感覚でいうと、通常、法律に当たるかどうかだけじゃなくて、通報を理由にした不利益の取扱というのはしないよという組織としてのルールを持っていて、対応しているので、そういった社内規程違反、組織上のルール違反みたいなものになってくるということになるので、公益通報に当たらなくても、そこはちゃんとカバーして配慮しながら進めていくというのが実務的な感覚です。
通報した人が、不正な目的でいろいろやろうとしているんだったら分かるんですけど、そうじゃなくて、内容が公益通報に当たらない部分があったりとかというときに、それで不利益に取り扱われる可能性があるとなったら、もとに戻って、怖くて誰も通報しなくなってしまうので、それは非常によくないというのが、組織のリスク管理、コンプライアンスの一般的な考え方なのかなというふうに思います。
続いて、そもそも今回の事案で、不利益な取扱、範囲外共有、通報者探索と言われるような取扱がされていたのかどうかというところに関して言うと、これは実際の事案の事実関係次第ではあるものの、例えば、懲戒処分がされていて、その根拠として、文書での内容に関してとか、あるいは見たときに、それは通報を理由として、懲戒処分を科している、あるいは記者会見のようなところで、こういった通報をしていて、それが事実でないということを認めていてということを言っていくとなると、記者会見で発言することは、何か処分をしたわけではないんですけれども、先ほどの事実上の不利益な取扱、事実上の行為も含まれるよというとことの関係でいくと、不利益取扱に当たるような行為という話になってくるんだろうなというふうに思いますし、範囲外の共有、誰が公益通報したかという情報を、例えば会見で言ってしまったりとかいうことになると、本当に必要最小限の範囲の人だけでその情報を管理してたんですかという、そんな話になってくる。
通報者探索、誰が通報したのかということを探そうとするということになると、通報者探索の問題になってくるということになります。
これ、そもそも例えば、知事がどうかという、事案について言われた側が何したかという論点ももちろんなくはないんですけれども、体制整備というのは、組織として、そういった例えば規程をちゃんとつくって、運用のルールをつくって、こういうことがないようにしなきゃいけないということなので、そもそもそういったことをしっかり捉えていたのかというのが、もう一つ問題になるところで、直近で言うと、いろいろ内部通報の対応体制というのが整備されて、改定されたというふうに理解していますけれども。この当時、どういうふうな体制整備がされてたのかという、県としての体制の整備のところというのをちゃんと見る必要があるんだろうなというふうに思っています。
3点目に書いてある組織幹部からの独立性と事案に関係するものの関与の排除というところで見ると、まず独立性のところなんですけれども、通報の内容で、こういった事実があるというふうに指摘された人というのは、事案に関係するし、かつ組織の幹部だということ、トップだということになると、こういったところの影響力、関与を排除する形で対応しなければいけないというのが、公益通報事案であれば、法律上の要請ですし、公益通報事案でなくても、大体どの企業であれば、どの組織もそういった人は関与しないようにして、何らか対応するというルールを持っています。それが一番公正で適正に対応できるからということなわけですけれども、ただ、独立性に関していうと、例えば法律上の指針で書かれている内容としても、組織の幹部が全く関与しない形、幹部に近い部門が一切関与しないかというと、全部、第三者委員会みたいなとこがやんなきゃいけないかというと、そこまでは要求されていなくて、先ほどのようにモニタリングを受けながら行う、そういった柔軟性はあると、こんな状況になっています。
最後、少しだけコメントして、私からのお話を終えたいと思うんですけれども、企業がどんなふうな思いで、公益通報や内部通報に取り組んでいるかということだけ少し申し上げます。
指針の第4―3(1)というところには、教育、周知に関する対応しなきゃいけませんよということも書かれていて、その中には、組織の長、企業で言えば経営トップが、主体的かつ継続的に制度の利用を呼びかける等の手段を通じて、信頼性を高めていかなきゃいけないということが書かれていて、例えば、コンプライアンス経営の推進における内部公益通報制度の意義・重要性、リスクの早期発見、企業価値向上に資する正当な職務行為なんだぞということ、不利益取扱は許されない、秘密保持は徹底する、こういったことを組織の長自身がどんどん発信して信頼を高めていかなきゃいけないということが、法的義務として要求されているわけですね。
企業で言うと経営トップというのは、コンプライアンス経営大事ですと、どの企業も言っているわけなんですけれども、そう言っている一方で、実はこういった問題を真面目に捉えてないということになると、企業の中の人って、そこを敏感に感じるわけですよね。なので、ここは本当に言動を一致させて、本気で取り組むという姿勢を見せないと、なかなか信用してもらえない。そうすると、リスク情報とか大事な問題というのが上がってこない。やっぱり経営陣にとって非常に怖いことなので、一生懸命取り組んでいるというのが企業の現場です。
企業だと見ていただいたときに、コンプライアンスの取組って、経営トップが一生懸命イニシアチブを取って進めていくわけなんですけれども、経営トップが何か問題があることをしたときのためにガバナンスの仕組みがあって、監視をする。
内部通報というのは、コンプライアンスの取組などしている中で、何かあったら言ってきてねというものがあって、それ以外にも、上司・部下のラインでもいろんな指摘というのがあり得て、プラス経営陣の不正みたいなものに関して言うと、こういったガバナンスの仕組みへの通報の仕組みがあって、こういったものが一体的に組まれていて、いろんなチャンネルで組織をよくしていこうというのが企業の取組なわけなんですけれども、内部通報制度大事ですというふうに今日申し上げてきましたが、内部通報制度って、あくまでも内部への通報なんで、内部をつかさどっているのは、一番上は経営トップですし、組織のトップですし、その下の役員とか、その下の上司、こういう人たちが信頼できないと、幾ら通報制度立派なものをつくっても、やっぱり中に言ったら、結局、握り潰されるちゃうんじゃないか、仕返しされるんじゃないかというと、右側の水色のとこ、機能しないんですよね。だからこそ、一生懸命、経営陣も含めて真面目に取り組んで、何か問題があったら言ってきてねという、何か自分に関係することがあったら、こういった独立の人がチェックするよというような仕組みをつくってやっているのが企業実務でして、そこはもちろん公益通報者保護法が適用になるかどうかも大事なんですけれども、それを超えて法律が適用になる事案でも、ならない事案でも、こういう発想を持って取り組んでいくということが、非常に重要なのかなというふうに個人的には思っております。
ということで、私からの話は以上にしまして、残りの時間をQ&A等でご対応できればと
いうふうに思っております。ありがとうございました。
○委員長(奥谷謙一)
ありがとうございました。
それでは、これより質疑と意見交換を行いたいと思います。
概ね11時30分ですが、委員の皆様、ご質問があれば。12時までよろしいですか。
○参考人(結城大輔)
大丈夫です。
○委員長(奥谷謙一)
すみません。ありがとうございます。
それでは、増山委員。
○増山 誠委員
ありがとうございました。ちなみになんですけど、告発文というのはご覧になっていると
いう認識でよろしいですか。
○参考人(結城大輔)
一部伏せ字になっているバージョンですけれども、拝見してます。
○増山 誠委員
告発文が発出された経緯についても。
○参考人(結城大輔)
理解しているつもりでおります。
○増山 誠委員
かしこまりました。3月に出された本件告発文について、公益通報としての保護が及ぶと考えられるかというところをもうちょっと詳しく聞きたいんですけれども、まず、4月の内部通報については適切に処理されていて、基本的に、そこについては争われていないというふうに認識してます。今、この場で争われているのが、3月に出されたほうの告発文で、3月20日の時点で、1号、2号、3号通報ではない、一般の方からの提供によって、知事は文書を入手したという経緯がございます。
公益通報に該当する要件、先ほど六つ述べられましたけれども、そのうちの法定の者による通報であることというのが、もう一つ、法定の通報先への通報であることというのが、どうも3月20日の時点では当てはまらないように思うんですが、これはどういうふうに理解したらよろしいでしょうか。
○参考人(結城大輔)
ご質問ありがとうございます。まず、法定の者による通報という部分に関して言うと、先ほどの1に書いてあった、労働者とか退職者、1年以内の退職者、一定の要件を満たす役員というのが法定の者による通報ということになって、これはもちろん実際に、例えば誰が通報したのかというのは、後になっていろいろ詳しく調べて分かることもあるものの、現実に元県民局長が通報してたということになると、法定の者による通報という部分は満たされるということになる。なぜかというと、現実の職員の方が通報するということになるので、この要件は満たすということになるというふうに理解されます。
○増山 誠委員
匿名であった場合、法定の者による通報であるかどうか分からない状態で、これは探索をしたから分かったものであって、それは、例えば、どこの誰か分からない人が出していた場合もあり得るわけじゃないですか。
○参考人(結城大輔)
あり得ますよね。実際、匿名通報というのは世の中にたくさんあって、匿名通報は公益通報に当たらないのかということだと、それはそうは考えられていなくて、なぜかというと、現実に誰かは通報してきてて、それは可能性として、もしかしたら外の人が言ってきているかもしれない。ですけれども、例えば、後で公益通報かどうかというのが、仮に裁判まで行きましたとなると、その時点で誰が通報していましたかということを見たときに、客観的な事実はあるわけですよね。
なので、分かるかどうかという問題と、現実にこれが通報に当たるかどうかというのは別の問題なので、そのとき、匿名だから分からないからといって、公益通報に当たらないというふうには判断されなくて、法的には、まさにこの事案でいうと、県民局長が当時通報していたんであれば、それは当たるのは当たるんですねと。
○増山 誠委員
分かりました。
○参考人(結城大輔)
対応する立場とすると、もしかしたら、匿名だと、これ誰が言っているか分からないで、外部の全然分かんない人が勝手に書いているものだったら、これ公益通報に当たらない可能性もあるので、一応両にらみはするものの、客観的にはこれは当たっているということになります。
○増山 誠委員
分かりました。次の法定の通報先への通報であることという要件に関してはいかがでしょう。
○参考人(結城大輔)
これは大きくは三つあって、役務提供先、すなわち勤めている兵庫県なら兵庫県、そして監督官庁、犯罪行為であれば警察、監督官庁、そして第三者、第三者は誰でもいいということではなくて、発生や被害拡大の防止に必要なもの、メディア等ということになってくると。
これらに対して通報すれば、法定の者に対する通報というのは満たされるというのが条文の書き方なので、そこに真実相当性などはここには出てこなくて、今のいずれかに当たればいい。
例えば、友達に何かこの話を言いましたというと、これは第三者ですけど、被害の発生、拡大防止に必要な人に言ったというわけではないので、これは公益通報には当たらないですよねというふうに判断するんですけど、メディアに言いました、例えば議員の方に言いましたとかというふうになってくると、ここは発生被害の拡大の防止に必要なものだというふうに認められて、法定の者に対する通報は当たるというふうに判断するというのが法律の読み方だというふうに思います。
○増山 誠委員
メディア、議員、県警に出されたものに対しては、そういうふうな整理でいいと思うんですが、3月20日の時点で、知事が受領したときには、一般の方からもらっていて、それが通報されているということがどこからも知らされていなかった状態なんですね。そうすると、ある意味、道端に落ちていたのを拾ったような状態なわけですから、それが公益通報に当たるのかどうかというのが、テレビでも、野村弁護士が、これは1号、2号、3号通報でないところから得たから公益通報に当たらないという法解釈をされているのですが、ここはどういうふうに考えられていますでしょうか。
○参考人(結城大輔)
まず、通報に当たるかどうかという判断をするときに、知事が入手した行為が、通報かどうかというと、それは知事に対して何か通報しているわけではないので、そこは当たらないというのはそのとおりだと思います。
ただ、その前に文書を送りましたと。ここがまさに通報者が事実を告げるという行為なんで、ここが当たるかどうかを判断するという話になって、その時点の判断になって、知事が入手したことを公益通報に当たるかどうかという判断をするのではないと、こういう関係性です。
○増山 誠委員
知事がそれを得てから、すぐに通報者の探索を開始していますと。その時点では、通報、どこかにあったことは誰からも知らされていない状態なので、探索行為が公益通報者保護法に違反するかどうかの限定した議論でいうと、どうでしょうか。
○参考人(結城大輔)
知事が文書を入手したときに、そうすると、文書の中身がどんなものかによってくるというふうに思います。私が拝見している一部黒塗りになっている文書でいうと、その中身というのは、公益通報に当たる可能性がある部分があるのかなと。先ほどのとおり、ハラスメントの指摘とかは、多分、公益通報に当たらない内容ということになってくるんですけど、一方で、収賄みたいなところに関していうと、公益通報に当たる可能性があって、だとすると、公益通報に当たる可能性ある文書が外に行っているのだとすると、これ3号通報に当たる可能性がある、あるいは2号通報に当たる可能性があるとなると、それが例えばメディアから取材が来ました、誰かから来ましたというときに、2号通報や3号通報について、体制整備義務の違反にならないように中で対応すると、こういうのがその時点の対応の仕方ということになると思います。
〇委員長(奥谷謙一)
はい。それでは、藤田委員、どうぞ。
○藤田孝夫委員
ちょっと関連でお伺いします。27ページ、質問の2のところなんですけれども、3号通報に当たるか、当たらないかのときに、メディア、通報先になっています。このときのメディアなんですけれども、これが仮にYouTubeだったり、SNSだったりした場合、既にそれをデータ、その情報が行った段階で、情報漏えいなのか、それとも通報なのかということの問いなんですけれども、SNSの場合、既にそれを取り調べることをしていない可能性が高い。それから、範囲外共有をしている可能性が高い。それから、問題視を意識する。問題視するんではなくて、それを拡散してしまうような可能性しか、ちょっと私には思いつかないんですけれども。
SNSなど、一部のとこに情報を渡したとき、部分的な情報ですけれども、これは通報足り得るんでしょうか。
○参考人(結城大輔)
ありがとうございます。メディアと書きましたので、まさにマスメディアなのか、ソーシャルメディアなのか、いろんなものがあり得るというふうには思っていまして、結論からすると、通報した相手によって、ここは変わり得るというふうに思っています。例えば、報道機関に言いましたと。報道機関は、まさに報道機関が情報提供を受けたときに、事実関係はどうなのか。取材をしたり、確認をして、報道機関としての報道にふさわしいものを取り扱っていくという話になる。
一方で、SNSなどに書いたら、それはそのまま公開されて、そういったスクリーニングとか検討というのは入らないというふうに考えると、報道機関、マスメディアとソーシャルメディア、報道機関とSNS、大分性格は違うのかなと思っています。
では、ソーシャルメディアが、一切、3号通報の法定の通報先に当たらないかというと、そこまで言い切る自信はなくて、これ裁判例など、まだない部分ではあるものの、例えば、緊急を要するような、何か生命とか身体に大きな害が起こるかもしれない不祥事が、実は組織の中で起きてましたみたいな事案があって、今すぐこれ呼びかけないと被害が拡大してしまうというようなときに、何か書きましたというふうになったとすると、条文に書かれている、被害の拡大を防止するために必要なものとして、第三者なんだけど、そこのSNS等に書いたことが当たらないかというふうになると、もしかしたら当たるという可能性もあるかもしれないなと。
これは、何か裁判例があったりするわけじゃない部分、少なくとも最高裁とかはないんですけれども、こんなふうにこの条文が解釈される可能性はあるかなというふうに思っていますが、一般的に言うと、そこまでの緊急性がないような事案であれば、それって、何でそこをいきなりSNSで公開するの。これ発生とか被害拡大の防止に必要と認められるものではないよねとなると、法定の3号通報先に当たらないと、こういうふうになってきて、公益通報に当たらないと、こういうふうに判断されると思います。
○藤田孝夫委員
情報漏えいなのか、公益通報なのかというとこら辺が非常に微妙なところでして、お聞きしたんですけれども。大体において、まず完全なる範囲外共有のケースが多いんで、この場合、例えばSNSであっても、それを受けたときに、それを受けましたということを公表しない場合、それから、これはSNSではあり得ないんでしょうかね。
○参考人(結城大輔)
ご質問、どこまで正確に理解できたかあれなんですが。
○藤田孝夫委員
SNSに上げるということは、それを受けたというように言うということは、既に拡散す
るという、範囲外共有になってしまうわけ、こことイコールなんでしょうかね。
○参考人(結城大輔)
まず、1個ずつ行きますと、内部通報、公益通報かどうかという話と情報漏えいなのかどうかという話は、いつものように、毎回のように、ぶつかる話で、非常に難しい論点だというのは間違いありません。公益通報に当たる事案でも、中身としては、例えば、企業の秘密情報などを企業の外に出す、組織の中の内部情報を外に出す、あるいは公益通報なんだけど、それは逆から見ると、もしかしたら名誉毀損なんじゃないか、そういう場面というのは幾らでもあって、常に両方微妙なところで分析して判断する事案であるというのは間違いないというふうに思います。
微妙なバランスを判断する上で、SNSに上げますという行為に関していうと、SNSって、直ちにもちろん細かい設定はともかく、基本は世の中に対して公表していく、公開していくという行為だとすると、本当にそれが必要なことなのかという話になるので、ここは報道機関が責任持って調査をして報道したりするのとは、大分性格が違うんじゃないかなというふうに思います。
ちなみに範囲外共有と申し上げているのは、必要最小限の範囲を超えてSNSに公開するなどというのが、全部法律上言われている範囲外共有に当たるわけではなくて、範囲外共有というのは、誰が公益通報したかという情報、公益通報者が誰かという情報を必要最小限の範囲を超えて共有してはいけないという言葉遣いなので、言葉としては、もうちょっと狭く定義されているんですが、情報漏えいかどうかという意味でいうと、それは報道機関に言うのも外に言っている意味では、漏えいは漏えいなんですけれども、ソーシャルメディア、SNSに言うのは、さらに漏えいの度合いというか、公表するという行為なんで、そこは大分性格が違うのかな、こんなふうに理解しています。
○藤田孝夫委員
ありがとうございました。
〇越田浩矢委員
まず、知事が8月7日の会見で、これは外部通報、2号通報に当たらないんだという主張の根拠の一つとしまして、配付された文書に記載されている大半の内容は、公益通報者保護法で定められた法律に反する犯罪行為に関するものではないということですと述べておりますので、今のご説明の中で、通報対象事実、今回7項目ある中で、先生は、先ほど通報対象事実に該当するような項目が含まれているというふうなご説明をされたんですけど、7項目のうち一つでもそういうことがあれば、公益通報、外部通報の通報対象事実があるというふうに認定できるというふうに考えてよろしいんでしょうか。
○参考人(結城大輔)
ここは考え方が複数あり得るとは思っていて、というのは、例えば、一つの通報の中に複数の対象事実が含まれているケースというのは結構あります。そのときに、項目ごとに分けて、個別に考えるのか、全部まとめて考えなければいけないのかという論点があります。必ずこうしなければいけないというふうに固まっているわけではないと思うんですけれども、複数項目が書かれていれば、まず自然に考えると、項目ごとに考えるという考え方があると思います。
仮に項目ごとに考えたときに、例えばこの項目は刑事罰があるような内容じゃないですとなると、その項目について公益通報に当たるというのは無理ということになります。一方、こっちの項目に関しては収賄ですねというようなことを言っているとすると、これは公益通報に当たるような指摘ということになって、その部分に関しては、少なくとも公益通報ですねという判断になると思います。
一方、全然違う整理として、全体として通報行為を見たときに、これは全体の中の本当にごく細かい一部なので、全体を見ると、これは公益通報じゃないんだなどというふうにまとめて評価するかどうかという考え方もあると思います。
まとめて見たときに、これはそれなりに重要部分なので、この部分は全体として見ても、結局は公益通報に当たるんだという見方をすることもあるかもしれません。これは公益通報者保護法の公益通報該当性について、全体で見るのか、部分で見るのかという、例えば最高裁の判例はないんですけど、名誉毀損かどうかという別の場面では最高裁の判例があって、例えば、ある表現がされたときに、一般の読者とか読み手、見た人が見たときに、普通の注意、読み方をしたときに、どんなふうに見えるかということで判断しますというふうな記事とか表現行為の読み方みたいな判断があって、仮にそういうのを前提にすると、これも結局は事案によるんですけれども、普通に読んだら、これは全体として言っていることなのか、個別に見てもいいのかみたいなことは、判断の参考にはなるかなと思います。
本件に関して言うと、項目、項目がいろいろされていて、それって全部連動していると言えば、一つ一つの事実関係とすると、まず項目に分けて考えてもいいのかなというふうに、私としては思います。
そうすると、この部分は、少なくとも公益通報だよねというふうな見方ができると。そうすると、その部分に関しての取扱というのは、法律の適用があるという前提で考えなければいけないし、先ほど申し上げたとおり、ほかの部分も法律適用ないんで、不利益に扱ってもいいですかというと、そうはならないでしょうねと、こんなふうに考えています。
○越田浩矢委員
ありがとうございました。よく分かりました。
もう1点、体制整備義務の件なんですけれども、今回の事象で言うと、文書を認識した知事が、まさに告発されている人々を集めて対応を協議して、告発者を探索したという事象で、さらに言うと、結局、懲戒処分までに至っているという事象なんですけれども、本来、体制整備がされているとするならば、どうあるべきだったのか。
これ、何かルールがあって、規程に基づいて処理しないといけないというものなのか、兵庫県でいうと、内部告発の窓口が財務部の県政改革課というところにあって、そこの県政改革課が、いやいや、それは外部通報に当たる可能性があるから駄目ですよみたいなことを、なかなか最初、どういう中身か分かんなかったと思うので、例えば3月27日の知事の会見を聞いて、それはまずいんじゃないかということで、それなりにアドバイスをするとか、懲戒処分までしろというのが指針に書いているわけなんで、体制整備義務という中身、どういうものが求められているのかというのを教えていただけますか。
○参考人(結城大輔)
まず、内部で通報が上がってきたときに、何らか窓口をつくってくださいね。窓口に来たら、一定の例外的場面を除いて、ちゃんと調査をして、事実関係があるかどうかを見て、そういう事実が認められるんだったら、ちゃんと是正措置をしてくださいね。こういう義務がありますと。
その際に、組織の幹部に関係するようなものは、何らかの独立性を確保しなきゃいけないし、事案に関係する者は排除して対応しなければいけませんね。こういう制度設計をちゃんとして、内部規程をつくってくださいね。これが指針に書かれている体制整備の中身ですと。
なので、これをそもそもやっていて、それに基づいて個別事案を扱っていかなきゃいけないというのがあるべき姿ということになります。
私、当時、3月なり、4月なり、あるいはその後の段階で、どこまで兵庫県の中の内部の規程がどうなってたかというとこまで、すみません、詳しく存じ上げないんですけれども、そういったもし規程があるんであれば、それに則って適切にされていたのかというところがポイントになってきて、例えば、幹部の関係する事案のときは、こうするという部分の規定が不十分だった、利害関係がある人を関与させないようにするという部分の規定が不十分だったとしても、仮に規程が不十分でも、この事案って、関係しているんだったら、あえて自分は一旦外れますと。関係しない人で見る、何らかそういうような配慮をしながら進めていくというのがあるべき対応だったんじゃないかなというふうには思っています。
本件でも、私の理解ですと、例えばいろいろ対応していく際に、外部の弁護士意見を確認したり、そういうことをしていること自体は意味があるというふうに思っていて、これ中だけでやるのか、外部専門家に確認するのかというのは大きな違いがあると思っているんですけど、そもそもそういったルールなどが、どういうふうに設計されていて、それに基づいて行われていたのか。必要な場面場面での検討とか対応がされていたのかと。この辺がポイントになってくるのかなというふうに思います。
○越田浩矢委員
ありがとうございます。もう1点、最後に、今回の懲戒処分に当たって、告発者を探索して、特定をして、押収した公用パソコンの中にあった情報でもって懲戒処分を行っております。このこと自体は、刑事訴訟法的に、違法収集証拠の排除ということからすると、不適切ではないかなと思うんですけれども、そもそも懲戒処分やってはいけない事例だとは思うんですけど、さらに言うと、告発以外の非違行為を探索の中で見つけたということをもってして、懲戒処分をすることについて、どのようなご見解をお持ちか、お聞かせください。
○参考人(結城大輔)
刑事手続そのものではないので、刑事手続の違法収集証拠のような議論は、そのまま当てはまるかどうかというのはあるとは思います。一方で、法律上、探索は防止しなければいけない、そういう体制を整備しなければいけないというふうに言われている中で、探索行為をして、そこで得られた証拠を使うということに関しては、非常に慎重に見なければいけないんだろうなというふうに、まず思ってますし、そういった証拠を結果として、そういったものが出れば使っていいとなってしまうと、手続上、少々問題があっても、結果として証拠を確保すればいいというふうな方向に、世の中、流れていってしまうので、そこは厳格に見るべきなんじゃないかなというふうに思っています。
現実には、例えば刑事訴訟と民事訴訟を比べたときに、民事訴訟の場合って、担当する裁判官の感覚によって、随分証拠の見方、証拠の手続をきちっとしなければいけないという考え方と、一方で、真実を追及しなきゃいけないという、両方大事な価値なので、そういったときに、裁判官によっては、真実発見のほうにより重きを置いて、少々証拠の収集過程に若干疑義があっても、刑事手続とは違うんだから、そこは評価としては、多少割り引いては見るけれども、評価しますということはあり得るので、そんなにがちがちに固めづらいという部分はあるんですけれども、懲戒処分ということになると、刑事手続とは言わないにしても、手続が非常に重要なプロセスだということになると、一般の民事訴訟もそうですけれども、証拠の収集プロセスみたいなところをより慎重に評価するべきなんじゃないかなというふうに、感覚としては思います。
〇委員長(奥谷謙一)
松本委員。
○松本裕一委員
不正の目的のところでちょっとお伺いしたいんですけれども、まず、最高裁判例がないことと、いわゆる高裁の判例見ても、非常に認定に関して慎重にあるべきだということはよく分かりました。その上で、お話の中で、例えば全て想像ですね、悪意を持って作成した告発等は、不正な目的に当たるというのは分かるんですけれども、なかなかそれ以外に、不正と認定する事案というのがイメージしにくいんですけれども、これまで先生の知っている事例の中で、不正な目的と認定されたような事例というのがあったら、参考までに幾つか教えていただければと思います。
○参考人(結城大輔)
そうですね。なかなか事案としては、具体的に申し上げづらい部分はあるんですけれども、例えば、虚偽の証拠を捏造して出してきているようなことが後で分かった場合、企業でいうと、いろんな企業の中での競争、足の引っ張り合いみたいなものがあって、そこでいろんなもろもろ、ほかの状況に照らすと、この証拠っておかしいねと、偽造だねみたいなものが出てきていて、それで、あの人はこういう不正をしているみたいなこと言ってくると、これって、そもそも正当な目的じゃなくて、その人を引きずり降ろして、自分が上がろうとしているために、こういうことをしたんじゃないかということが客観的に明らかになると、これは不正の目的による通報だねと、こんなふうに認定されるケースなんかがありますかね。
これは公益通報者保護法そのものではない事案でも、例えば、グローバルにビジネス展開してる企業なんかだと、いろんな海外からの通報とか含めて、いろんな種類の通報が来て、そういう中には、偽造なんじゃないかみたいなケースとかも入っていたりすることもあって、そういうときに不正の目的だというふうな認定とか、この通報は正当な目的に出たもんじゃなくて、これ以上は取り扱わないみたいになったりするようなこともあったりはします。
○松本裕一委員
分かりました。ありがとうございました。
〇委員長(奥谷謙一)
それでは、北上委員。
○北上あきひと委員
通報内容の調査をする前に、不利益な扱いをしてはならないということでお話があったと思うんですが、3月の段階で県民局長の役職を解いている。予定されていた退職を認めなかった。結果として、予定されていた就職先に就くことができなかったということがありますが、これは不利益の扱いの一つだというふうに考えていいものなのかどうか、まずお聞かせください。
○参考人(結城大輔)
そうですね。不利益取扱の何を不利益な取扱というのか。通報を理由とする不利益な取扱の範囲というか、その部分に関しては、かなり広いというのが、法律上示されている解釈、法律あるいは指針解説書上、示されている解釈で、これまでの裁判例とかでも、非常に幅広く見られているというふうに思います。ということで、そういった退職に関する取扱を変えて、その結果、そういった影響が発生しているということになると、そういった取扱まで含めて、不利益な取扱だったと、この不利益取扱に該当するというのは、十分あり得るのかなと、そんなふうに思います。
○北上あきひと委員
ありがとうございます。3月27日の知事の記者会見で、告発文書について、事実無根、うそ八百ということを知事が発言をされ、加えて、公務員失格と、告発者のことを評価しています。告発者本人は認めておられないにもかかわらず、自分は怪文書を流布したということを本人も認めているというようなことを発言をされていまして、このことについて、百条委員会の中の証言でも、ご本人は究極のパワハラだというふうな認識を示されておるんですけれども、結城弁護士のご見解として、この記者会見での発言は不利益な扱いに該当するのか、あるいはパワハラの一つだというふうに認識できるのか。お願いします。
○参考人(結城大輔)
この会見の前にどんなやり取りがあって、仮に会見前のやり取りの中で、実際事実じゃないんですというふうに仮に認めていて、それについて言ったのか、認めてないのに認めてるというふうに言ったのか。それは直接確認しないと、ほかの人が確認したものに基づいて言ったのか、いろんな事実の経過の可能性はあり得るのかなというふうには思うんですけれども、そこ、私、直接関与してないんで分からないですので、そこを一旦捨象すると、その後のやり取りで言うと、事実無根だなんてことは認めてないんだということをその後は言っていて、ということからすると、認めていなかったのにもかかわらず、こういうことを会見で言われたということになると、これは不利益の扱いなんじゃないか、あるいはそれをパワハラという定義の中に入れるかどうかは場面にはよるとは思うものの、そういった不適切な発言で、本人に対して、不利益を与えるというような言い方をしていたということになってくるんじゃないのかなというふうに思います。
そのとき何に基づいて発言したのかとかによって変わってき得るのかなと思うので、そこはちゃんと確認したほうがいいのかなとは思います。
○北上あきひと委員
調査前に、告発文書の内容を事実無根、うそ八百と断じていることについては、ここはどうですかね。
○参考人(結城大輔)
ここは、本当に事実無根なのかどうかは、客観的な事実は本当はどこかにもあるわけですよね。ただ、それを言われた人が言ってしまうと、まさに当事者なので、それがお互い主張が対立してて言っているのか、それとも本当にそのとおりなのかが、かえって分からなくなってしまうわけですよね。だからこそ、本人は、事案の判断とか処分には関与しないで、ほかの人が進めるとかということによって、ほかの人が確認した結果、事実ではなかった、あるいはこの部分は事実だとかというのが、公正な客観的な進め方なのかなと。
それをご本人が言ってしまうということになると、よく分からないという話になってしま
うんじゃないかなというふうに思います。
○北上あきひと委員
ありがとうございます。不適切な対応だったということだと思うんですけど、法律的に、
不利益な扱いとは断じることは難しいということですか。
○参考人(結城大輔)
ご質問は、会見での発言がということですかね。
○北上あきひと委員
はい。
○参考人(結城大輔)
今出ている事実関係からすると、会見で、こういうふうに本人が認めていなかったにもかかわらず、事実無根だというふうに認めているみたいなことを言ったら、それは不利益な扱いだというふうに見ます。
○北上あきひと委員
ありがとうございます。最後、真実相当性の考え方なんですけど、例えば、おねだりとか贈収賄の疑惑があって、利害関係者からの物品の受領はあった。利害関係者から無償貸与は受けていた。その事実はあったが、しかし、それが法令違反にまでは当たらないとなった場合、真実相当性というのは、どのように考えたらいいんでしょうか。
○参考人(結城大輔)
いわゆる真実相当性というのは、そういった事実関係があったと信じるについての正当な理由ということになるので、法的にどう評価されるかというのは一旦置いといて、そういう事実があったと信じたことについて、何らか合理的な具体的な根拠なり理由があったかどうか、ここを見ますということになるので、最終的に、法的にどう評価されるかは直接関係なくて、こういう事実があったということが、例えば、どの立場の人、誰が言っていたのか、何人言っていたのか、実際この立場の人がこういうことを言っているのだったら、それを信じたのは合理性があるんじゃないかな、そういうところを見て判断するということになると思います。
○北上あきひと委員
ありがとうございます。
〇委員長(奥谷謙一)
富山委員。
○富山恵二委員
基本に、また戻るかもしれないんですけれども、人事管理上の処分、企業でもそうだと思うんですけど、やはり社員なり職員から、そういった何か会社に対する意見が出たときに、それと今日説明された、いわゆる通報の扱い、現に今回いろいろ議論になっている3月の文書、警察にも議員にも、それから報道機関にも、ある部分は一定要件そろっているんですけれども、すぐに誰が発したというのを突き止めて、すぐに人事管理上の処分の動きをしていると、外形的に私は見てるんですが、それと、今回の通報の、いわゆる通報者保護の関係のその辺の整理をもう一度ちょっと教えていただければと思います。
○参考人(結城大輔)
私、よく企業の事案で対応していると、人事上の処分などをどうするかというのは、いろんなタイミングで出てくる話ではあるんですけど、まず通報事案の対応として重要になるのは、客観的な事実関係はどうだったのか。具体的に言うと、通報された内容があって、通報内容に書かれていることは事実なのかどうか、証拠はあるのかどうか、ここをよく確認しないと、処分の前提が動いちゃうんですよね、後で。
なので、いきなり処分の議論というのはできなくて、まず事実関係を確認する。いろいろ調査を尽くした結果、これはこういう事実関係ですねとなると、それに基づいて処分どうするのかというのがプロセスなので、先後関係で言うと、別の手続なんで、通報についてどう対応するか、人事上の処分どうするかというのは、別ではあるものの、やっぱり内容は連動していて、そうすると、まず通報された事実関係がどうなのかとかをよく調べてから対応すると。こういう先後関係だというふうに理解します。
○富山恵二委員
その関係から言いますと、本来、内部通報は誰も知り得ないのが普通ということなんですが、今回は本人が4月4日に内部通報をしましたという事例が出ている段階で、今回、人事管理上の処分という動きになっているんですが、この辺は専門家から見て、将来、組織としてはどうあるべきなのか。今の時点で結構ですので、教えていただければと思います。
○参考人(結城大輔)
通報者が誰かどうかという情報を本人が隠したいというときに、しっかりそこの情報を守ってあげる。これ一つ大事なことなんですけど、一方で、事案によっては、誰が通報したかということは分かっている、本人がいろいろ言っているみたいなケースもありますねと。それはそれで一つの論点なんで、守るべき事案では、誰が通報したかという情報を匿名化したり、秘匿化したり、一部の人しか分からないということで進めていく。大事なことだというふうに思います。
一方で、通報された内容が事実かどうかという、ここを確認しないと、必要な、例えば、制度の変更だったり、誰かもし不正行為みたいに関与した人がいるんだったら、その人に対する処分だったり、ルールが曖昧だったのなら、ルールの明確化だったり、どんな対応が必要なのかというのをまず指摘があった通報内容の事実関係をしっかり調査しないと決められないので、これはこれできちっと調査をするというのが大事で、調査する際に、指針の内容、指針解説の内容も参考に進めていくということで、そういう社内規程だったり、運用を整えていくということになるんではないかなと思います。
○富山恵二委員
今回の事例で言うと、文書の内容を調査するのが、二つの部門が動いているわけで、片一
方だけが、先出して、片一方がまだ調査中、だから人事管理上のほうが先に動いちゃったと
いう、今の先生の話だったら、いびつなのかなという感覚がしたんですが、その辺、普通の
会社ならどうなんでしょうか。
○参考人(結城大輔)
ご指摘のとおりかなというふうに思いまして、そこは、どの部署がどういうふうに調査を
して、どう連携するのかしないのかと、整理をして、確認しないといけないんでしょうね。
そうしないと、混乱するように私も思います。
〇委員長(奥谷謙一)
関連で、伊藤委員。
○伊藤勝正委員
すみません。説明資料の29ページで、不正目的と真実相当性のことをお答えいただいています。うわさ話や臆測以外に、何ら具体的根拠等がない場合は、真実相当性があるとは認められない可能性が高いというご説明ですね。これ、具体的根拠等というのは、同時に示さないといけないんですか。後から、しっかり確認、調査の結果で。僕のちょっと理解が浅いんで、そこをちょっと教えていただきたいんですけど。
○参考人(結城大輔)
大事なご指摘だと思っていまして、真実相当性というのは、要するに通報したときに、どういうふうな認識を持って、どういう根拠を持って通報したのかという話になってくるんで、そのときの状況はどうだったのかというところで決まってきますと。すなわち通報した時点なんですけれども。ただ、そのときにどういう認識を持っていて、どういう根拠があったのかというのは、その通報より前の時点のいろんなやり取りだったり、持っていた情報、誰とどういうふうなやり取りしたか、どんな資料を持っていたかにもよるし、通報のときに持っていたのにもよるし、その後、いろいろ判明してきたことにもよるかもしれないので、いろんな事情を総合的に考慮して決めるんだろうというふうに思います。
何か通報のときに、誰かにそれを示さなきゃいけないか、提示してなきゃいけないというような要請、要件はないので、そこで示してなかったから駄目ということにはならなくて、実は後で調査してみたら、その前にこんな人とこんな話をしていた、こういうふうなことを聞いていた、こういう資料を持っていた、こういう話を聞いていたというのも、後から分かったことでもよい。
なので、ちょっとややこしくなるんですけど、判断する時点は、通報した時点でどういう認識を持っていたか、どういう根拠を持っていたかなんですけど、調査をその後ずっとしていくと、その後、いろいろ見たら、こういう状況が分かってきたとなると、これはこの時点も恐らく本人はこういう認識を持っていただろうなというふうに認定する、例えば裁判になって、この法律上の保護が与えられるかどうかというのが訴訟になっていたケースだとすると、後の調査で分かったことなんかも使われるという、こういうことになると思います。
〇委員長(奥谷謙一)
丸尾委員。
○丸尾まき委員
初めは、今の制度上の問題で、内部規程の整備義務というのが存在するとは思うんですが、そのときに、現状、企業だとか行政でもいいんですが、具体に告発者探索あるいは範囲外共有の禁止だとか、具体にそのものを規則の中できちんとうたっていくという理解でいいんですよね。
○参考人(結城大輔)
消費者庁の指針の中には、内部公益通報の対応体制として、実効性を向上するために、この指針に定めている内容を内部規程に定めてくださいというふうに書かれていて、これが法的義務になっているんですね。なので、今まさにおっしゃられたとおりで、こういった対応をするんだということを規程上定めておかなきゃいけないと、こういうことになります。
○丸尾まき委員
それと、先ほど藤田委員の質問にもあったんですが、調査途上で告発者の個人情報を入手したと、その情報は理解としては、範囲外共有の禁止にもかかって、通報者を特定できる情報の守秘の義務付けに当たるんではないかなというふうには思うんですが、それは当然個人情報が一緒に流れ出ますから、そのことはどう考えたらいいんでしょうか。
○参考人(結城大輔)
個人情報の保護というのは、公益通報者の保護というのとは別に、当然、個人情報保護法上の要請があって、それは個人情報に当たるのか、個人データに当たるのか、そういったことも踏まえながら考えていく必要があると。なので、公益通報だから個人情報を無視していいということはもちろんならないし、個人情報保護法上の要請も考えながら対応していかなければいけないということになる。要するに、違う法律なんで、両方意識しなきゃいけないと、こういうことになりますよね。
○丸尾まき委員
ガイドラインの中でも、個人情報の保護というのはうたわれてますんで、そこはきちんと管理しないといけないんだろうなというふうに思うんですが、それは、後置いておきます。
あと、内部通報と外部通報との関係で、先ほど項目ごとの評価も含めてみたいな話もありましたが、兵庫県自体は、内部通報で県政を推進するに当たり、県民の信頼を損なうおそれのあるものは内部通報として取り扱うということになっています。
このときに外部通報の取扱として、法的要件を厳しく定めた上で判断するのか、あるいは内部通報の規程に準じて幅広く認めていくのか、そこはどういう取扱が必要でしょうか。
○参考人(結城大輔)
まず、公益通報者保護法上の要請とすると、中に言ってくる内部公益通報だけじゃなくて、あるいは兵庫県が定める法律よりもっと広い範囲の内部通報は、それはそれであるとして、法律は外部に対する行政機関、その他第三者とかに対するものも公益通報と定義していて、一定の範囲については、法律上の保護を与えているので、ここについては法律の要請に違反しないように適正に対応していく必要がありますねと。プラス法律とは別に、内部としては、こういうようなものも通報として扱いますよと。一部はもちろん法律の保護も重なるんですけれども、法律の保護はなくても、兵庫県としてはこういうものを通報として扱って、こういう取扱をしていくんですよというふうに、兵庫県としての扱いと法律上の扱い、両方併存するというか、両方かかってくる。これは企業も全く一緒で、企業としては、うちはこういうものを通報と扱いますよ、法律はもちろん法律の要請があるんで、両方関係してくると、こういう状況になると思います。
○丸尾まき委員
必要であれば内部でルール上も定めれば、より明確になるということですね。
○参考人(結城大輔)
おっしゃるとおりです。
○丸尾まき委員
最後です。この間、兵庫県が取ってきた対応について、先ほどの告発者探索、範囲外共有の問題も含めて、もちろん最終の確認はまだですが、もしも問題があるとしたときに、どういう措置を取る必要がありますかということですね。処分を撤回するなど、必要な措置があれば教えてください。
○参考人(結城大輔)
そうですね、まず大事なのは、実際何が起きていたのかという調査だというふうに思います。なので、この委員会としての調査も大事ですし、いろんなところが調査するということになっているのかもしれませんが、まず事実関係をしっかり確認をする。それに基づいて、では、これは不利益な取扱だったんじゃないかっていうことになると、指針の中には不利益な取扱が実際されていたら、その回復措置を取る義務があるというのが出てくるので、その回復ができるよう、例えば懲戒処分が不利益取扱だと判断したんであれば、それを無効だとして回復するという対応を、これは組織として、要するに県として、そういう対応を取っていくなど、こういう話になってくると思います。
○丸尾まき委員
はい、ありがとうございます。
〇委員長(奥谷謙一)
庄本委員。
○庄本えつこ委員
体制整備の問題なんですけれど、企業はもう体制整備も随分進んでるということのお話だったと思うんですけど、自治体としての体制整備には、まだまだそれぞれの都道府県でいろんな違いがあるというふうにも聞いているんですけど、兵庫県の場合は、この公益通報、内部通報の場合、財務部が受け持つという形になってるんですけど、東京都などは独立した形でつくられてるということなんですけれども、私は独立して、きちんと体制整備というのはされたほうがいいんじゃないかというふうに思ってるんですけど、その辺はいかがでしょうか。
○参考人(結城大輔)
ありがとうございます。これ、何かこうしなければいけないっていう決まった形とかがあるわけではなくて、その組織によって様々あり得るんだろうなというふうには思っています。
例えば、企業で言えば、法務部みたいなところが通報を受け付けたり、対応するところもあれば、それとは別のコンプライアンス部門が受け付けているところもあれば、内部監査部門が受け付けているところもあれば、規模が小さいところだと監査役が受け付けているところと様々あって、何が正解で何が間違っているとことはないんだろうというふうに思います。
それぞれのメリットもあるし、難しさもあるしっていうところで、いろんな組織が悩みながら制度を設計してるのかなというふうに思います。
そういう意味で言うと、兵庫県の場合にこの部門が受け付けると、こういうメリットがあるけど、ここが難しい、リソースが足りない、あるいは事案によって、事案に関係する人がいっぱい出てくると、その都度ほかの人が対応しなければいけないと、これだとなかなかワークしないんであれば、じゃあ、初めからその独立的な専門的なところをつくったほうがいいのか、件数がどれくらいあるかによっても変わってきますし、そこはよく、何が一番フィットする体制なのかというのを検討して進めるっていうことで、一般的にもよいのではないかなというふうに思っていて、何か、必ず独立してなきゃいけないということじゃなくて、独立しなきゃいけない案件のときに、そういった体制が取れるように、例えば、こういう関係するときは、この部分のモニタリング、例えばこの監査委員のモニタリングを受けるなのか、何らかそういう制度設計をする、そういった独立性が担保されるような仕組みをつくるというようなこと、それが公益通報の委員ということもあるでしょうし、いろんなパターンはあり得るのかなと思います。
○庄本えつこ委員
ありがとうございます。すごい基本的なところなんですけど、今回の事案の場合、3月12日に警察や報道機関、また県会議員に告発文書が送付、通報されたんですけど、3月27日の時点で人事異動が辞令されるときに、ご本人が、自分が告発した文書の中身について、きちんと調査をしてほしいということを申し述べてるんですね、当局に対して。その場合、私たちが勉強した中では、それは内部通報に、1号通報に当たるというふうなご回答をいただいたんですけれども、先生はいかがですか。
○参考人(結城大輔)
同じ理解です。これは今回の法改正がされる前から消費者庁から示されている解釈で、例えば窓口をつくっています、窓口への通報はもちろん1号通報なわけですけど、窓口以外の上司、担当役員、こういったところにこれは問題じゃないかということを指摘していって、その中身がその通報対象事実、その刑事罰があるような行為を指摘していくと、その部分は窓口以外でも公益通報に当たるということが解釈として示されていて、なので、今例に挙げられたような事案は、例えば3月27日の時点でこういう指摘をしました、窓口じゃないけれども、中で、そのしかるべき立場の人に対して指摘をしたとなると、これ内部公益通報に当たるというような理解です。
〇委員長(奥谷謙一)
最後、お一方、佐藤委員。
○佐藤良憲委員
すみません、先ほど伊藤委員が言ってた29ページの部分なんですけど、その下の2行の所あるんですけど、下の2行目で、例えば、信頼できる関係者等から具体的な内容を聞いた場合等っていう、これ両方等がついて広く示されてるんですけど、等を取って、信頼できる関係者、具体的内容を聞いた以外の方法で何を指して、等というふうに表現されてるんですか。
○参考人(結城大輔)
弁護士の悪いくせで、すぐ等をつけたがっちゃうんで、申し訳ありません。
例えば、伝聞でも、その数、いろんな人が言ってますとなるという場合に、もちろん数だけでは決まらないんですけれども、そういった数というものも関係するかもしれない。数が少なくても、この立場の人がこういうことを言ってるということだとすると、信頼できるっていうことになるかもしれなくて、数だけでも決まらないし、誰か、その立場だけでも決まらないしという、そういうようなことがあり得るというふうに思います。
現実に、認定は難しいんですけれども、証拠上は結構微妙でも、いろんな人がいろいろ言っていて、その中でこれは合理的な根拠あるよね、客観的に真実であるっていうところまでは要求されてないので、真実相当性に関して言うと、信じるに足りる相当な理由があったかどうか、正当な理由があったか、相当な理由があったかって考えたときに、これだけの人から言われていて、それが例えば今度は逆に、誰か対立している人から言われると、これは逆に、あそこはもともと対立してるんだから、対立している人から言われてるんだと、逆にその根拠としては不十分だよねっていう方向に働くしというようなことがあるので、そういったものをもろもろ考えたときに、これは信じるについて相当な理由あったんじゃないかとなったり、ならなかったりという、そのあたりがこの等に込められております。
○佐藤良憲委員
これ例えばですけど、この方、文書をつくられた方の陳述書というのがあるんですよ。
それは、もしかしたら見られてないかもしれないんですけど、その中をずっと見ていくと、誰に聞いたか忘れた、覚えてない、臆測っていう言葉がずっと並ぶんですよね。そうなってくると、信頼できる関係者とか具体的な証言には該当しないと思うんですけど。
○参考人(結城大輔)
そこは場合により得ると思うので、慎重に判断したほうがいいと思います。
○佐藤良憲委員
それでも場合によるんですね。
○参考人(結城大輔)
場合によると思います。
○佐藤良憲委員
分かりました。ありがとうございます。
○参考人(結城大輔)
例えば、この後ろの方の等ですけど、具体的内容を聞いたっていうふうに、場合等って書いてるのは、例えば具体的だけじゃなくて、よくその法律家だと確信性っていうんですけど、いかにリアルな中身が伝わってるかみたいなことも、やっぱりその供述の信用性を評価する上では見るところがあって、具体的だけではなくて、どれだけその感情面が盛り込まれているのかとかというようなことも、聞いた中身によっては関係するかもしれなくて、もろもろ総合的に考慮するって非常に微妙な判断になってくるので、それは誰から聞いたか覚えていて、この人がこういうこと言ってたという、覚えてるときと比べると、覚えてないのはもろもろ考えたときの評価としてはより慎重に判断しなければいけなくなるんだと思うんですけど、それだけでも決まらなくて、全体的に見るのかなというふうに思います。
○佐藤良憲委員
はい、分かりました。
〇委員長(奥谷謙一)
それではちょっとお時間が。1個だけ、増山委員。
○増山 誠委員
すみません、藤原弁護士がこの問題の公益通報に関して文書を出していまして、目的の正当性に関しては、不正の目的があったことは疑われるが、不正の目的があったと断定するまでには至らないということです。
通報対象事実に該当するかに関しては、第2条第3項に関して該当し得るのは、ゴルフクラブの贈収賄とパワハラによる暴行傷害のみであるというふうに回答されています。ほかは犯罪行為に該当しないとか、別表に掲げる法律に該当しないというところなんですが、ゴルフクラブに関しては記載されている事実自体は犯罪行為の事実の指摘であり、通報対象事実に該当する。(ただし、信ずるに足る相当の理由がない。)というふうに書いているんですね。全体の全ての項目を結城弁護士が見られた中で、この認識と何かずれのある部分というのはありますでしょうか。
○参考人(結城大輔)
まず、贈収賄、あとはハラスメントの中でも暴行などに当たるようなものが公益通報者保護法の言う通報対象事実に当たってくるっていうのは同じ認識です。じゃあ、その個別の事案について、真実相当性まで認められるかどうか、ここはもっと直接的にいろいろ証拠を見たりしないと、何ともコメントが難しいなと、そういう感覚です。
○増山 誠委員
分かりました。ありがとうございます。
○委員長(奥谷謙一)
それでは、お時間が参りましたので質疑を終了したいと思います。結城先生、本日は貴重
なご講演をありがとうございました。皆さんもいま一度、拍手で。
○参考人(結城大輔)
ありがとうございました。
○委員長(奥谷謙一)
以上で参考人招致を終わります。
この際、暫時休憩いたします。再開時間は午後1時です。
証人尋問(片山安孝元副知事)
動画
議事録(文字起こし)
○委員長(奥谷謙一)
それでは休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
片山安孝証人におかれましては、ご出席をいただき誠にありがとうございます。委員会を代表しまして御礼申し上げます。本委員会の調査のため、真相究明のため、ご協力いただきますようにお願いを申し上げます。
証言を求める前に、証人に申し上げます。
証人は、原則として、お手元に配付の留意事項に記載の場合以外、証言を拒むことや証言を求める場合の宣誓について拒むことができません。もし、これらの正当な理由がなく証言を拒んだときは、禁錮または罰金に処せられ、また、虚偽の陳述をしたときは、禁錮に処せられることになる場合がありますので、ご承知おきください。
また、証人は尋問された事項に対してのみ証言をしてください。尋問内容が不明確なため、証人がその疑義をただすために、私や委員に対し、確認の質問をすることは可能であります。それ以外の質問や反論はできません。
加えて、元県民局長のプライバシーに関わる情報については、元県民局長の代理人弁護士から取扱については、十分に配慮いただきたい旨の申入れがあり、当委員会において取り扱わない旨、委員会内で合意をされております。
証人におかれましても、発言に御留意をお願いいたします。
なお、以上のことで、それらに反した場合は、発言を中断させていただきますので、その点あらかじめご了承ください。
それでは、法律の定めるところにより、証人に宣誓を求めます。傍聴の方、報道関係の方含めまして、ご起立をお願いいたします。
(全員起立)
それでは、証人は宣誓書の朗読をお願いいたします。
○証人(片山安孝)
宣誓書。
良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓います。
令和6年12月25日、片山安孝。
○委員長(奥谷謙一)
それでは、ご着席をお願いします。
(全員着席)
証人は宣誓書に署名をお願いいたします。
(証人 宣誓書に署名)
証言に当たっての留意事項はお手元配付のとおりですので、ご確認をお願いいたします。
委員各位に申し上げます。
本日は、事前に証人に通知をいたしております証言を求める事項について、証人より証言を求めるものであります。
尋問に当たっては、証人の人権に配慮されるとともに、円滑な議事進行にご協力をお願いいたします。
また、委員会冒頭にも申し上げましたが、発言される前には個人情報等について十分配慮いただきますようにお願いを申し上げます。
これより片山安孝証人から証言を求めます。
私から所要の事項をお尋ねし、次に、各委員から発言を願うことにします。
それでは、片山安孝さんで間違いないでしょうか。
○証人(片山安孝)
はい。まず最初に人定尋問があるんですか。
○委員長(奥谷謙一)
はい。
○証人(片山安孝)
分かりました。
○委員長(奥谷謙一)
片山安孝さんでよろしいでしょうか。
○証人(片山安孝)
はい、そうです。
○委員長(奥谷謙一)
住所、職業、生年月日は、事前にご記入いただきました確認事項記入表のとおりで間違いありませんでしょうか。
○証人(片山安孝)
はい。
○委員長(奥谷謙一)
それでは、各委員から個別尋問をお願いします。
それでは、自民党からお願いをいたします。
○証人(片山安孝)
委員長、その前に先ほど委員長からの注意事項について確認をしたいと思うんですが、よろしゅうございますでしょうか。
○委員長(奥谷謙一)
はい、どうぞ。
○証人(片山安孝)
人権に配慮したということでご説明がございましたけれども、このことについて1点だけご確認をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
といいますのは、12月17日の神戸新聞に、県議会の調査特別委員会の聞き取り調査で複数の県議が西播磨県民局長の私的情報を前総務部長から聞いたと、この報道でございました。
このことにつきまして、あれっと思ったんですけれども、その後でネット等では私が何か指示をしたとかいうようなことになってます。このことですね、12月11日の、ちょっと委員会を調べましたら、秘密ということで調査をしているにもかかわらず、このようなことが報道されているということ。しかも、ネットでは、私が指示をしたというようなことは流れてる。このことは、守秘義務が必要な委員会の情報が流れて、私にプレッシャーを与えていると、このことではないかと思いまして、それを調べておりましたら、12月11日のこの委員会で、情報管理の申合せがなされております。にもかかわらず、このようなことになることについて、委員長に対して疑義を申し上げたいと思っております。
〇委員長(奥谷謙一)
はい。
〇証人(片山安孝)
しかも、もう一つだけ、同じことですから。
〇委員長(奥谷謙一)
はい。
〇証人(片山安孝)
しかも、この委員さんが調査いたしました対象が県議会議員というふうに伺っておりますが、私はこの場で公開で氏名を述べて証言に応じておりますが、県議会の議員さんは、公人であると思いますので、複数というふうに神戸新聞はなっておりましたが、これお二人というふうなことがほかの報道でも確認できました。
これはやはり、私がここで証言していることの均衡上ですね、氏名を公表されるということがよろしいのではないかと。二つ目は要望でございますが、一つ目の、やはりこの情報が漏れるということについて12月11日に申合せがあったにもかかわらず、こういうことになった。しかも、証人に対する圧力になるような形で流れておることにつきまして、疑義を申し上げたいと思っています。
このことは10月25日に私が証言した際も同じことが起こっております。10月25日の朝、神戸新聞を見ましたら、前日秘密会があったかと伺いましたけれども、そのときの信用金庫の理事長の証言内容が流れておりまして、片山副知事から金額を言われた、偽証ではないかと。このときも秘密会の情報が外へ流れて、しかもねじ曲げて投げられて、信用金庫の理長は、そのことは後ほど虚偽であると、そのようなことは言っていないと言われてましたが、そのようなことが流れておる。これで2回目になっておりまして、このことにつきまして、まず委員長から情報漏えいについて証人の、今人権に配慮するとおっしゃいましたけども、このことについて、いかがなものかということについてお伺いいたしたく、それからご質問に対するお答えに入っていきたいと思っておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
○委員長(奥谷謙一)
はい、ありがとうございます。本日は証人尋問の場でありますので、ご要望いただきました点については、後日対応させていただきたいと思います。
それでは自民党のほうからご質問をお願いします。
○黒川 治委員
それではお願いをいたします。まず、政治資金パーティーのことについて伺いたいと思っております。
齋藤知事は就任後、令和4年12月、その後、令和5年7月と2回政治資金パーティーを開催されておりますけれども、このパーティー開催について当時副知事であった片山氏のほうに依頼、かなり片山さん自身がこのパーティー事業について活動されてたというお話がございますけれども、このパーティー開催について、知事のほうから片山さんのほうにどのような指示、あるいは依頼というものがあったんでしょうか。
○証人(片山安孝)
知事から後援会の活動について十分な体制ができていない。したがって、政治資金パーティーをやりたいんだけれども、それに前提となる名簿が集まっていない。したがって、名簿集めについて手伝ってくれないかと、こういうふうにお話がございました。
○黒川 治委員
体制をつくりたいから名簿を欲しいということでありますけれども、まずその前に。
○証人(片山安孝)
体制をつくりたいじゃなくて、政治資金のパーティー券を売るために名簿を、どこにどういうふうにご案内していいかという蓄積がないので対応したいと、こういうふうに、それについての手伝いをやってくれないかと言われましたので、手伝いました。
○黒川 治委員
はい、分かりました。それを、依頼を受けて、片山さんのほうから令和5年の分についての話になりますけれども、当時、古川信用保証協会の理事長、そして信用保証協会専務に対してお手伝いの依頼をされたということは間違いございませんでしょうか。
○証人(片山安孝)
それは間違いないです。県職員の知ってる者で、やはり声をかけてやっていかないといけないということしか私はノウハウがありませんでしたので、名簿集めをするので手伝ってくれ、ただし、それはあくまでも個人としての位置づけであるから、その点だけはよろしくお願いしますねということを言いました。
○黒川 治委員
分かりました。2人に依頼をして、先ほど言いましたパーティー券の販売先の名簿集めであるとか、そういうことの依頼ということであったというふうに思っております。
その2人からの証言によりますと、名簿集めのということでありましたけれども、2人に依頼されたのは県内の各商工会議所関係のところに行って、もう連絡をしているので、名簿を取りに行ってくれということであったというふうにありましたけれども、それは事実でしょうか。
○証人(片山安孝)
はい。名簿のお願いはあらかじめ私が各商工会議所なり商工会だったか、ちょっと忘れましたけど、それぞれのところに依頼をしてて、取りに行くので名簿だけをいただけませんかというふうにお願いした記憶があります。
○黒川 治委員
今で言いますと、2人に対して、表現悪いかも分かりませんけれども、こどもの使いというか、ということであったというふうに思うんですけれども、各商工会議所関係のところに、なぜこの信用保証協会の理事長あるいは専務である2人に依頼をされたのか。
○証人(片山安孝)
結局、そういうような名簿集めをやろうと思ったんですけれども、やっぱりなかなか県職員OBでそれに協力してもらうということは、人数が確保できません。その中で、やっと確保できましたので、彼らに行ってもらおうというふうに考えたわけです。と申しますのは、知事が外郭団体の、役員の定年を65歳というふうにしておりましたので、手伝ってくれというのも、前の井戸県政のときは、66歳以降もそういうような選挙頑張ったら残れるということで、いけたんですけども、もう65歳以降のそういうことはできませんので、もう何とか私のコネで何とか頼んだということで2人に頼んだんで、どないぞ行ってくれなと、こういうことをお願いせざるを得なかったので、よう知っとるやろ、おまえらというふうな感じも内心ありましたから、場所もね、一々言わなくてもいいですし、商工会議所とか、そういうとこへ行ってもらえると思いますので、ただ彼らにも全くのボランティアで頼みましたので、私が全部電話して、全部調整しとって、今、こどもの使いと言われましたけど、ボランティアですから、何のメリットもなく手伝うてくれということになりますんで、まあ全部私が電話したという次第であります。
○黒川 治委員
まあいいでしょう。以前、片山さん自身も信用保証協会の理事長という職にあられました。そういう経験もあられたということで、その職責上、信用保証協会の役員というそういう職責上、政治的なことに接するのは控えるんだというような発言をされておられたということを伺っておりますけども、それは事実でしょうか。
○証人(片山安孝)
私は、それは政治的な行為を控えると言った記憶はないですけれども、令和3年7月の知事選挙については、私は中立でいますよというふうに、ほとんどの先輩方からおまえも何で井戸さんの後援会の仕事、金澤さんを応援せえへんのやと厳しく言われましたけども、いや、私はもうその選挙はもう中立ですよと言うた、そのことを指しておられるんではないかと思いますね。
○黒川 治委員
政治的に中立であるというのは、選挙のときに現職の理事長であられたので、そのときのことを指している話がこうやって出てるんだということですね。
○証人(片山安孝)
そのときに理事長というよりも、私自身ということで言ったつもりでしたけども、言ったときは理事長でしたから、そういうふうに取られることになったかというのは結果の問題かと思いますね。
○黒川 治委員
今回、先ほど言いましたOBの中から人選して気安く声かけれる、後輩であるんでしょうか、仲間内という形で2人に声かけられたということでありますけれども、その2人のご自身が経験した中で、先ほど選挙では中立的な立場を取ったということでしたけれども、その1人の政治家の政治資金パーティーの手伝いをその職にある2人に対してやるということに対して、何も考えなかったんでしょうか、思わなかったんでしょうか。
○証人(片山安孝)
私思いましたのは、そういうような役職に就いて仕事をするということではなくて、みんなすまんけど、個人の資格でボランティアでやってくれなということにしておりましたので、本人にもいろんなところへ行くときは申し訳ないけど、自分の車で行ってくれよとか、要は今の役職とは違う仕事をやってくれということで注意してて、本人たちにも分かったということで、その上で手伝いますということで手伝ってくれたと、こういう認識があります。
○黒川 治委員
2人の方の証言から言うと、まさしくおっしゃいますように、あくまでもボランティア、役職ではなくて個人の立場で活動しましたというお話はされておられました。それはそういう思いであったということが続いておったのかも分かりませんけれども、結果としてですけれども、お2人とも相手さんに尋ねて行った先でのご挨拶という形で、信用保証協会の役員という形の名刺交換をされてます。
そして、パーティーのチラシという、結果的には申込用紙的なものを配布、お渡ししたりもしています。また、訪ね先の幾つかにおいては、協力頼むねというようなニュアンスの話もしてしまったということで、お2人ともが結果的にそういう行為に及んでしまったことについては反省してますというのがこの場での話でありました。
ということは、あくまでも個人だと、確かに公用車じゃなくて自分の車、休暇を取って行った。勤務中だったけれども、時間休を取って行ったという話もありましたけれども、結果としてそういう信用保証協会の役員が商工会議所関係を訪ねていって、知事のパーティー券を買ってもらうための名簿を取りに来ましたという行為は、何もないと感じますでしょうか、相手に対して。
○証人(片山安孝)
私は十分注意をするということで注意してやろうということで心がけたと、そのつもりです。今、委員のほうからは結果的にという言葉が頻繁にお使われになってたと。このことについては、結果的にということについてのご指摘は真摯に受けますが、やってるときは彼らとも十分これは前の井戸さんのときみたいに県職員OB丸抱えにならんようにしようなと、はっきり彼らにも言いましたんで、十分ボランティアとしてやってたというつもりはありましたが、その名刺を渡したということまでの注意喚起とか確認までしてなかったということは認めます。
○黒川 治委員
お2人がその活動をされているときに片山さん以外のその職にあった方、県職員OBの方から、数名か1名か、ちょっと私確認できておりませんけれども、県職員OBの方からその立場で、そのような活動をしたらいかんぞという注意を受けたというような話もあって、やはりそういう職に立ってる者、県職員OBの方が就かれてる職ということかも分かりませんけれども、特にその役職にある者については注意をしてこないといけないんだという認識が県職員OBの方にあったんですけれども。もう一度確認しますけれども、単なる県職員OB、親しいOBやから頼みやすかったから頼んだっていうんじゃなくて、そういうところに信用保証協会の役職者に行ってもらうということに何も疑問というか、ちゅうちょもなくお願いされたんでしょうか。
○証人(片山安孝)
ちゅうちょもなくといいますのは、十分注意してやろうということで、ボランティアということでやってもらうということでやっておりましたので、その面でいって、ちゅうちょとかいうことではなくて、注意してやろうなと。要は役職やから動いてるんじゃなくて、あくまでもボランティアやということで対応してやろうということでやっておりましたので、彼らもそういうふうなつもりやったんではないかと思っております。
○黒川 治委員
結果的で、また言いましたけれども、そのようなやり取りがあって、2人も注意をして行っておられたようですけれども、問題は訪ねてこられた側です。相手側です。相手側がそのようなやり取りが、例えば立場を利用して行ってこいって言うてないわけですけれども、受け取る側にしてはどう思うというところまでは考えなかったんですか。
○証人(片山安孝)
受け取る側についてのところを、その指示したときとか、相談したときには、あくまでもボランティアやということでやっとるんやでということで話をしましたので、その点についてはボランティアとしてやってねということでやっておりました。
○黒川 治委員
いやいや、そうではなくて、受け取る側は相手がボランティアなのか、雇用されているのか、何で来てるのか分からないですね。でも、間違いなく信用保証協会の理事長が来た、あるいは信用保証協会の専務が来たというのは事実としてあるわけですよね。その相手の気持ちを考えなかったんですか。
○証人(片山安孝)
こちらはもう名簿を集めるのに必死でしたから、どの段取りでやるかということで、その手段を考えているということになりますので、そこまでということを、私は彼らにも指示をしておりませんので、その点についての認識は、そのときに指示しておりませんから認識があったんかと言われたら、なかったということになると思います。
○黒川 治委員
名簿を依頼されたのは電話ではなくて、訪ねて行かれたりして、直接、商工会議所とかに訪ねて行かれたりしてお願いしておったという話も聞きましたけども、それは事実でしょうか。
○証人(片山安孝)
私がですか。それ、私がっていうこと。
○黒川 治委員
はい。
○証人(片山安孝)
副知事をやっておりましたので、そんなちょっと余裕がなかったので、ほとんど電話やったと思いますが、多分いろんな会合ございますよね、そのときに会ったときに、また名簿が欲しいんだけどもということで、ただ手間をかけたらいかんので、後援会のスタッフが取りに行くことになるかもしれないので、よろしくお願いします。名簿を何とかお願いできませんかと言って、会合のときに言ったことはあるかもしれませんけども、基本は電話が多かったかなというふうな記憶ですね。
○黒川 治委員
電話あるいは直接チャンスがあったときには面談で、じかにお願いしたことがあったかもしれないということですね。
○証人(片山安孝)
はい。
○黒川 治委員
今、そのお話の中で事務所の者が取りに行くから頼みますねというお話をされましたけれども、そのときに信用保証協会の専務が行くから、理事長が行くからというふうには言わなかったですか。
○証人(片山安孝)
職名を言った可能性はあるかもしれませんが、はっきりとは覚えておりません。
○黒川 治委員
分かりました。今2人の方を特出ししてお話をしましたけれども、その2人からのお話の中に県職員OB16名という数字も出たんですけれども、実務世話人会と称する16名の方々がこの政治資金パーティーの準備に動かれたというふうに聞いておりますけれども、この16名の方っていうのは、先ほど2人を選ばれたように、片山当時副知事が声をかけやすい県のOB職員あるいは後輩という立場の方々にお声かけて選ばれたんでしょうか。
○証人(片山安孝)
現職には声をかけるわけにいきませんので、後輩ということは、ちょっと誤解を招く表現でありますので、県職員OBだけです。県職員OBだけで、先ほど申しましたように、私としてはノウハウがありましたのは井戸前知事のときの後援会の動きだけですから、井戸前知事のときは100人以上、たくさんの県職員OBの方集めてやっておられましたけども、それについて集めるだけの自信がありませんし、何とかボランティアで何のメリットもない中で手伝うてくれよとお願いできんかなということでやりましたけど、事実上、私よりも年下で県職員のOBであると、つまり当時でいきましたら、私が63歳でしたから、62歳か61歳ぐらいの1年目、2年目の人に声かけて、何とか手伝いますよと言ってくれたのが十五、六人集められたということだったと思います。
○黒川 治委員
まあ何とかということですから、声かけられる、声かけやすい方の、そういう県職員OBになられて1年目、2年目の方にお願いして手伝ってもらったっていうことですね。
○証人(片山安孝)
そうです。
○黒川 治委員
そういうことですね。
無事にというか、令和5年7月の政治資金パーティーも終わられたという後に、ご苦労さんやったということで、打ち上げの会、反省会という名目だったでしょうか、されたというふうに伺っておりますけれども、それは事実ですか。
○証人(片山安孝)
はい、私が主催してやりました。
○黒川 治委員
片山当時副知事主催での打ち上げ。その席に齋藤知事もお見えになられましたでしょうか。
○証人(片山安孝)
来てないと思いますね。
○黒川 治委員
そうでしたか。
○証人(片山安孝)
いや、来たかな。はっきり覚えてないです。
○黒川 治委員
そうですか。来たというお話も伺っておりますので、それは今。
○証人(片山安孝)
はっきり覚えてないですね。
○黒川 治委員
覚えてないですか。分かりました。
○証人(片山安孝)
来たのかな、いや、来てないかな。覚えてないですね。
○黒川 治委員
結構です。この反省会、先ほど自分が、片山が主催したというお話しになられましたけども、この反省会の費用は、じゃあ、片山さんがお支払いになったんでしょうか。
○証人(片山安孝)
全部私が払いました。
○黒川 治委員
それはポケットマネーで。
○証人(片山安孝)
ポケットマネーで全部払いました。
○黒川 治委員
そうですか。これ、パーティー、自分が声をかけた、独自の応援隊というか、パーティー事業に対する活動体ということだったので、この費用について、例えば、パーティー事業を行った政治団体に対して要求するとか、請求するとか、そういうことではなかったんですか。
○証人(片山安孝)
全然、もうボランティアでやろうと。この活動をしたことについての対価とか、そういうようなことについては、もう何もないですよというふうに、16人の人に言ってましたので、ただ、それで名簿集めにいろいろ行ってもらったということで、私は申し訳ないと思ってましたので、しかもほかに何もありませんから、一応、皆ようやってくれたからということで、ご苦労さんせないかんなと思って、自分で全部段取りして、場所も全部自分で段取りして、金も全部自分で払いました。これはもうボランティアでやって、もうご苦労さんやったなと、この思いからです。
○黒川 治委員
結果的にですね、その後に、実はこの後3回目の政治資金パーティーも予定されておったんですけども、できなかったということを伺ってるんですけれども、3回目が予定どおり開催されるということの運びになったときは、またこの16名プラスアルファあったかも分かりませんけれども、同じように協力要請をするようなイメージだったでしょうか。
○証人(片山安孝)
当然、やろうと思ったら、もうその16人ぐらいに頼らんと、ほかに1人ではできませんし、私も仕事、当時は副知事をやっておりましたので、そこに頼んでやっていこうと。ですから、とにかくもう人数が多かったらええなと思ったんですけども、そこはやっぱりそういうふうにOB丸抱えでやったら、旧県政、井戸さんと同じようになるやないかと思いましたので、違うやり方でやって、とにかく少ない、最低限の関係であると。
ただ、3回目のときに、同じように必要なのかどうかということについては、私は必要やったかどうかは、ちょっとやってないから分かりませんけれども、最初やりましたのは、とにかく知事から言われたときに思いましたのは、一度もそういうことをやったことがないので名簿がないんですと、片山さん手伝うてくれませんかって言われました。これ確かにそうやったと思うんですが、1回やってて、2回目は名簿が手元にありますよね、だから同じように県職員OBを動員して、たった15人でありますけれども、必要があるかどうかは、やってみてないので、ちょっとそこは分かりませんね。
○黒川 治委員
知事からパーティー事業をやるためのということで依頼されたからスタートしたことですけれども、この政治団体、ひょうごを前に進める会という政治団体だったと思いますけれども、そことの関係っていうのはないということでよろしいんでしょうか。
○証人(片山安孝)
関係がないというのは。
○黒川 治委員
片山さん個人とそこの団体、例えば、そこ団体の役員に入ってるとか、そこの団体から直接、団体の関係者から直接やり取りがするような間柄であるとか。
○証人(片山安孝)
全然それはありません。もう知事から名簿を集めるのを頼むと言われて、それでやっておりましたので、その政治団体の役員になったりとか、そういうような事実は一切ございません。
○黒川 治委員
そうですか。はい、分かりました。私からは結構です。
○富山恵二委員
私からお尋ねさせていただきます。片山前副知事については、もう片山さんと呼ばせていただきますので、よろしくお願いします。
阪神・オリックスパレードの協賛金の関係、ちょっと確認をさせてください。
協賛金の収集については、知事のほうから片山さんと原田部長、お2人に中心になってやれよっていう指示があったっていうふうに認識してるんですが、間違いないでしょうか。
○証人(片山安孝)
本来やるべき県民生活部には、あらかじめ指示は全部下りておったと思います。
県民生活部のパレード担当部門が動いてましたですけども、やはり協賛金の集まりが悪いということで、産業界に呼びかけなきゃいけないということで、原田部長にと。
私は、別に知事から言われたんじゃなくて、もうパレード担当部門から集まりが悪いというのを聞いてましたから、皆が頑張って、いろいろお願いに回ってくれてるということを聞いておりましたんで、自主的にいろいろと動いてた中で、知事からも片山さんもお願いしますねって言われたのはありましたけど、それよりも前に動いとったということは事実です。
○富山恵二委員
そうですか。私が調べた資料の中では、知事から片山さんと、それから原田さんに中心になってという指示が出てるようなペーパーが、ちょっとまだ確認しないとあれですけど。
○証人(片山安孝)
だからそう言われたことは言われたんですけど、その前から動いとったということを今説明しただけです。
○富山恵二委員
分かりました。
次に、パレードは23日ですけれども、その前の17日ぐらいに片山さんと原田部長の間で協賛金集め、20日ぐらいまでやろうかなという話が進んで、今度、井ノ本さんのほうから片山さんに協賛金については20日、月曜日まで勧誘していただければいいですよっていうような発信がなされてるっていうふうにあるんですが、それは事実でしょうか。
○証人(片山安孝)
20日という日は覚えてないんですけども、それよりも、僕はもう、とにかく行けるとこまで集めなあかんやろがいと言った覚えがありますので、何日までというようなことは、あんまり鮮明には覚えてません。もしかしたら、やり取りのときに23日やから20日ぐらいまでにせないかんなということは、事務部門が言うとったかもしれませんけども、とにかく、その日まで頑張ろうかいなと言ったような記憶がありますね。
○富山恵二委員
ただ、その17日ぐらいに片山さん自身が吉報やということで、何人かの幹部の人にお金の形が入ってるよって、それを受けて井ノ本さんからそういう形が出てるっていう記録があるんで、ちょっとお尋ねさせていただきました。
○証人(片山安孝)
吉報やと言うたかもしれません。というのは、パレード部門もみんな一生懸命協賛金集めに回ってくれてましたんで。副知事もこんだけ取ってきたぞと言うたような記憶がありますので、それは言うたかもしれません。
○富山恵二委員
ありがとうございます。それで20日までっていうことでいう話が出てるっていうことは、大変やったということは今おっしゃったんですが、一応20日で大体めどがつくなっていう形だったと思うんです。そういうやり取りがあるっていうのは、20日まで頑張ろうかっていうのは。めどがないと多分そういうことは言わないと、事実的に通常の場合は思われるので。
それが、片山さんが急遽21日に、ある信用金庫の理事長にお会いして、何とかまだという話が、この間もお聞きしたとおりあったんで、もうそういう、逆にせっぱ詰まった感がないと。20日で終わろうかって言うてるのが、何が起きたか、何かその記憶にあるものありますか。
○証人(片山安孝)
いえ、もう20日の日のときも20日でやめるなという認識は私もしてませんでしたし、とにかくもう実行委員会からの方針は、クラウドファンディング、プラス協賛金と言ってましたので、公費は投入しないということになってましたので、これ集め切らなあかんなと、この思いだけでしたので、20日に切るというイメージ、もしその打合せで20日を一つの基準点にしてたのは事実かもしれませんけれども、とにかく集めないかんなという認識はずっと持っておりました。
何かそのときに大きなあれがあったかどうかやなくて、とにかく集まってない分は頼みに回るから、みんなも回れよという話をした記憶があります。
○富山恵二委員
いや、今、片山さん自身がおっしゃったように、せっぱ詰まった中で、一応、井ノ本さんも副知事に20日まで勧誘してくださいって、現に言われてるみたいなんで、だから一応めどがついた後、当然収支の状況は刻一刻と原田さんとか、井ノ本さんとか、片山さんなんかが共有されてるんだろうなっていうのが資料で見てとれるんでこういう質問をしてるんですが、しかもこの信用金庫は17日ぐらいに、協賛金を片山さんのご努力があって入れますよっていうんで、地域のためにという形で入れていただいている。そこに、あえて21日にもう一度行かれてるというのが、その理由が知りたくて。
○証人(片山安孝)
そのときにパレード事務局から、もうお金が足らないですと言うてきたので、とにかく一番地域振興に理解のあるところに頼みに行こうかいなと、このように思うたんですけども。
僕20日、20日と、今いろいろ言うて、20日って、そこまでのイメージはないんですけど、とにかく収支が足りませんと。しかも、まだその時点では歳出のほうも、まだ不安定要素が結構ありましたので、パレードはまだでしたから、これもとか、あるいは人件費とか、警備費なんかも、いろいろ詰めて、細かい詰めをやってましたので、なかなか収支が合うかどうかということは自信がありませんでしたので、もう頼めるところはみんな頼もうかいということで、私だけじゃなくて、多分、事務局職員も一生懸命、準備やってるところは準備やってましたけど、そうでない部分はやってましたし、産業労働部門についてもお願いは、行けるとこは行けよということで頼んで収支を協賛金ということで、これはとにかくお願いせなしゃあないねんからということで、結局、事務局なんかもいろいろ頑張ってくれましたけど、お断りになられたというところですね、私も当然断られたところもありますけども、その中で、いろんなところ回っとったと。その一つが話に応じていただけたのが信用金庫のほうだったということだと思います。
○富山恵二委員
ありがとうございます。この資金集めについては、片山さんがほとんど大半を占めているというのは、我々の調査でも事実として、ご努力はもう本当に認めるわけなんですが、当然に、収支の関係もそういった形で、やっぱり逐一今お金が、大阪府と共同でやってたから、兵庫県は何ぼ集めなさいっていうやり取りがあり、片山さんのほうにも入ってた中で、残りがもう前日ぐらいで、しかも、県内広い企業がある中で、数日前に入れていただいた信用金庫グループにもう一度行かれた理由っていうのは、何か
○証人(片山安孝)
それはもうほんまに理事長には申し訳ないと思っております。そやけど、もう頭下げに行かんことには、お金を集めなあかんと。もう、こういうことですから、とにかくできる限りの額をお願いしますということで、行きました。
そういうときに行こうと思ったら、やっぱり無理をお願いすることになりますから、どうしても知ってる人のところへ行かざるを得ない。こんな感じやったと思いますので、何とかお願いするというて頼みに行きました。
○富山恵二委員
ありがとうございます。片山さんも組織人やったからやと思うんですけども、理事長がご努力で、そのとき冒頭の話にもありましたけど、金額が何ぼ欲しいとは言ってへんけど、2人の間で1,000万かな、2,000万かなというような話の中で、結果として一定の数字が出たっていうことなんですが、やはりそれぞれの信用金庫も理事長のご努力もあったと思いますけれど、やっぱり内部的に多額のお金を出すときにはいろんな、いわゆる稟議、決裁が必要なはずなので、そこがその短期間の間でできるのかなという、そういう難しさは片山さんとして、理事長のほうから聞かれたとか、それはありましたか。
○証人(片山安孝)
そういうようなことで、難しいとか、そういうことは聞いておりませんけども、私自身としては、むちゃくちゃ無理を言いに行ったなということはありました。ただ、事務局に確認したとき、協賛金の受付日関係はパレードの日までやなくて、たしか1ヵ月ぐらい後にしますということですから、それまでに何とか歳入をしてもらえたら、事務の運営上はいける可能性もありますし、とにかく今足らない分についての確保が必要ですというのは事務局からよく言われておりました。
○富山恵二委員
ありがとうございます。結果として21日に行かれて、前回も22日にほぼ決着がついたみたいなお話だったんで、それならもっと早く、期間があれば、そういうところになぜ行かれなかったのかという疑義だけが残ったので、確認の質問をさせていただきました。ありがとうございます。
○委員長(奥谷謙一)
時間が経過。維新の会、お願いします。
○増山 誠委員
パーティー券の件で少しだけ、井戸さんのときは県職員OB丸抱えでやってたというご発言あったんですけど、これ保証協会の理事とかも入ってたんでしょうか。
○証人(片山安孝)
私のところへ来てなかったと思いますから、入ってなかった。私は、そこへ入ってませんでしたから、私の信用保証協会の役員でね、入ってないかもしれません。
それはもう本人が入るかどうか決めるんですから、逆に、今回の16人はもう入る人が誰もおれへんから私が頼みに回ったんですけども、過去の場合は、本人が入る、入らないということで、たくさんの人が入ってたと思いますので。
○増山 誠委員
分かりました。
次に、クーデターについて伺います。元西播磨県民局長が公用PCで作成した私的文書の中には、関係者と会話した内容や感想などが日付入りで数多く記載されておりまして、簡単な日記のような形式になっているものがあります。幾つか例として挙げますと、まず日付が令和3年9月12日、約3年前、知事が就任して間もない時期なんですけれども、内容としては『荒木副知事から元西播磨県民局長に連絡があった場面。小橋・原田と協議した。あと2人の態度は酷い。仕事もできないくせに偉そうに。井戸さんからは、荒木副知事は粘って残れと言われている。井戸・金沢からそれぞれ連絡があり、金沢さんはSさんが面倒見ることになったようだ。顧問として。』などという記述がありまして。
青文字は、公式議事録ではカットされ、筆者が文字起こしした発言です。以下同じ。
○委員長(奥谷謙一)
あんまり個人名は出さないように。
○増山 誠委員
これは特別職をご経験された方だったらいいと思ってるんですけど。
それを言われると何も質問できないんですが。状況がつかめないと。
○委員長(奥谷謙一)
例えば、役職、当時の総務部長とか。
○増山 誠委員
当時の役職、はい分かりました。前副知事などと記載がありまして、前副知事が退任後も県人事に干渉してきている様子がうかがえました。
次に、その3ヵ月後の令和3年12月14日、元西播磨県民局長・教育次長・人事課長・他1名が姫路で飲み会をした場面の記載があります。
まず、人事課長が人事情報を皆に教えるような記載がありまして、『〇〇副知事が退任し一人体制になる。県民局長の異動はない。教育長・防災部長はF氏・E氏』というような会話があります。
次に、教育次長が幹部の人間関係について話す場面になりまして、『室長の〇〇ちゃんが最近よく自分に接触してくる。〇〇のことを良く思っていない。』と発言し、これを聞いた元西播磨県民局長は「このあたり剝がしたら何か起こるかも」と感想メモらしきものを残しており、まさにクーデター計画が芽吹き始めたような記載をされております。
さらに3ヵ月後、令和4年3月25日には元西播磨県民局長のクーデター計画を実行に移していく状況を示す以下の記述があります。『今後、教育次長が〇〇室長に接触し、片山と〇〇組とを分断させる』というような内容の文章であります。
次に、奥谷委員長が確認して、全く関係ないと判断された文書についてでありますが、元西播磨県民局長が携帯電話から自分宛てに送ったメモとされる文書を引用します。
これは「片山、ほか3名の左遷、適切な人事評価、対外的に我々の思いを公表する」といった気に入らない幹部を左遷させたいという意図の記載があり、その後に怪文書の作成と配布を類推される記述が続きます。
少し引用しますと、『知事が維新に傾いたとき、その違和感は逆モーションで増幅し取り返しのつかないへだたりとなる。』『怪文書をあちこちにばら撒いてみる。〇〇室長が片山に相談したら片山は握りつぶす。その後でマスコミに撒く。マスコミから知事に直接あのペーパーが行く。マスコミには写しを同封し、知事に見たことがあるか、これは事実か確認させる。知事の信用を失った人事当局がいかにしんどいか思い知らせる。』『片山他3名を仲違いさせる。出番が来るまで待つ。辺境の地で待つ。クーデターを起こす方法はあるのか。メンバーはそろっている。担ぎ上げるリーダーは?』という形で記載がされております。
これに加えて、詳細な人事案というのが40ページ余り作成されておりまして。
○委員長(奥谷謙一)
増山委員、そろそろ質問していただけますか。
○増山 誠委員
もう質問に入ります。公用パソコンにはこのような資料があって、公用パソコンを調査することで、間違いなく今回の文書作成の動機や目的が明らかになったというふうに思うんですが、資料全体を通して見ると、政権に打撃を与える目的を持って特定の幹部をおとしめたり、仲たがいさせる行為を計画し、実行していることが明らかだなというふうに感じた。また、反齋藤派と思われる職員の名前がたくさん出てきて、人事案は反齋藤派職員で、知事の周りの主要ポストを固めるような内容になっておりました。
この内容を総合すると、まさにクーデターを画策していたように感じるんですが、片山元副知事の認識というのは、こういった文書に基づいて、どういったものでありましょうか。
○証人(片山安孝)
今おっしゃられましたのは、公用パソコンの中を見られたということですよね。
元西播磨県民局長は私の部下だったので、よく知っておりますけれども、彼はメモをきちんとやる人間でした。全部書き留めておりますから、今お話しになったことは、ほぼ事実やと思います。
先ほどちょっと聞き取れなかったんですけども、前知事が退任後も人事に介入しとったと、そないいうておっしゃられたんですが、副知事じゃないですよね、前知事ですよね。
○増山 誠委員
前知事です。
○証人(片山安孝)
当時は、ちょうど政権発足の1ヵ月半後ぐらいで、私がまだ副知事になってないときでした。そのときには、元西播磨県民局長は私の前任の、委員長、これは特別職も個人名は言わないということで運用されますか。
○委員長(奥谷謙一)
できれば、配慮していただければ。
○証人(片山安孝)
でも、私は片山、片山って、ずっと言われてるんですけど、こことの均衡はどうしましょ
う。
○増山 誠委員
そのとおりですよね。もう個人になられてるのにもかかわらずということですよね。
○委員長(奥谷謙一)
証人ですからね。
○証人(片山安孝)
ちょうどこの頃は、私の前任のA副知事が中心になってて、元西播磨県民局長はそこへいろいろ頼みに行ってたと思います。そこに対して、前知事がいろいろと関与してたと。この流れで前知事、前副知事、前副知事は前政権のときから副知事でそのまま、進退伺を出されずに、そのまま残留されてたというような感じになっておりますけれども、そこと、それから今お話にありました元西播磨県民局長と、こういう関係があって、いろいろと相談してたことを示している資料だと思います。
現に、私が令和3年9月21日に副知事になったときに、当然、前任の副知事がいらっしゃいますから、そこへ挨拶に行きましたら、こう言われました。片やん、何でも変えるのがええのと違うぞと一喝されました。だから、前の知事とお話しされとったということが書いてあるということは、一定正しいんじゃないかと、このようにも思ってますし、9月6日の日に竹内さんがしきりに、前の副知事のことを非常にすばらしい人や、おまえ、それ失礼やないかと。これ9月6日の証言のとき、記録見てもうたら分かるんですが、しきりに竹内さんはそう言ってました。これは竹内さんは、もしかして公用パソコンの中に、前副知事のことが書いてあることを知られたらまずいということで一生懸命言うとったのかもしれません。ということは、竹内さんは公用パソコンの中に何があるかを知っとったのかもしれない。これは推測です。
こういうような状況ですけれども、このような事実のことが公用パソコンの中には非常にあるということです。
それでいきますと、結局、彼らがターゲットにしとったのは、当時私はいませんから、知事、それから側近グループ、今名前が少し出ましたけど、2人ぐらいと、この対立関係が出てくるんじゃないかと思ってます。
このクーデターにつきましては、側近グループの仲間割れとかいう言葉、文言並んでます。これ単に文言並んでるかもしれませんけれども、今のお話聞いていただきましたら、仲間内で情報収集してますし、自分たちに都合のいい人事案をつくっている、こういうような資料と分かりますので、メールは単なる文言の羅列だけではなくて、そのメールの文言に基づいて行動してたことが分かるのではないかと思います。
齋藤知事の周り、主要ポストに反齋藤的な職員を配置して、知事の改革を進めさせないというのは、これはある意味、クーデターというふうに解釈してよろしいんではないかと思っております。
○増山 誠委員
ありがとうございます。
続いて、齋藤知事は県政推進のため掲げる政策に理解の深い職員を抜てきして、改革ですとか、若者・Z世代の施策展開に当たってきたと思うんですが、しかしながら、これをもって側近グループによる偏った人事が行われているとの指摘もありますが、この点どのようにお考えでしょうか。
○証人(片山安孝)
やはり、県職員の中にも齋藤知事をよく思わない者がいる中で、やっぱり改革を進めるためには気心の知れた者を自分の周りに集めると、このことは必要じゃないかと思っております。そのために、知事は新県政改革推進室をつくられたんじゃないかと。そこで中心となって若者・Z世代の施策をするなりということを強力に進められたり、改革を進められたと思っております。
人事というものは、反対派から見たら恣意的なものとなるのは当然であると私は思ってます。知事が改革を進めようとして、それに対して、やり方に対応しなかったと、呼応しなかったというものは別のポストに異動する、そして頑張ってやってもらう者を主要ポストに異動するということになりますが、反対派から見たら、このことを人事による恐怖政治というふうなことを言っとるようでございますけれども、私からしてみたら、これは単なる人事異動と、このように思っております。
特に、県職員OBの方は非常に県政の批判をされてます。これは知事が、先ほども申しましたが、外郭団体の定年年齢をはっきりさせたと思うんですけれども、特に匿名でネットでは、私もよく知ってますけれども、県職員OBのS氏なんかは、非常に厳しく攻撃されてますし、また頻繁に統廃合が議論される外郭団体の理事をしている方も非常に知事の批判をされていると、こういうような状況でありますけれども、私が思いますのは、3年前の知事選挙と今回の知事選挙で、もう2回にわたって民意が示されておりますのに、まだ知事の攻撃をするというのはいかがなものかと、このように思っているところでございます。
○増山 誠委員
ありがとうございます。
先日の委員会において、TBSの報道特集及び村瀬健介キャスターの問題点というのを申し上げましたけれども、やはり百条委員会にもかなり影響を与えていると。ほかにも、めざまし8という番組において、立岩陽一郎氏は知事を人殺しであると断定し、それに副知事も加担していたと発言されております。キャスターの谷原章介氏も、それに同調するという放送が行われました。このような行為は報道倫理の欠落が著しく、まさに公共の財産であるテレビ放送に携わる資格のない者の発言であるというふうに考えておりますが、片山元副知事として、今回の文書問題における報道について、どう思われますでしょうか。
○証人(片山安孝)
やはり、知事や副知事が悪、こういう前提に立った報道ばっかりやと思ってます。ただ、私思いますのは、現場の記者たちと話したら、実態は一定ご理解いただいとうと、このように思うんですけども、実際の報道となると、あれっと思うような内容になってまして、現場と、やっぱり兵庫の地から遠く離れたところでオペレーションがされてるところとで、この差があるのではないかと思っております。
中でも、私、問題にしたいのは、今ご指摘がございましたけども、9月17日のフジテレビ、めざまし8ですね、知事や副知事が人を殺してしまったと、たしかそういう表現だったと思います。それにつきましては、私は私の弁護士にお願いしまして、BPOの人権委員会に提訴しているところでございます。
また、10月2日にNHKはクローズアップ現代というのを放送しました。NHKといえば公共放送ですから、受信料で成り立っておりますのに、出てくるインタビューは反齋藤派の県職員OB、反対派の県職員ばかりで、偏った報道、また公益通報者保護法については、何ら結論が出てないのに公益通報者保護法違反であると受け取れるような内容で放送してたと。このことについては、公共放送、受信料で成り立っているNHKということから問題ではないかと思います。
最後に、先ほども申し上げましたけども、10月25日の神戸新聞の朝刊ですね、信用金庫の理事長が2,000万円を片山副知事から言われたという、全く誤った報道がされてました。この報道を信用金庫の理事長は、全くそういうことは答弁してないということで、神戸新聞に抗議されたみたいですけれども、それはすぐに、11月のすぐに取材があったようですが、なぜか、そのインタビューが報道されましたのは、知事選挙の後です。これは意図的に齋藤知事に有利にならないような思惑が働いたのではないかというふうな疑いを持ってしまうようなものです。
事ほどさように、一定の報道については、私は理解できないところがあります。ただ、現場の記者さんたちは非常に理解いただいている方もいらっしゃることは念のため、付け加えさせていただきます。
○委員長(奥谷謙一)
時間が経過しているので、最後でいいですか。
○増山 誠委員
最後。文書の内容の真相究明に当たって、片山さんのほうで、我々の委員会に一度疑義を呈されたということで、要望書というのを出されてると思うんですけれども、これ一部委員が、本件告発文の作成に関与しているとの疑惑ということで、元県民局長のご家族から議会事務局宛てに7月12日金曜日に届いた資料を産経新聞が7月11日には知っていて報道しており、竹内委員も11日には記事を引用して自らのブログにおいて発信していることがネット上で確認できました。こういった状況がある以上、百条委員会としても調査の必要があるのではないかというふうに考えておりますが、これについて片山元副知事、何かご意見ありますでしょうか。
○証人(片山安孝)
大変申し訳なくて、委員の方、皆さん方、ここで顔を見ましたら、顔分かるんですけれども、私はこの場に疑惑があるということで出てきています。
特に7項目のうちの1番目、ひょうご震災記念21世紀研究機構につきましては、7月19日の本人の陳述書でも、本人が臆測ですって言ってるんですね。そこで、私は疑惑にもかかわらずここへ出てきてるのに、大変申し訳ないことを言いますけども、委員さんの中には疑惑を持たれてる方がいらっしゃいます。
例えば、奥谷委員長の場合は、公用パソコンの中に出てくる職員からこの騒動が始まる前に相談を受けてたと、こういうようなことも出てます。
公益通報委員会の7月末ぐらいに発表するということについて説明があったときに、百条委員会の自民党と維新の人に説明したけれども、自民党の委員から、今そんなものを公表するなと言われたというような話も伝わってますが、普通に考えて委員長と副委員長に説明に行きますよね、そしたら自民党というのは奥谷さんじゃないかなと。申し訳ないです、これ疑惑ですからね。私も疑惑言われてますから、疑惑を言わせていただくということで、疑惑、疑惑で申し訳ない。
じゃあ、疑惑じゃないことを言いましょう。疑惑じゃないことは、竹内さんは疑惑じゃなくて、ゆかたまつり、丸尾さんはスキーウェアのことですね、これは地元から全然違うということ、二つのことを言われてると。また、竹内さんについては、百条委員会の事前調査のときに、職員に圧力をかけたんだと、このことは私も報告を受けたところでありましたし、それから8月24日の秘密会の証言で知事が最高幹部に文具を投げたと。どうも最高幹部って私やったらしいんですけども、私に向かっては投げられてません、何も。そういうようなことを捏造してるってことです。
また、竹内さんについては、もっと火のないところに煙は立たないということですけども、非常に言われてますね、元西播磨県民局長の奥様のメールの作成に関与してたんじゃないかと。また、本人の陳述書の作成に関与してたんじゃないかと、こういうようなことが言われてますので、こういうようなことについて、ぜひ解明いただかなければいけないのではないかなというふうなことを思ってますし、また直前に本人と話をして圧力をかけたのではないかと、大変申し訳ない、長岡さん、ちょっと言われてるようなこともあるんですけれども。これは疑惑ですから、疑惑については申し訳ありません、疑惑ですが、私も疑惑を言われてますから、疑惑を言わせていただきました。
スタンダードを一緒にさせてもらったということですけれども、疑惑でないこともあります。なぜそのことを協議されないのか、そのことについて委員長にお願いしているということになりますので、疑惑のある方は、委員会の中では5人、それから委員会以外の方で5人というふうな形で、全部で10人ですが、私はその10人の中に1人入ってないなと思いますのは、6月10日の県議会で伊藤傑さんが質問されたときに、おまえ誰んとこへ頼みに行ったんやと、百条委員会やめてくれと、その人誰やっていうて言われまして、私は最後まで答えませんでしたが、伊藤傑さんが、この人やという名前を言ってます。6月10日の質疑応答の記録の中に出てます。私はその人も非常にいろいろと影響力ある方やと思うんで、私はその人のところに頭を下げに行ったということですので、名前は申し上げませんけども、そういうような状況です。
やっぱり、こういうような疑惑がある以上ですね、調査をしていただかなきゃいけないんじゃないかと、このことを申し上げたところでございます。すみません。
○委員長(奥谷謙一)
それでは、公明党さん。
〇伊藤勝正委員
今日はありがとうございます。私も片山さんでいいですか。
○証人(片山安孝)
はい、大丈夫です。
〇伊藤勝正委員
先ほどのやり取りの中で、信用保証協会のお二人にお願いをされて、注意してねと、あくまでボランティアでということを念押しされてお願いされたと思うんですが、この点、やっぱり、例えば、法律に抵触するんじゃないかとか、誤解を招くおそれがあるんじゃないかなっていう思いはおありでなかったんですか。
○証人(片山安孝)
申し訳ないですけど、もうそのときは何とかして集めなあかんし、手伝うてもらう人を集めるのがもう一苦労で、完全ボランティアやからって言うたときに、名簿がないんで、もうとにかく、よう知っとう者から順番にいきましたんで、申し訳ないけど、理事長はよう知っておりましたから、頼むわって行ったら、横にもう1人おったということで、2人頼んだと。
〇伊藤勝正委員
それはなかったいうことですね。
○証人(片山安孝)
その認識はしておりませんでした。
〇伊藤勝正委員
分かりました。先ほど、齋藤知事に近い方に批判的な表現とか、いろいろ公用パソコンに入ってたということが、ある意味クーデターという表現されましたけども、クーデターっていうと、要は、いつ、どこで、誰が、どのように実行するんかとかいうのが、前回の証言のときに計画があるとかいう話をされてたと思うんですが、ある意味というのは、どういう意味なんですか。
○証人(片山安孝)
前回、計画書というのは存在しませんって言うたような記憶あるんですけど、計画書というのはないけども、いろんな言葉で、クーデターや転覆やとか、片山を早く辞めさせろとか、そういう言葉がずっと並んでまして、そしてもう一つ資料がありますのは、資料の中、先ほどご紹介あったような、いろんなそんなことが書いてありますし、ある意味、知事をおとしめる資料だということで、知事は福祉に理解がないということで、福祉関係者へ配布したような資料が入ってたりとか、それから側近のA氏に対する誹謗中傷の紙をばらまいたと、そういう言葉と実際にやったことがあるので、それやってるのは要するに誹謗中傷して失脚させようということは、実行計画に移してるんですよということがある。
〇伊藤勝正委員
総称してクーデターと。
○証人(片山安孝)
そうそう、総称してという。
〇伊藤勝正委員
それで結構です。はい、分かりました。
3月21日の話なんですが、これについて急ぎ調べてくれ、徹底的に調べてくれと、知事から指示があったということを証言されてます。
私、ふとこの問題のときにいつも思うんですけど、一目見て、これ事実と異なる記述多いなっていうのが、どの幹部の方からもそういう表現されてるんです。一目見て、うそが多いなということを表現されてるんです。じゃあ、この記述で多くの内容が異なる、要は事実じゃないなって思われたんなら、これもう怪文書として扱いましょうよとかいう提案をどなたもされなかったんですか。特に、片山さんは。
○証人(片山安孝)
すみません、ちょっとね、それを伊藤県議言われるのは、もうよう分かります、今となってはね。けど、そのとき思うとったときには、もう二つのことですわ。一つは、要は県庁外の企業の名前がいっぱい出てきとったんですよ。これをやっぱり何とかせなあかんなと。このことが一つ目。
二つ目は、これ9月6日にも言うたん違うかと思いますけども、最初に私のとこに来とったら、くしゃっとしとったのに、最初に来たのが知事のとこへ来てましたやろ、副知事マターやったらもうどないでもしときますわ。しかも、後から、後からというのはちょっと訂正しましょうかね。すぐに西播磨県民局長やと分かりましたからね。この二つです。
〇伊藤勝正委員
分かりました。
その最初の協議で、作成者の候補っていうのは、一番最初の協議のときに上がってたんですか。今おっしゃいましたけども、元県民局長ということは。
○証人(片山安孝)
もう私の部下ですからね。
〇伊藤勝正委員
分かったっていうことですか。
○証人(片山安孝)
分かりますわ。
〇伊藤勝正委員
分かりました。
それから、22日に指示した、要は文書作成に関与したと思われる職員のメール履歴を調査っていうことで指示されてますが、この調査をそもそも発案されたのはどなたなんですか。
○証人(片山安孝)
ちょっとはっきりは覚えてませんけども、集まっとったので人事当局が言うたのかもしれませんし、メールでやり取りしてる可能性がありますねって誰かが言うたんで、発案はちょっと分かりませんが、最終決定したのは私やいうことは認めます。やろうかというのは。ただ、発案はちょっとその場で誰が言うたかは覚えてませんけども、それをまずやってみなあかんな、すぐにと言うたのは間違いありません。
〇伊藤勝正委員
分かりました。
あと、退職保留のことについてお伺いします。職員局長に定年延長になるから、必ず3月末で退職する必要はないんだろうということを確認されたようですけど、これは事実ですか。
○証人(片山安孝)
制度的にどないなっとんやったかなと、念のため、大体制度は分かってましたけど、念のため確認して、要は退職させなかったらどうなるかっていうと、3月31日までは役付、管理職の役付におって、管理職の場合は自動的にそこから外れて、どう言うんですか、別の役付後の職に就くということが制度的になっているということですから、それが自動的に適用になるんだということの確認をした覚えがあります。
〇伊藤勝正委員
それを基に退職保留を知事に進言されて、了承されたというのは事実ですか。
○証人(片山安孝)
はい、しました。
〇伊藤勝正委員
最後に、公用パソコンの私的情報についてですけども、9月6日の証言では、300ページぐらいのものを全部シュレッダーした覚えがあると。覚えがあるとおっしゃってた。
○証人(片山安孝)
覚えがありますけど、もうしました。
○伊藤勝正委員
したんですか。
○証人(片山安孝)
しました。かなり早い時期やったと思います。
〇伊藤勝正委員
ただ、10月25日には、かなり詳細に証言をされようとしてた、何か資料を見ながら、とうとうとしゃべられようとしてたんですけども、ああいうのはどうなんでしょう、手元になかったらできないのかなと思うんですけど。
○証人(片山安孝)
概要だけになってますし、あのとき慎重に話しよったのは弁護士と非常にセンシティブやから、どういうふうにして言うかについては厳格に、限定してしゃべってましたので、個人名が特定できないように。だから慎重にしゃべってたと。ご指摘で言うたら、いつもと違うやないかということを指摘されとんかと思いますけど、弁護士からも、やっぱりここは一番慎重にやってくれということを言われてましたので、見たような感じになってましたけども、当時を思い出してですが。
〇伊藤勝正委員
シュレッダーされたんは間違いないですか。
○証人(片山安孝)
間違いないです。
〇伊藤勝正委員
分かりました。
〇越田浩矢委員
不正な目的に関してお伺いをさせていただきます。文書の目的は不正な目的だという証言を9月6日に片山元副知事されました。一方で、齋藤知事は3月27日の会見以降、一度も不正な目的に関する言及というのは一切なかったです。9月6日、片山元副知事が証言されて以降、ちらっと不正な目的がみたいな発言を齋藤知事もされるようになったなというふうに認識しておるんですけれども、この不正な目的について、知事とか人事当局とどのようなやり取り、検証を行っていたのかっていうことをちょっと教えていただけますか。
○証人(片山安孝)
知事とすごい議論をしたということはありませんけれども、要は公益通報者保護法の前提となる一番入り口のところで不正な目的ということになったら、対象とならないなということは言ったような記憶はありますけども、それはさらっといってしまいまして、知事はそれよりも、法的に詰めた議論は必要であると思うので、真実相当性のほうをきっちり詰めなければいけないと言われたような記憶はありますけれども、不正な目的に認識してないようなことはないと思います。
人事課にも確認したのは、不正な目的があった場合は対象にならないというふうに私からも言いましたし、彼らもその認識は十分あったと思いますけれども、要は不正な目的ということになりました場合には、個々のことにはもう入らないということになりますので、人事当局は個々の調査をやってましたので、個々の調査からいきますと、真実相当性、真実がどうかということを議論して確定させたいという思いがあったんじゃないかと思いますので、認識がなかったいうようなことはないと思います。
〇越田浩矢委員
一応、人事当局、百条委員会に来て証言されている証言としては、不正な目的であったというふうに明確に内部で判断したということはないですと。明確に言ってます。
そういうことからすると、片山元副知事は退職の日まで不正な目的を確信しているような証言を前回もされてると思うんですけれども、そこの辺の認識が一致してないのはなぜですか。
○証人(片山安孝)
ちょっと、そこのところは分かりませんけど、私はこれはもう不正な目的やというのを、公用パソコンの中に何が入ってるかも分かっておりましたから、そういうふうに思っておりましたので、その認識は十分持ってたと思ってるところです。
だから、彼らがどういうふうに言ってるというのは、彼らはとにかく知事から厳しく、個別の調査をきっちり押さえてやりなさいっていうことを指示されてたと思いますので、個別のことイコール真実相当性ということで議論をしてたんじゃないかと思います。
〇越田浩矢委員
先ほども参考人の聴取もありましたし、藤原弁護士の証言としても、不正の目的っていうことに関しては簡単ではないというふうに藤原弁護士もアドバイスをしているようでして、不正の目的があったかどうかを立証する裏づけがないので、不正な目的があったかどうか分からないという意見を明確に人事当局にも法的アドバイスをされてるんですね。
先ほどの参考人の話としても、専ら不正な目的がっていうことで、主たる目的が不正であったとしても、それ以外の目的があれば不正ではないんだというふうな見解を示されておりました。
ということは、人事当局も認識しているのは後輩のためだと元県民局長はおっしゃっているので、そういうことも含めて、不正な目的だけではないということからすると、公益通報に該当しない不正な目的に当たらないというような証言があるんですけれども、そのことに関しては、もともと公益通報の委員をやられてる片山元副知事としては、どのように認識されてるでしょうか。
○証人(片山安孝)
私は公益通報委員会の委員してましたから、不正な目的だとまず第一番目にはねられることは十分認識しておりましたので、そこが不正な目的があるということで、これはもう問題外だというふうな認識をしておりました。今の午前中の議論の中でも、やっぱり専らという議論があったかというふうなことは伺っておるところではありますけれども、やはり公用パソコンの議論をした場合にはまず不正な目的ということにはなるんだろうということで、やはり公用パソコンの議論をあんまり今までしてなかった。今回、委員の皆様方ご覧になったと思いますので、それをどう評価するかということが出てくると思います。
越田委員の質問の際で、ちょっと一つだけ今話させてもうていいですか。今日の午前中の参考人の質疑の中で、公益通報者保護法第11条第2項の体制整備等について、外部通報にも適用があるかということが議論になるということをおっしゃってまして、今日、参考人は的確にご説明されて、消費者庁の解説書によれば対象になるとなっとんですが、ちょっとこの点、私のほうから疑義だけを申し上げておきますと、公益通報者保護法第11条第2項には、明文で、1号通報ですね、つまり内部通報だけに該当するというふうに明文規定がございます。もしよろしければ、後で法的アドバイザーに確認いただいたらいいと思うんですけど、公益通報者保護法第11条第2項にははっきりと明文規定があります。そして、その規定について、ある解説書、この解説書なんですけど、改正公益通報者保護法の解説書によりますと、法第11条第2項は外部通報に適用にならないということが書いてありまして、この解説書の筆者は消費者庁のいろんな検討委員会の座長をされている先生がやっておられます。執筆は消費者庁のそのような検討会に深くかかわっておられる弁護士さんです。
青字の部分は、公式議事録では以下のように修正されています。
ある解説書に法第11条第2項は、外部通報に適用にならないと読めることが書いてありました。
この本の執筆者からの抗議を受けての修正ですが、片山元副知事の発言通り、この本には「第11条第2項は内部通報に限定される」と書かれた個所があります。抗議内容や、解説書の記述に関する詳細は、「公益通報者の探索は外部通報も禁止か」のページ参照。
ということは、意見が分かれとんですね。ただ、その解説は消費者庁がそういうふうに出してきてるということでありまして、これ非常に疑義があるんで、今もしかしたら放送されてると思いますので、ここのところを詳しい専門家の弁護士の先生方か、専門家の方が、この法律の文理解釈をしたらどっちが妥当なのかということを検討いただいたらということを希望しておきます。
〇越田浩矢委員
今の点は百条委員会から消費者庁に問い合わせしている質問の項目にもたしか入ってたと思うんですけれども、その上で回答としては句読点の取り方によって、今のような解釈が成り立つんではないかという疑義も含めて質問してますけれども、含まれるんだという回答を消費者庁から明確に得てますので。
○証人(片山安孝)
得てるんですか。ということは、やや不安になるんですけども、この本に書いてあるこの執筆者は消費者庁の専門委員会の座長さんがまとめた本なんですね。非常にこれやっぱり差があるんじゃないかということと、後ほど、時間がないからいいですけれど、法的アドバイザーに、公益通報者保護法第11条第2項を確認いただいたら、明文規定があるのに、なぜ通知になった段階で明文規定に反するような内容になるかということが、文理解釈からして私ちょっと分かりにくいということを申し上げております。ちょっとこれは委員ご指摘の、11月に消費者庁からの回答も見ておりますので、そういうふうにないというんですけど、ただそれを見ても、なおかつちょっと、えっと思って調べたら、ちゃんと文献には違うと思われる意見も書いてあったと、こういうようなことでございます。失礼しました。
青字の部分は、上記と同様の理由で、公式議事録では以下のように修正されています。
ということは、やや不安になるんですけども、
○委員長(奥谷謙一)
それでは、県民連合、上野委員。
○上野英一委員
同じく公明党の伊藤委員、あるいは越田委員の関連みたいになるんですが、9月6日に藤田議員の尋問に対して、片山さんは非常にその取扱を厳格に、人事課も含めてね、個人情報の取扱はやらなあかんということを明確に言われまして、さすが私元副知事だなというふうに、個人情報保護には厳しい認識をお持ちやなというふうにそのとき感じたんですが、それがなぜ10月25日の尋問では、奥谷委員長が制止しようとしてるにもかかわらず、私的プライバシーまで話そうとされたんですか。
○証人(片山安孝)
あれは私的プライバシーを話したのではなくて、公用パソコンの中にある文書が何であるかということを説明しようということをしているわけです。だから、プライバシーのことを話しているというんじゃなくて、公用パソコン中に何があるか、つまり何かというと、本人の懲戒処分について、この委員会では問題にされておりますから、懲戒処分の理由を説明しているということで必要になるということでやってます。
○委員長(奥谷謙一)
そこちょっと勘違いがあるかと思うんですけど、我々の委員会、その懲戒処分の妥当性とか、そこは審査外なんですよ。
○証人(片山安孝)
審査外ですか。懲戒処分は争わない。
○委員長(奥谷謙一)
処分までの手続を。
○証人(片山安孝)
処分はもう争わないということで、大変失礼しました。処分はもう争わないということで
すね。それは勘違いしてました。
○委員長(奥谷謙一)
そこは、だって僕ら処分に関しては当事者しか。
○証人(片山安孝)
処分はもう争わないということですね。大変申し訳ありません。そやけど、何で処分の事前の経緯。
○委員長(奥谷謙一)
じゃあ、上野委員、質問を続けてもらって。すみません。
○上野英一委員
それでね、最初はそういうふうに厳密にそういう取扱されとると思うたのに、あのときは突然に、少し興奮されておっしゃいましたので。
○証人(片山安孝)
別に興奮はしておりませんよ、普通にしゃべってましたよ。
○上野英一委員
ちょっと私は意外やったんでお聞きをいたしました。
その次に、先ほどシュレッダーにかけられたということなんですが、ちょっと、さっきの答弁の中でも何かあるんかなというような感じがしたんですが、いわゆるファイル名の一覧ですね、タイムスタンプの載った、あれは手元に持ってらっしゃるんですか。
○証人(片山安孝)
持っていません。あの一覧表は持ってません。
○上野英一委員
いうのは結構な文書内容やと思うんで。
○証人(片山安孝)
下の打ち出しのほうの個表が来ましたんで、あんな、今、外部に出ているようなものを見ましたけれども、あのようなものについては私はそのものの写しをもらったようなことはなくて、ただ画面は見たかどうかって言いましたら、公用パソコンを回収して帰る車の中で、人事課の職員と一緒にこんなんがありますって見たんで、あの画面は画面でしか見てませんので、打ち出したものを持ってません。画面では見ました。
○上野英一委員
なるほど。
それで、300ページにわたる内容のものをね、シュレッダーされて、それから随分経過しとうと思うんやけども、かなり内容を詳しく今ももう話されて。
○証人(片山安孝)
詳しく言うたって、25日もA、B、Cの3項目しかしゃべってないですよ。言えませんから言いませんけれども。
だから、それ以上の詳しいこと何も言ってませんので、詳しく言われているというのはどういうことでしょうか。何も手元に資料ないですから、A、B、Cとこの三つしか言ってないんで。
○上野英一委員
いずれにしても、いろんなネットで出てるところにあったんで、私はそのファイル名の一覧表ぐらいは持ってらっしゃるんかなという思いがあったので、お聞きいたしました。そしたら、それはもうそれで結構です。
そしたら、次に、いわゆる中小企業経営改善・成長力強化支援事業補助金のことでちょっとお尋ねします。
これ、片山さんの証言も、ほかの方の証言も踏まえて、私なりにこれ取りまとめをしたんですが、それで間違いないかちょっと聞いていただきたいと思います。
11月21日にT信用金庫の理事長を訪ねて寄附の依頼をされました。理事長は依頼に応えて信用金庫11社で総額2,000万円の寄附をすることを、翌22日に11社の寄附額一覧表をファクスされてます。寄附額は50万円、100万円、200万円、300万円の4ランクに分けられ、それは補助金受給額の4ランクとも一致してます。その根拠になった資料については、片山さんから産業労働部長に指示か依頼があって、部長は金融室で一覧表を取得して信用金庫に提供されています。時を同じくして、11月16日に財務部から産業労働部に対してソフトランディングということではなく、事業再設計の必要があると指示がなされ、結果、11月21日に知事査定も含めて1億円から4億円に予算は増額されました。
この事実認定、認識として合ってますか。
○証人(片山安孝)
はい。ただ、いつもこの議論のときに4億円から1億円だけが独り歩きしてるんですけども、信用金庫の理事長も、神戸新聞の報道で言っておられましたけども、初年度12億円、2年度8億円、3年度4億円、その4億円の要求過程で、最初は1億円で、財源が確保できひんからどうやっていうけど、8億円から1億円にするのは何ぼ何でも減らし過ぎやろ、財源が確保されたら4億円という、12億円、8億円、4億円が抜けていると、このことは信金の理事長さんもおっしゃっておられましたし、私もそういうふうに思います。1億円を4億円にしたから、これはおかしいやないかという議論が独り歩きしてますが、その点が抜けてますけども、それ以外は上野委員のまとめで大体、ちょっと日にちが、ちょっと今すぐに確認できませんけども。
○上野英一委員
それはもう日にちは合ってますから間違いないし。私途中で言いましたけど、財務部から産業労働部に対して指示があったときには、ソフトランディングということは一切なかったということで、要は事業再設計せえということで3億7,500万円かいう数字を出した。それで、それに対して知事が切りのええとこで4億円にせえというふうになったというふうに伺ってます。
それで、それをなぜキックバックと言うんかというようなことになると思うんですが、私は元県民局長からしたら、信用金庫から県にということではなくって、県から信用金庫に対して補助金の増額という形でのキックバックというふうに元県民局長は述べられたんかなというふうに感じたわけですが、いかがでしょうか。
○証人(片山安孝)
ちょっと質問の趣旨がよく分からなかったんですけども。
○委員長(奥谷謙一)
もう一度、上野委員、ちょっと質問短くしてもうたほうがええかも。
○証人(片山安孝)
どういう理解かっていうのがちょっと。
○上野英一委員
いわゆるキックバックという言葉を元県民局長は使われてますよね。告発文書の中でね。
○証人(片山安孝)
それは分かります。それはいいです。
○上野英一委員
それで、それを私なりに解釈をしたら、信用金庫から県にキックバックしたんではなくて、県から補助金という、増額という形で金融機関に対してキックバックされたというふうな表現かなというふうに思うんですが、それはどうお感じになりますか。
○証人(片山安孝)
それは西播磨県民局長が考えたんですから、私らはそんな認識、全く両者に関係がないと言ってますから、それがどうかと言われてもお答えはできませんけど。
○上野英一委員
分かりました。結構です。
以上です。
○証人(片山安孝)
ちょっと、上野先生に、顔見て思い出したんですけど。
○委員長(奥谷謙一)
聞かれた質問にお答えしてください。
○証人(片山安孝)
ゴルフクラブね、もらった時期間違うてまして、すみませんでした。
○上野英一委員
2回。
○証人(片山安孝)
2回もらってません、1回だけ。
○上野英一委員
産業労働部長のときと、副知事のときと2回あるでしょう。
○証人(片山安孝)
違いますよ。2回もらってない。副知事のときに1回だけ。産業労働部のときはもらって
ません。家帰って見たら、4本ないとあかんでしょう。
○上野英一委員
専務理事がAWとSWを。
○証人(片山安孝)
2本。2本だけですよ。
○上野英一委員
それでも、あのとき部長は産業労働部長時代に、○○のやつをもらってる。
○証人(片山安孝)
もらってないです。
あの質問、後でちょっと怒られました。2本もらった言うて、時期違うやないかと言われて、すみません、失礼しました。
〇委員長(奥谷謙一)
北上委員、質問お願いします。
○北上あきひと委員
3月21日の知事から徹底的に調べてくれという指示がありました。その内容について、証言者によって受け止めが異なるんですが、文書内容について調べてくれということなのか、誰が何の目的で文書を作成したのか、そのことを徹底的に調べろということなのか、片山さんの受け止めをお聞きします。
○証人(片山安孝)
それはもう広くやと思いましたので、とにかくその場では知事にも確認もしてないので、広く調べないかんなと思ってましたし、当然そのときに誰がやったんやろうなということは議論にすぐなりましたから、それも含まれておったんではないかと思っております。
○北上あきひと委員
片山さん自身、告発文書で疑惑の対象であります。その片山さんが知事の指示に基づいて、西播磨県民局長のパソコンを押収したということについては、ふさわしかったとお考えですか。
○証人(片山安孝)
押収したという認識はありません。県の公用物を回収したという認識があります。以上です。
○北上あきひと委員
聞き取り調査等をされておりますが、それにふさわしかったとお考えですか。
○証人(片山安孝)
聞き取り調査は、一部メディアが非常に厳しい発言のところを取り上げて、あれはひど過ぎるということですが、この会場の中にも、播州の浜手の県会議員さんがいらっしゃると思いますが、播州弁では。
○北上あきひと委員
ちょっと待ってください。調査の内容についてお聞きしてるんではなくて、片山さん自身
が疑惑を持たれているにもかかわらず。
○証人(片山安孝)
問題はないと思っております。
○北上あきひと委員
調査を行った主体だったということは問題ないとお考えですか。
○証人(片山安孝)
はい。
○北上あきひと委員
これまで公用パソコンを持ち帰って調査をしたという例は、このこと以外にありますか。
○証人(片山安孝)
私の記憶ではありません。
○北上あきひと委員
この間の百条委員会の調査の中で、パワハラについてですが、社会通念上必要な指導の範囲を超えた叱責があったというような証言もありました。知事自身も非常に強い調子での叱責をしたということを認めておられます。片山さん自身も9月6日の尋問の際に、私は付箋を投げられたのは事実ですし、厳しく叱責するということは間違いなくあると証言されていますが、これらのことを合わせると、告発文書でのパワハラの指摘、これは事実無根、うそ八百ではなく、真実相当性が含まれるというふうな認識に至ると思うんですが、そのことについてはいかがですか。
○証人(片山安孝)
パワハラと認識していません。
○北上あきひと委員
4月以降、知事が退任されるまでに、県庁内で片山副知事が文書問題をめぐって大逆転をするというような発言をされたということを私聞き及んでいます。この大逆転というのはどういう意味なのか、何をテコにして、どういうことを目指されていたのか、意図した発言だったのかお伺いします。
○証人(片山安孝)
言った記憶はございません。
○北上あきひと委員
私は今週初めに、片山副知事から直接お聞きしたという方から大逆転をしたというふうにおっしゃっていたということでありますが、どなたにもそういう発言されておりませんか。
○証人(片山安孝)
記憶にございません。
○北上あきひと委員
最後お聞きします。片山さんが調査されたパソコンの中から個人情報が含まれていました。その個人情報の取扱について、井ノ本さん及び職員に何らかの相談をされた、指示をされたということはありますか。
○証人(片山安孝)
質問を確認しますが、どういう指示を指していらっしゃいますか。
○北上あきひと委員
個人情報の取扱については、公務員の守秘義務があるので絶対漏らしてはならないとか、このことを理由にして告発者に対して圧力をかけてはならないとか、そのようなことを含めて、何らかの指示や、あるいはどう取り扱うかということについて相談された事実はありますか。
○証人(片山安孝)
そのようなことをするとは思っていませんので、そういうような話をした記憶はありません。
○北上あきひと委員
私が申し上げた事柄以外にも、この個人情報をめぐって、何らかの相談や指示をされたことはありますか。
○証人(片山安孝)
記憶はありません。
○委員長(奥谷謙一)
北上委員、そろそろまとめてください。
○北上あきひと委員
最後、4月4日付の公益通報事案について、本県公益通報委員会は、県に対してハラスメント研修の充実や贈答品受領のルールの明確化等の是正措置を講じるように県に求めています。今問題にしている3月の告発文書と、4月4日付の公益通報の事案の内容はほぼ同じであります。よって、この不正の目的云々という片山さんの認識は私は間違っているのではないかと思いますが、ご所見をお伺いします。
○証人(片山安孝)
4月4日の公益通報にどのようなものが出されてきたかは、認識ありません。知りません。
○委員長(奥谷謙一)
それでは、共産党、庄本委員。
○庄本えつこ委員
先ほどの越田委員の質問の中で、公益通報として扱うのは不正の目的ではなくっていうことを認識していたっていうふうにおっしゃったんですけど、おっしゃいましたよね。
○証人(片山安孝)
はい、私はでしょう。私は不正だと思ってますよ、最初から。
○庄本えつこ委員
ということは、9月6日のときに私の質問に対して公益通報という認識は全くなかったっていうふうな答弁されてるんですけど。
○証人(片山安孝)
だから、不正な目的だから公益通報ではないというふうに答弁したつもりやったんですけど。公益通報の入り口は不正な目的であれば、公益通報としては対象としないという認識になってますので、公益通報ではないと、このように答弁したつもりやったんですけども、何か疑問ありましたでしょうか。
○庄本えつこ委員
私たち、今日も午前中勉強しましたけれども、一つ一つの事実を確認した上で、ちゃんとやらなくちゃいけないっていうのに、入り口で公益通報として扱わなかったその責任があると思いますが、いかがですか。
○証人(片山安孝)
そのときは、メールを全体を確認しておりますし、また、その25日以降になりますけれども、公用パソコン内の状況を確認しておりますので、動機、目的を確認した上で、動機、目的の面から全体としてどうかという判断をしたものであります。
○庄本えつこ委員
全体としてではなく、一つ一つの事実を確認するということが必要だったと考えます。
それから、4日に職員の公益通報事案として受理していますよね、兵庫県は。その時点で人事課の調査を止めるべきだったと考えますけれども、なぜ止めなかったんですか。
○証人(片山安孝)
3月のときの取扱と4月4日以降の取扱は明確に区分して対応していると思います。
そして、懲戒処分等の対応につきましては、4月4日のことについては何ら対応せずに、また4月4日以降のことについては私は一切関与しておりません。
また、県の顧問弁護士と相談した上で4月3日までの間、というより、3月の文書といいましょうか、3月のことについて懲戒処分の対象として、また懲戒処分は何度も説明を申し上げていると思いますが、この文書だけではなくて、ほかの3つの非違行為ももって、合わせて処理をしていると、こういうような形になってきております。
○庄本えつこ委員
今、処分の話ではなく、人事課の調査をなぜ公益通報として受理したのに止めなかったの
かという質問でした。
ちょっと確認なんですけど、別の話です。優勝パレードについてなんですけど、中小企業
経営改善・成長力強化支援事業の、これは1億円から4億円に増額すべきじゃないかってい
うのをおっしゃったのは、日付は16日でしたか。
○証人(片山安孝)
ちょっと日付、確実な日は財政課が来て、財源が確保できたと言ったので、そのときに、それやったら増やしたほうがいいなというようなことを言ったと思いますので、それがいつやったか、ちょっとはっきりした日付は覚えてませんが、まあ、11月の中頃の予算査定のさなかやったと思います。
○庄本えつこ委員
1億でもって言ったのを、片山副知事が4億円にしたほうがいいんじゃないか、3億7,000万円にしたほうがいいって、片山さんがおっしゃったと。
○証人(片山安孝)
私が言いましたよ。だから、その前に財政課に財源確保できたんかって聞いたら、財源確保できました。ほんなら幾つまでいける言うたら、4億まで行けますと言うから、積算してみいと言いましたので、積算したら3億7,500万円になったと、これだけです。
○庄本えつこ委員
いや、それはちょっと話が。
○委員長(奥谷謙一)
すみません、そろそろまとめてください。
○庄本えつこ委員
はい、すみません、ごめんなさい。
それでは、私も本当に疑問に思っているのは、政治資金パーティーのボランティアっていうふうにおっしゃいましたけど、私も県会議員として、どんなに親しくやってねって言っても、やっぱり県会議員として見られるってことがありまして、すごく気をつけるんですけれども、やはり協賛金を得る信用保証協会の名刺を使用したということ、元理事長自身などは反省してるんですけれども、やはり、結局肩書を持ってる方が名簿だけを取りに行くっていうのは大変不自然だと思うんですけど、これは依頼した片山さんにも大きな責任があると考えますがいかがですか。
○証人(片山安孝)
もうそれは、依頼したのは私ですから。彼らは取りに行ったんですから、彼らは取りに行ったことだけを頼んだんですから。私が頼んだという事実は間違いありませんので、後から、ちょっと一番最初の何か質問のときに、たしかこどもの使い違うんかいって言われましたけど、結果的にはこどもの使いになってたかもしれませんけども、私が電話でなり、会ったときに全部根回しをしたのは事実やと思ってます。
○庄本えつこ委員
すみません、最後に1個だけ。
その政治資金パーティーの当日のことなんですけど、県の職員のOBの方々は公職選挙法に引っかかるかもしれないということで、お手伝いするのはちょっとやめておこうということで、お一人だけお手伝いに来られたっていう証言があるんです、私たちの調査の中で。ということは、やはりそのことを認識すべきだったと考えます。
○証人(片山安孝)
公職選挙法に触れるからやめとこうではなくて、知事は政経パーティー当日は事務所のほうが手配した者で対応するから、皆さん方は名簿集めを手伝ってもらったので必要ありませんと。ただ、受付の際に名簿の関係でトラブルがあったら困るので、何人かだけは来ておいてもらえませんかと、ごく少数の者だけ来てて、もう始まったらみんな帰ったような記憶がありますので、公職選挙法に触れるからというようなことで言った記憶は私はございません。現にどこが公職選挙法に触れるんですか。
○委員長(奥谷謙一)
ちょっと、すみません時間が経過してますが。
丸尾委員、質問。
○丸尾まき委員
先ほど名前出ましたけど、疑惑の捏造は一切してませんということで、先お伝えしておきます。
ちょっと、いろいろ飛びます。3月21日、最初に集まった会合で、コーヒーメーカーの返却を原田部長がし忘れていたと。知事から返却するよう指示を受けていたということで言われてました。
片山さんは、齋藤知事が早く返すように言ったよねと産業労働部長に対して返却をするよう指示したことは覚えておられますか。
○証人(片山安孝)
その3月21日だったかどうか覚えてませんけども、それはもう返さなあかんような物やったやないかというふうなことは会話したような記憶はあります。日にちはいつやったかどうかはよく覚えておりません。
○丸尾まき委員
了解です。産業労働部長、元県民生活部長がその知事の発言を覚えておられるということで、それはお伝えだけです。
それと3月25日の調査ですが、片山副知事、元総務部長が入られましたが、お二人が入られたというのは、それは知事の指示があったのか、あるいは副知事の判断。
○証人(片山安孝)
日にち何日。
○丸尾まき委員
3月25日、一番初めのパソコンを取りに行った日ですね。
○証人(片山安孝)
あんまり覚えてません。
○丸尾まき委員
あとUSBについてということです。報道では、県職員OBが県民局長からUSBも含め
て全部持っていかれたとの証言が出ていますが、片山氏あるいは人事課はUSBは持ってい
かなかったということで言われてますが、それは事実ですよね。
○証人(片山安孝)
そのとおりです。
それ、私の音源がね、何か漏れてて、それ聞いてもうたら、「USB抜いて、USBを置いて帰るな」って言ってますから。
○丸尾まき委員
そこも聞きました。
○証人(片山安孝)
はっきりしてるんじゃないですか。何でそんなことが。あの音源が漏れとるのもおかしいんですけどね。
○丸尾まき委員
USBのデータが、そのパソコンの中に入ってたんじゃないですか。それも含めて、情報は県として取ったということじゃないですか。
○証人(片山安孝)
だからUSBを抜いてね、それ私物やろうと確認しましたら、私物やと本人言うた記憶があります。だから、それは私物やったら抜けよということで。彼のパソコンはたしか県庁の最新型はUSBは挿せないですけども、地方のやつは挿せますから、挿しとったんで、抜けと。そのパソコンを持って帰るわなと、持って帰っただけですから、そのパソコンにどうしたや、こうしたやと、その場では何も。
○丸尾まき委員
その中身を把握されてないということ。
○証人(片山安孝)
してないですよ。だから、パソコンを持って帰るよと言ったんです。
○丸尾まき委員
こちらの聞き取りで、そのUSBのデータはパソコンに入ってたっていうことなんですよ。それも含めて県の職員のパソコンに移したということで聞いてるんですが。
○証人(片山安孝)
USBのデータがパソコンに入っとった。だって、その場で抜いて、パソコンだけ持って
帰ってきただけですから。
○丸尾まき委員
そのUSBのデータをパソコンに入れてそこで作業していた。
○委員長(奥谷謙一)
質問して、お答えがあってですので、ちょっとかぶらないように。
○丸尾まき委員
USBのデータはパソコンに県民局長が入れて、そこで作業してたのを。
○証人(片山安孝)
県民局長が入れてね、それ知りません。
○丸尾まき委員
そのデータを県として持っていったっていうことなんですよ。
○証人(片山安孝)
USBから入れとったか、知りません、私は。
○丸尾まき委員
ご存じないということですね。
○証人(片山安孝)
パソコンを持って帰っただけです。
○丸尾まき委員
それと、データはだからそこへ入ってたんですよ。
○証人(片山安孝)
入っとったかどうか知りませんがな。パソコンを持って帰ったんですやん。
○丸尾まき委員
7月30日に、県民局長の代理人から7月30日にPCに入ってたデータを31日までに廃棄してほしいとの趣旨の文書が届いたんですが、そのことはご存じですか。
○証人(片山安孝)
それはよく存じております。でも、今の話だったら、USBに同じものが入っとったんですか。そしたら、もう漏えいがいろいろしとういうたら。
○丸尾まき委員
ごめんなさい、時間がないんで。
片山さんが紙でもらった県民局長の個人情報は他の方には見せてないですね。
○証人(片山安孝)
一切見せてませんよ。
○丸尾まき委員
産業労働部長に、その情報をお伝えしたということで聞いてますが、口頭での報告です
か。
○証人(片山安孝)
口頭です。
○丸尾まき委員
あとは、片山さんが県民局長の個人情報をデータで所持したことはない。
○証人(片山安孝)
ないです。
○丸尾まき委員
ないですね。
前回の百条委員会ですか、のときに音声データが流出したということでしたが、そのことで何かご存じのことはありますか。
○証人(片山安孝)
何の音声データですか。
○丸尾まき委員
片山さんがしゃべった内容が、データが外へ出たということについては、何か知ってることはありますか。
○証人(片山安孝)
何も知りません。
○丸尾まき委員
知りませんね。あと、優勝パレードのこと、ちょっと二、三だけお聞かせください。
片山さんは4金融機関に連絡を入れてます。1社は寄附を断られたんですが、他はいずれも寄附をしているということですが、3社とのやり取りで補助金の話をしたことはありませんか。
○証人(片山安孝)
一切ありません。
○丸尾まき委員
4社に寄附要請した後に、お礼を兼ねて12月だとか、あるいは1月だとか、金融機関に個
別に連絡を入れて補助金の話をしたこともないですね。
○証人(片山安孝)
ないです。
○丸尾まき委員
ないですね。あと、これも報道特集です。副知事から寄附金が足りてないのだが、赤字を出すわけにはいかない、寄附できないか、補助金はしっかり出しますんでというふうに言われたそうだというような報道もあるんですが、これ何か、似たような話をしたなど、そんな記憶はありますか。
○証人(片山安孝)
そもそも、その報道は言われたそうだですから、伝聞ですよね。
○丸尾まき委員
はい、伝聞ですね。
○証人(片山安孝)
この百条委員会はその伝聞が多過ぎるんじゃないですか。特に丸尾さんは伝聞を優先するという傾向があるんじゃないですか。
○丸尾まき委員
結構です。
あと、4月19日の弁護士相談で人事課から類型の異なる複数の非違行為が認められた場合、各非違行為に関する処分の量定を活用することに加えて、最終的な処分量定を加重することに法的な問題はないかというふうに質問がされて、弁護士は停職6ヵ月はさすがに重いなと、懲戒3ヵ月でも問題ないのではということで弁護士から停職処分の話が最初に出てきてるんですが、この辺のやり取りについてはご存じですか。
○証人(片山安孝)
委員長、懲戒処分については問題にしないという発言があったのですが、今、懲戒処分の話。
○丸尾まき委員
中身じゃない。
○委員長(奥谷謙一)
もう一回質問お願いします。
すみません、ちょっと時間経過してるので、もうまとめてください。
○丸尾まき委員
それは中身の話じゃないです。中身の話じゃなくて、経過として、その懲戒処分をすることが前提として物事が進んでたんじゃないかなということでの弁護士の提案がそのまま通っていったんじゃないかというのが、その辺はご存じですかということ。
○証人(片山安孝)
記憶ございません。
○丸尾まき委員
以上です。
〇委員長(奥谷謙一)
はい、最後、藤田委員。
それで終わります。時間が経過しているので。
○藤田孝夫委員
端的に答えていただいたら助かります。
初回の尋問で片山さんは、当該文書は西播磨県民局長が一人で書いたもんだっていうことが言われました。それを証言されています。そして、最初の調査のときに、なぜか前副知事の名前が出たことに対して申し訳なかったと。その方に陳謝したというようなこともおっしゃいました。
○証人(片山安孝)
陳謝しなきゃいけない事態になるかもしれないなと言ったような記憶があるんですけども、陳謝したという過去形は言ってません。
○藤田孝夫委員
とにかく、申し訳なかったという意味のことをおっしゃいました。
○証人(片山安孝)
その名前を軽々しく出したのは申し訳なかったという意味でしたね。
○藤田孝夫委員
僕は一旦それで終息してたと思ったんですけども、10月25日の百条委員会で維新の委員の方の説明から始まって、大演説が始まったわけです。今回もそのことが起こったわけですけれども、ここからが質問です。11月18日の午前中、維新の会の控室に行かれたという情報があるんですけれども、片山さんは維新の会の控室に行かれましたか。
○証人(片山安孝)
11月何日ですか。
○藤田孝夫委員
11月18日です。
○証人(片山安孝)
もしかしたらあれですね、要望書を持って行ったかもしれません。理事会で配ってほしいということを言いました。
○藤田孝夫委員
そういう意味ですか。それで、どなたとお会いになったんですか。
○証人(片山安孝)
名前は控えますけども、維新の県会議員の方にお会いして、各理事に渡るような方策を考えてほしいということをお願いしただけです。
○藤田孝夫委員
その要望書というのは、この11月14日に。
○証人(片山安孝)
14日付になってませんか。
○藤田孝夫委員
なったこの要望書のことですね。それを配ってほしいと言ったんですね。
○証人(片山安孝)
はい、配っていただいたかどうかは分からないですけど。
○藤田孝夫委員
当然、そうすると片山さんは、この書いた要望書を誰よりも先に維新の議員さんに渡したっていうことでよろしいですか。
○証人(片山安孝)
はい、ほかの方で理事会で配っていただけるめどがなかったので、理事会で配ってほしいなと思いました。
○藤田孝夫委員
なるほど。この中に書かれている内容と今日の証言の内容というのは非常に似通ってて、つまりクーデターを証明する内容になっているってことは認められますよね。
○証人(片山安孝)
クーデターはずっと言ってますから。それはもう私は前からずっと指示してますね。
○藤田孝夫委員
維新の部屋には何回行かれましたか。
○証人(片山安孝)
1回だけ。配ってくれてと、1回だけ。
○藤田孝夫委員
そのときの1回だけですか。間違いありませんか。
○証人(片山安孝)
間違いないです。
○藤田孝夫委員
私からは以上です。
○委員長(奥谷謙一)
すみません、時間が経過しておりますので、これで証人尋問を終えたいと思います。
片山証人におかれましては、ご出席いただきましてありがとうございました。
退出いただいて結構でございます。
(証人退室)
それでは、暫時休憩いたします。再開は午後3時です。
証人尋問(斎藤元彦知事)
動画
議事録(文字起こし)
○委員長(奥谷謙一)
それでは、休憩前に引き続き委員会を再開します。
次は、齋藤元彦兵庫県知事に対する証人尋問を行います。
齋藤元彦証人におかれましては、お忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうございます。
委員会を代表しまして御礼申し上げます。本委員会の調査のため、ご協力いただきますようによろしくお願い申し上げます。
証言を求める前に、証人に申し上げます。
証人は、原則として、お手元に配付の留意事項に記載の場合以外、証言を拒むことや、証言を求める場合の宣誓について拒むことができません。
もし、これらの正当な理由がなく証言を拒んだときは、禁錮または罰金に処せられ、また、虚偽の陳述をしたときは、禁錮に処せられることになる場合がありますので、ご承知おきください。
また、証人は尋問された事項に対してのみ証言をしてください。
尋問内容が不明確、また証人がその疑義をただすために私や委員に対し確認の質問をすることは可能であります。それ以外の質問、反論することはできません。
加えて、元県民局長のプライバシーに係る情報については、元県民局長の代理人弁護士から取扱については十分に配慮いただきたい旨の申入れがあり、当委員会において取り扱わない旨、委員間で合意をされております。証人におかれましても発言にご留意をお願いいたします。
なお、以上のことに反した場合は、私のほうで発言を中断させていただきますので、その点、あらかじめご了承ください。
それでは、法律の定めるところにより、証人に宣誓を求めます。
傍聴の方、報道の方も含めまして、全員ご起立をお願いいたします。
(全員起立)
○証人(齋藤元彦)
宣誓書を読ませていただきます。
〇委員長(奥谷謙一)
はい、どうぞ。
〇証人(齋藤元彦)
良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います。
令和6年12月25日。齋藤元彦。
○委員長(奥谷謙一)
それでは、着席をお願いします。
(全員着席)
証人は宣誓書に署名をお願いいたします。
(証人 宣誓書に署名)
それでは、証言に当たっての留意事項はお手元配付のとおりです。ご確認をお願いします。
委員各位に申し上げます。
本日は、事前に証人に通知をいたしております証言を求める事項について、証人より証言を求めるものであります。
尋問に当たっては、証人の人権に配慮されるとともに、円滑な議事進行にご協力をお願いします。
また、委員会冒頭にも申し上げましたが、発言される際には、個人情報等について十分に配慮いただきますようにお願い申し上げます。
それでは、齋藤元彦証人から証言を求めます。
では、私のほうから所要の事項をお尋ねいたします。
齋藤元彦さんで間違いないでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
はい。
○委員長(奥谷謙一)
住所、職業、生年月日については、事前にご記入いただきました確認事項記入表のとおりで間違いありませんでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
はい。
○委員長(奥谷謙一)
それでは、自民党から順次質問をお願いします。
○黒川 治委員
それではお願いをいたします。
まず、3月21日、3月20日に知事が文書を手に入れた翌日、幹部の職員というんでしょうか、初めての協議を行った場でのことでありますけれども、そのときに産業労働部長より、私自身が預かった、ある企業からもらったものを手元に置いていますと、申し訳ございませんという謝罪がありましたけれども、知事、これは受けられましたですよね。
○証人(齋藤元彦)
私の記憶では、そのような発言を受けたということはないというふうに認識してます。
○黒川 治委員
その場におられました他のメンバー、それぞれも、この他のメンバーですね、知事と部長を除いたほかの3人、ですから4人が知事に対して、3人ですね、ごめんなさい、が知事に対して謝罪並びに返却について語ったことを記憶されていますし、この場で証言もございました。改めて伺いますけれども、知事はそのやり取りの記憶ございませんか。
○証人(齋藤元彦)
はい、私の記憶ではそういったやり取りはなかったというふうに思ってます。
○黒川 治委員
では知事が、この商品、コーヒーメーカーでありますけれども、この物を受け取っていた。そして知事の指示、返却をしなさいよという指示があったにもかかわらず忘れていたということを知ったのはいつでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
その後、報道機関の取材の中でそういった取材がされているということをたしか秘書室長から聞いたときに、初めてその事実を知ったということです。
○黒川 治委員
いつかは覚えておりませんか。
○証人(齋藤元彦)
報道がなされた前日ぐらいだったと思います。
○黒川 治委員
3月の21日の時点ではなくて、報道がなされた、4月に入ってからだったと思いますけれども、その時点ということですね。
○証人(齋藤元彦)
そうですね。
○黒川 治委員
他の方との証言のずれがあるということですけれども、よろしゅうございますでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
はい。その報道の前の時点で初めてその事実を知ったというのが私の認識です。
○黒川 治委員
次のことを伺います。令和4年の12月、そして令和5年の7月と2回にわたりまして、知事を励ます会というか、ひょうごを前に齋藤元彦と語る会、あるいは県政報告会2023だったでしょうか、そういうタイトルで政治資金パーティーを行っておりますけれども、間違いないでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
はい。
○黒川 治委員
この会を主催した団体はどちらでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
ひょうごを前に進める会が主催しています。
○黒川 治委員
ひょうごを前に進める会とはどのような団体でしょうか。
○証人(齋藤元彦)
令和3年の知事選挙に際して設置した政治団体です。
○黒川 治委員
これは知事の後援団体という認識でよろしいでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、私に関する政治団体です。
○黒川 治委員
代表はどなたがやっておられるんでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
今ちょっと手元にありませんが、私の親族だというふうに認識しております。
○黒川 治委員
今申しました2回の政治資金パーティーをされておりますけれども、2回それぞれにおいて、知事の命を受けたということでしょうか、片山前副知事がパーティー券の販売あるいは運営等について主体的に動いておられた。特に2回目の開催におきましては、県職員のOBというか、の方々に依頼をして、このパーティー運営、パーティー券の販売について動かれておったということでありますけれども、知事はこのパーティーを開催するに当たって、片山、当時の副知事にどのような依頼をされたんでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、特別職である片山副知事ですから、政治的なパーティーの運営に関してお願いしていたということです。
○黒川 治委員
具体的なお願い内容というのは分かりますか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、パーティー券の販売、それから含めて全体的なパーティーが、開催が円滑にいくようにお願いしていたというふうに認識してます。
○黒川 治委員
分かりました。
先ほど、私は片山さんのほうから県のOBの方等を中心に依頼をされたというお話をしましたけれども、その中で片山さんは、当時、商工会議所の関係先へ、当時現職でありました信用保証協会の理事長並びに専務理事に依頼をされて、依頼をされた2人は、その指示どおりに活動を行っております。
依頼された商工会議所関係者のところに訪ねていって、相手との挨拶のやり取りの中に信用保証協会の役職者である旨の名刺を交換したり、協力要請をされていましたけれども、知事はこのことをご存じでしたでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
存じ上げてません。
○黒川 治委員
知らなかったですか。
○証人(齋藤元彦)
はい。
○黒川 治委員
今、私がちょっと気になって、先ほども片山氏にも確認をしたんですけれども、OBの方に依頼することについて問題にしているわけではありませんけれども、信用保証協会、特に信用保証協会の現職の理事長、専務という肩書の方に依頼をしたということは、ちょっとまずいんではなかったかなという思いで先ほども聞いていたんですけれども、知事はどう思われますでしょうか。そのとき知らなかったんですけど、今知って、どう思われますか。
○証人(齋藤元彦)
パーティーに関しては特別職であった片山副知事に販売を含めた運営の支援を依頼したということはあります。その後、片山副知事が有志のボランティアとして、県のOBの方々と一緒に手伝っていただいたということは認識してますけども、どのようなやり方でやってたかということについても、片山副知事に基本的にはもうお願いしてました。
○黒川 治委員
はい、それは先ほど分かりました。今、私が言った、その中で、そういう2人の信用保証協会の役員がおったということについて、知事は知らなかったということですから、それは結構ですけども、今、私のほうからそのことを申し上げました。もし当時、そのような役職の方がやっているということを知っていればどうされていましたかということを伺っておりますが、いかがでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
それは当時、片山副知事がそれぞれの方とボランティアの中でやられたということだと思います。
○黒川 治委員
どなたがやってても、逆に気にはしないということですね。
○証人(齋藤元彦)
ボランティアとしてやっていただいたということだと思いますね。
○黒川 治委員
この2人に頼んだことについて、他の元同じ職にあった方、あるいは県職員のOBの方がそういう役職、そういう立場ではこういう政治的な関係には携わらないほうがいいよという、私にとっては一般論、まさしく常識論だと思いますけれども、そういう注意がありましたけれども、今、知事は、当時のことは知らなかったから結構ですけども、今そういうことがあったということに対して、それはまずかったかな、注意すべきだったかなということもないということですね。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、個人として、ボランティアでお手伝いをいただいてたということですから、そこは片山副知事に運営については、そういった形の中でお願いをしてましたので、その当時の対応はそういうことだったというふうに思ってます。
○黒川 治委員
個人という立場でということを認識もしながら、当事者2人も思っておりましたけれども、結局は役職名刺を使った。そして、実際は名簿を取りに行くということだったけれども、チラシを配った、協力要請もしてしまったという行為に対して、当事者は反省をしています。まずかったかなということを認識されていますけども、知事はやっぱりそれは、ボランティアだからしようがない。何ら問題がないというふうにお思いということですね。
○証人(齋藤元彦)
法的に何か問題があるかどうかということを含めて、ご指摘だと思いますけども、私としては片山前副知事にパーティーについては、対応をお願いしてましたので、片山前副知事が関係するOBの皆さんとボランティアの中で対応して協力をしていただいたということだと思います。
○黒川 治委員
実はこの2人以外にも、多くの方々に片山さんは依頼をしてます。県職のOB、県の関係団体、当時現職、県の関連の団体の現職の理事長であるとか、会長の方々がその実務世話人として活動されていました。
知事は当然知っておられたと思いますけれども、この実務者の世話人の方々に、知事のほうからお言葉をかけられたりとか、協力要請したということはございましたか、直接。
○証人(齋藤元彦)
基本は片山前副知事が当時、有志の方々にお声がけをして、ボランティアで一緒にやっていこうということをされたんだと思いますね。会のときにも一部の方は、ボランティアで手伝っていただいたんで、そのときに運営についてのご支援をいただいたということのお礼をしたということはあります。
○黒川 治委員
どのようなメンバーであったかというのはご存じですか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、県のOBの方々だったと思いますけども、詳細の名前と役職はちょっと今は
覚えてませんが、有志の元県職員のOBの方々が、有志でボランティアでやっていただいた
ということだと思います。
○黒川 治委員
7月のパーティー事業が終わった後、このグループが片山さんが主催で打ち上げ会、反省
会をされました。この場に知事、お礼に上がっておられますよね。
○証人(齋藤元彦)
いや、私は行った記憶はないですね。
○黒川 治委員
そうですか。六甲荘でお昼間の時間にやられて、知事がお礼を言いに来られて、まあ長時間ではありません、短時間ですけれども、皆さんにありがとうございましたと言ってということがあったというふうに、私は耳にしましたけど、それは間違いだったでしょうか。ごめんなさい。行ってないということでよろしいでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
それは、私はそういった認識はないですね。その場では、ありがとうございましたって、パーティーが終わったときに。
○黒川 治委員
会場ではという話ですね。
○証人(齋藤元彦)
会場ではお礼しましたけど、打ち上げに行ったっていうことは多分ないというふうに認識してます。
○黒川 治委員
打ち上げ、反省会が開かれたというのはご存じですか。
○証人(齋藤元彦)
ちょっとそこは知らないです。
○黒川 治委員
知らない。実は、このときの会費を片山さんがもう全額自分が頼んだメンバーだからということで、全額負担をされたということなんですけども、このこともそういうことでは、当然知らないということですね。
○証人(齋藤元彦)
私は、それは存じてません。
○黒川 治委員
そうですか。
残念ながら、現在は知事にとって、そういう意味で大変信頼されておられた片山さんがそばにおられない状況でありますけれども、片山さん、副知事に就任されてからというか、知事にとって大変よき相談相手というか、信頼されておった方だと思うんですけれども、よりそのような深い関係、深いというか、知事にとって大切な存在だったということでよろしいでしょうか、片山さんのことです。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、大変熱意があって、優秀な方ですから、仕事面においても大変心強い方でしたし、そういった意味でも信頼を置いてる方でしたね。
○長岡壯壽委員
では、時系列で尋問をさせていただきます。
まず、今年の3月20日のことです。知事がこの告発の文書を民間から入手したと証言されています。後ほど、事務局に連絡します。このような証言であったと記憶しております。これは、されてなかったら後ほどしていただけますでしょうか。民間とはどなたかを、どなたからもらったかいうことを。
○委員長(奥谷謙一)
前回、そうですね、ちょっとまだお聞きできてないんで、また事務局に。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、民間の方からいただいたということです。
○長岡壯壽委員
それは後ほど事務局に連絡しますという証言だったんですけど、それはしていただけますか。
○証人(齋藤元彦)
そこはまた事務局と相談しながらですね、委員長にまたお任せしたいと思います。
○長岡壯壽委員
続いて、翌日3月21日です。知事はこの文書を基に幹部4人の方と合計5名で協議をされています。そして、やっていないということで調査が始まりました。そのときに、様々な証言はあるんですけれども、齋藤知事からどう指示を出されましたでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
職員の名前や企業名など、具体的な個人名などが出されて、その方々の誹謗中傷性の高い文書ですから、しっかり調査をするようにということを指示したというふうに記憶しております。
○長岡壯壽委員
しっかり調査してくれということを指示されたということです。
それから、3月21日、22日、そして23日と調査が進みまして、3月23日、これは土曜日ですが、当時の副知事から元西播磨県民局長に確認しに行くと、会いに行くということの発言がありまして、齋藤知事は了承されたと認識しています。そのとき、あなたは何と言って了承されましたでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、たしか公用メールを確認等する中で、今ご指摘いただいた元西播磨県民局長さんが作成・流布した可能性があるので、本人に事情を聴きに行くということを含めて対応したいという話、報告があったというふうに記憶してます。
○長岡壯壽委員
そのときに齋藤知事は何とお返事されましたですか。
○証人(齋藤元彦)
適切に対応してくださいと。
○長岡壯壽委員
適切に対応してくださいと、こういうことで。
それから3月25日、当時副知事が西播磨県民局に行かれて、パソコンを回収されてきまし
た。そして3月27日、午後から知事の会見がありました。そして、このとき午前中のレクで
なんですけれども、人事当局は、県民局長の総務部付の人事異動を発表し、特に記者レクで
は調査中のため詳細は言えないとしていました。そして、これも幹部に伝え、そして知事も
了承していたと、そう認識しています。この調査中のため詳細は言えない、この報告を知事
が受けられたときに、知事は何と発言されましたか。
○証人(齋藤元彦)
ちょっと詳細は覚えてませんけども、そういった人事異動ですね、総務部付にされるって
いうことを人事当局として発表しますということを報告を受けたということですね。
○長岡壯壽委員
このときに知事の行動として、注意喚起のメモを渡されたとの証言もあります。そのメモ
の内容はどのようなものであったのでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
ちょっとすみません、今、手元にないので記憶してません。
○長岡壯壽委員
メモを渡されたことは、ご記憶ありますか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね。その後に、たしか定例会見が予定されてましたので、その人事に関することが聞かれる可能性があるという話だったと思います。
○長岡壯壽委員
また、メモの内容については、様々な証言もありますので、思い出していただきたいなというのはあるんですけれども、今は記憶にない、今は。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、人事異動の内容があってという話だったと思いますが、その中で、たしか当時副知事とのやり取りの中で、やっぱりこの文書というものが、一定、誹謗中傷性の高い文書だから、私のほうとしては、やはり会見で述べたように、大変、県としてはよくない文書だということですから、SNSへの拡散を含めて、注意をしてくださいっていうことを話したほうがいいんじゃないかということを私はその場で申し上げて、たしか副知事含めてその場で聞いておられて、そういった方向性で会見に臨むかということをたしか確認をしたという記憶もあります。
○長岡壯壽委員
それをメモで渡されたと、書いたもので。
○証人(齋藤元彦)
その内容ではないですけど、私のほうでそういった発言をしたほうがいいかなっていうふうに話を出しまして、そこでたしか副知事などと話をして、そういったことで発言するっていうことの知事の方向性というものをみんなで共有したというふうに記憶はしてます。
○長岡壯壽委員
この当時のことです。3月27日前後、3月の人事異動の時点、この頃のことについて、知事は8月7日の記者会見で述べておられます。少し長くなりますが、3月の県民局長から総務部付の人事異動の部長級の人事異動の時点では、このときですね、この記者会見の頃では外部通報に当たらないとする法的な見解までは有していませんでしたが、元県民局長は3月25日において文書はうわさ話を集めて作成したものであると説明しております。また、真実であることを裏づける証拠、関係者による信用性の高い供述などが存在することは説明されていませんでしたので、外部通報として保護されないことを示す事実、すなわち信ずるに足りる相当の理由が存在しないということを示す事実は入手していたということになりますと。よって、人事異動や懲戒処分に問題はなかったと考えておりますと、こう発言されています。すなわち、この3月27日前後、人事異動した時点では外部通報に当たらないとする法的な見解までは有しておられませんでした。
そこでお聞きします。一つ目、外部通報に当たらないとする法的な見解は、ではいつ頃、どなたから得られましたか。
○証人(齋藤元彦)
ちょっとそこは記憶には今の段階で、いつかっていうことは定かに申し上げられないかもしれないですけども、少なくとも3月27日の段階では、今、委員が申し上げたことを私は認識してましたので、人事異動をさせていただいたということだと思います。
○長岡壯壽委員
今おっしゃったように、この時点で外部通報に当たらないとする法的な見解がない中で、元県民局長の職を解き、退職を保留されています。それはあなたの指示ですか。
○証人(齋藤元彦)
3月の時点で作成、配布された文書が全体として、私も含めて当事者としての認識の中でもありますけど、今、委員がおっしゃったように、誹謗中傷性の高い文書だというのは私ども県の認識でしたから、それに基づいて退職を保留したり、ここは人事当局としても判断をされたというところで、私としてもそれを最終的には了承したということですね。
○長岡壯壽委員
この外部公益通報に関して、公益通報者保護法が2020年に改正されています。この公益通報者保護法が2020年に改正されたことを知らないと齋藤知事は証言されています。
その内容を読みます。公益通報者保護法が2020年に真実相当性に関係なく、目的が不正でない限り公益通報と認めるという改正がされたことは知らない。ご指摘の、このときの証言の前の質問ですけれども、ご指摘の2020年の法改正を踏まえて違法性があるかどうかは少し確認させていただき、必要があれば文書で提出させていただきたいと証言されています。
そこで、この百条委員会として、まあ、私からですけれども、この文書でこの見解を提出いただきたいんですけど、このときの証言どおり、いかがでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
対応については、また確認、検討させていただきますが、いずれにしても2020年の改正を踏まえて、今の現行の2024年の公益通報者保護法の今の状況になってますから、その法律の中で、今回の3月20日の文書に対する対応については、適切であったというふうに、これは県当局、そして県の弁護士とも相談しながらやってますので、全体としては問題なかったというふうに考えています。
○長岡壯壽委員
このあと3月27日、定例記者会見が終わった後、当時の幹部、総務部長が第三者による調査を進言していると、齋藤知事に進言したと証言しています。これについて齋藤知事はどのように発言されましたでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
第三者委員会というものが議論の中で出たということはあるかもしれないですけど、私の記憶、認識では、進言されたっていう認識はないです。むしろ、懲戒処分に該当する可能性のあることだから、今回は人事課が内部調査として、人事当局が調査をするということが適切だというふうな、むしろ進言を受けたというのが私の記憶です。
○長岡壯壽委員
4月中旬です。この4月からの新しい総務部長を通じて人事当局に4月4日の調査結果を待たずに処分できないかと14日か15日に打診されています。そして、4月24日は人事から提案し、知事も一旦了承されたんですが、人事のほうが撤回し、5月10日か17日でと再提案し、5月10日で齋藤知事も一旦了承されたんですが、早めて5月7日に処分の発表の日が決まりました。
そして、このとき、この当時の総務部長が、知事はこうおっしゃったと証言しています。風向きを変えたいよねという証言であります。知事はどのように発言をされたのでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
私の認識、記憶ではそういった風向きを変えたいっていう旨の発言をしたっていうことは全くないですね。今回の懲戒処分については、あくまで県の人事当局が調査をして、懲戒処分に該当する事案が四つ判明しまして、認定されたので、手続、内容とも正規の手続を経て対応したということです。
私が何か公益通報を、結果を待つということを了承したりとか、公益通報の結果を待たずにやれとかって言ったことも、記憶としてはないです。これは今回は人事当局が、これ5月の7日のたしか会見でも言ってますけども、懲戒処分に該当する非違行為が判明した以上、それは手続に沿って処分をするということがある意味、必然の流れであるということを当時の人事当局の担当者も言ってますし、私はまさにそのとおりだというふうに認識してます。
○長岡壯壽委員
そうすると、これは当時の総務部長の独断でこのような調整を進めたということになります。齋藤知事は、これは総務部長の独断であると、そういう認識でしょうか。
○証人(齋藤元彦)
独断というか、今回は県の懲戒処分ですから、何か独断でするということは基本的にはできない。やっぱり、人事課の調査、それから手続、これは綱紀委員会も経て、県の調査としてやりながら手続もきちっとやった上での懲戒処分ですから、これは時期も含めて県の人事当局などが適切に対応していったというふうに私は思ってます。
〇長岡壯壽委員
以上です。
〇委員長(奥谷謙一)
はい。藤田委員。
○藤田孝夫委員
私のほうから時系列に沿って聞いていきたいと思います。
まず、令和3年度の知事選挙のことについてお聞きします。
齋藤知事が知事選挙に出るっていうことを県職員に伝えたことはありましたか。
○証人(齋藤元彦)
そういったことはないと思います。
○藤田孝夫委員
ない。
○証人(齋藤元彦)
はい。
○藤田孝夫委員
選挙前に知り合った職員は多数存在しているっていうことは事実なんですけれども、選挙前に立候補する話は誰にもしていないということで間違いありませんか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、私の記憶では誰にもしてないです。
○藤田孝夫委員
ひょうご民博2025、こういう事業のホームページがありまして、今下りてるのかな、ちょ
っと見つからなかったんですけど、その打合せの場所において、齋藤知事と県職員が写って
いる写真、その他にも数枚あるんですけれども、誰からの紹介で、そのひょうご民博2025に
参加されましたか。
○証人(齋藤元彦)
これはたしか民間の方だと記憶してますけども、万博というものが開催が決まったので、兵庫県でも万博をしっかりチャンスと捉えて、県内各地の地場産品であったりとか、そういったものをPRする流れをぜひつくっていくことがいいんじゃないかなっていうふうに話し合って、その方々といろんな地域のいいものを見てみようかという話を有志で、ボランティアっていうか、やってたっていうことは記憶してます。
○藤田孝夫委員
民間の方までは覚えておられる。誰とは言えない。それとも記憶にない。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、民間の方。記憶にないというか、民間の方数名だったというふうに。
○藤田孝夫委員
数名。
○証人(齋藤元彦)
はい。
○藤田孝夫委員
知事は、その当時、大阪府の財政課長でしたね。兵庫のイベントに参加した目的っていうのは、さっき言われた、その万博の関連で、様々なことを兵庫で展開したいと、こう思われたわけですか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、当時は大阪のほうで勤務してましたけど、そういった万博のいい流れをぜひ兵庫県でもいろんなところで波及するっていうことがいいんじゃないかということで、個人として、これは職務ではなく、プライベートな、個人としてやってたということです。
○藤田孝夫委員
個人としてやったと。当然、大阪の財政課長の立場からだったら、万博の波及効果を大阪に持っていきたいと考えるのが普通ですから、あくまで個人の好みとして兵庫県で活動したいと思われた。それ、何かこれは意味があるんですかね。
○証人(齋藤元彦)
万博は大阪だけで開催されるのは、大変、大阪だけではなくて、大阪・関西万博ですから、それはやはり兵庫県にその効果というものを、誘客も含めて、いい流れをつくっていきたいという思いをお持ちの方もおられましたので、その方々と共鳴した中で、そういった活動をしようというふうに思ったということですね。
○藤田孝夫委員
次に、齋藤知事と接触があった県職員、県議会議員等についてですけれども、その県議会議員何名かは、県職員のほうから県の資料やデータなど、県の基本的な様々な特徴的な施策に関する情報を得ていましたけれども、そのことはご存じでしたか。
○証人(齋藤元彦)
ちょっと私はそこは存じ上げてないです。
○藤田孝夫委員
じゃあ、その件は結構です。知らなかった。
人事の昇進についてお伺いします。
知事選挙前からの知事の知り合いだった職員の出世のスピードが速かったことが、様々な調査で明らかになっています。齋藤知事は関与していますか。
○証人(齋藤元彦)
人事については、適材適所でやってるということだと思います。
○藤田孝夫委員
関与していない。また、誰かにそのことをじゃあ指示したっていうことなんですか。それとも強烈に自ら直接に関与したのかを聞いてます。
○証人(齋藤元彦)
県の幹部職員含めて、当然、私が任命権者ですから、そこは知事が任命したりするということは当然ですけども、その配置をどのようにするか、どの方がどのタイミングで、部長であったりとか、課長、次長に就任するかということは、これは当然、県の人事当局などがしっかり考えて適材適所で、タイミングも含めてやるものだというふうに思ってます。
○藤田孝夫委員
その人事当局と知事との関係については、どうなんでしょうか。知事が一定程度、人事当局に対して関与しているということでいいんですか。それとも、一切、人事当局に任せているということなんでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
そこは当時の片山副知事であったりとか含めて、人事のことについては、当然、私は人事当局以外も、それは相談しながらどういう人事がいいかっていうことはもちろんやるのが、これはどこの県であっても、組織であっても一緒だと思います。
○藤田孝夫委員
分かりました。
それでは、次ですけども、新県政推進室長の初回の人選ですけれども、これはどなたが行ったんですか。
○証人(齋藤元彦)
新県政推進室の室長は、どなたがというか、私ですかね、結果的には。
○藤田孝夫委員
知事が行われた。
○証人(齋藤元彦)
はい。
○藤田孝夫委員
片山副知事の人選はどなたが行ったんですか。
○証人(齋藤元彦)
片山副知事を副知事に。それは私です。
○藤田孝夫委員
両方とも知事が行ったっていうことですよね。
次に、第三者委員会の設置についての知事の発言について、その関連でお伺いします。
先ほども長岡委員の説明にもありましたとおり、第三者委員会の設置について、様々な進言があったとか、前向きな検討がなされたとか、様々証言はあったんですけれども、一向に進んでいなかったのが、4月の話です。4月24日に丸尾議員のほうから第三者委員会の話が、それから5月の10日にひょうご県民連合さんが知事に対して第三者委員会の設置を申し入れられた、9日ですか、10日、どっちかですね。
その後、県民連合さんは同時に百条委員会も必要だよねっていうようなことを公表されています。5月14日、知事は定例記者会見で第三者委員会の設置を、方向性を明らかに、要るんだろうと思うっていうようなことをおっしゃっています。
この発言っていうのは、知事が決められて発言したことでしょうか。それとも、片山氏からの進言だったんでしょうか。どなたかからの。
5月14日の知事が記者会見でおっしゃった第三者委員会の設置の方向性について言及されたことです。
○証人(齋藤元彦)
ちょっとそこは時系列がよく、ちょっと今手元に資料がありませんが、たしかその前後に、議会のほうから第三者委員会の設置の申入れをする話があったと思いますので、出てきたのかな。当時、内藤議長だったと思いますけども、そういった話が出てきてたので、第三者委員会の設置についての検討も言及したというふうなことだと思いますね。
○藤田孝夫委員
なるほど。実は、5月16日の代表者会議でその話が正式に出たので、知事のほうが先におっしゃってるっていうことは申し上げておきます。
それから、5月15日に、いよいよ自民党の総会でもその話が出まして内藤議長が座長を務める非公開ですけども、マスコミを入れない県議会の代表者会議で第三者委員会設置に向けた議論があって、同時に百条委員会の並立を求める意見も出たということですけれども、出まして、5月16日の代表者会議で正式に、維新さんも後から賛同されて、議会の要望として第三者委員会をつくるっていう形がつくられました。
知事は、県議会議長あるいは県議会議員の誰かに第三者委員会設置要望を議会から出してほしいというお願いをされましたか。
○証人(齋藤元彦)
そこは、ちょっと全然覚えてはないですけども、議会のほうから第三者委員会の設置というものが大事だという声が強まっているということは、当然いろんな方から伺ってたということは記憶してますね。
○藤田孝夫委員
私が聞いているのは、そのことを知事からの要望として、県議会議員の誰かに、もしくは片山前副知事ほかに、要望書を出してほしいというお願いがされたか、されていないかを聞いています。
○証人(齋藤元彦)
そこは、当時はちょっと全然覚えてないですけども、当然、議会のほうから要請がされるということは重く受け止めなければいけないということで、そういう話があればしっかり対応しなきゃいけないということを協議してたということは記憶してます。
○藤田孝夫委員
知事が今おっしゃったのは、議会のほうから要請があったから、第三者委員会の検討をしなければならないとおっしゃいましたけど、私がお聞きしているのは、知事が先に議会のほうに要請してほしいというお願いを、親しい県議会議員とか片山さんにされたかどうかを聞いています。
○証人(齋藤元彦)
ちょっとそこは私は全く記憶にないですね。
○藤田孝夫委員
記憶にない。
○委員長(奥谷謙一)
そろそろまとめてください。
○藤田孝夫委員
最後ですけれども、6月13日、県議会の一般質問の最終日、片山副知事のほうが自民党ベテラン県議会議員に百条委員会設置をやめてほしい、代わりに副知事を辞めると話された件ですけれども、これは知事の指示で片山さんがそうおっしゃったんでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
それは全くないです。
○藤田孝夫委員
ない。これ、実は片山さんの、結局とか、一般質問の事前通告っていうのがありますから、通常であれば、それを見たときに副知事の役職とかいろんなことを聞かれるっていうことでありましたから、その答弁の確認とか調整っていうのは当日されたんでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
答弁調整はたしか前日にしてるもんだということが通常ですね。
○藤田孝夫委員
そのときもそうおっしゃってました。初めてそのとき聞いたと、議場でとおっしゃいましたから、それは間違いないですね。
○証人(齋藤元彦)
はい。
○藤田孝夫委員
そうしましたら、その後ですね、これは重大な問題ですから、議会が終わった後以降、そのことの確認を片山副知事にされましたか。なぜだとか、いろんな経緯を聞かれましたか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、たしかその後に、事後で、こういった当時の議運委員長のところにお話をしに行ったということは、たしか経緯を説明されたことは記憶してます。
○藤田孝夫委員
私が聞いてるのは、片山副知事と齋藤知事がその件の行動についての話合いをされたかってことです。
○証人(齋藤元彦)
だから、片山副知事から事後でこういう話がありましたということを報告を受けた記憶はあります。
○藤田孝夫委員
報告を受けた。
〇委員長(奥谷謙一)
時間が経過しておりますので。
〇藤田孝夫委員
はい、もう結構です。ありがとうございました。
○委員長(奥谷謙一)
それでは、維新の会。
○増山 誠委員
11月14日に、片山元副知事が議長あてに要望書というのを出してるんですが、この内容についてはご存じでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
ちょっと詳細は見てはないですけど、そういったものがあるということは存じてます。
○増山 誠委員
これの中に、アンケートについては伝聞が大半を占めているが、伝聞を過大評価していないかという話があります。アンケートが公表されてから知事への誹謗中傷が非常に大きくなったというふうに認識しておりまして、深刻な影響を受けられたのではないかというふうに考えております。
委員会として、アンケートの取り方、公表方法、集計の方法等についてですね、反省があってもよいのではないかというふうに思っておりまして、アンケートの問題点の具体例として、告発文の2項目め、知事選挙の事前選挙活動について、ちょっと取り上げたいと思うんですが、証人尋問を通して事前選挙活動に全く関与していないと判明した職員の名前がアンケートに25回も出てくるという珍現象が発生いたしております。特筆すべき内容として、アンケート回答に、その職員のおじさんが齋藤知事の後援会長をしているとの記載があったのですが、職員の方に聞くとおじさんは既に他界されており、アンケートの回答が完全なデマであるというふうに判明しました。これに限らず、明らかなデマが何度も出てくるアンケートでありますので、精査してから事実のみ公表する、そもそもマスコミには公表しないなど
の対策が必要であったと思います。
特に、丸尾委員がされた私的なアンケートに記載された臆測を基にしたデマの拡散というのがこの文書問題の火つけ役となった面がありまして、これを資料として採用したことも、我々百条委員会として大いに反省すべき点であるというふうに考えております。
報道機関への情報提供にも反省すべき点が多いと思いまして、当初から様々な不備が指摘されているこのアンケートの回答をきちんと精査すれば、4割の職員がパワハラを見聞きしたという内容の報道にはなり得ないわけですけれども、精査してもなお、4割パワハラ見聞きというような記事を書く人間がいたら、よほど読解力がないか、悪意を持って編集したかのどちらかしか考えられないと思うんですが、ネット上でこのアンケートを精査した方で、パワハラを見聞きしたのは4割だと言ってる方はほとんどいないところを見ると、やはりマスコミの皆さんに1から10までこれからは説明して、こういうふうに悪用したらいけませんよというような形で注意事項を添付した上で情報提供しないといけないふうに思いますけれども、アンケート結果から、知事に今いろいろ質問出ましたけれども、全く身に覚えのない
質問も多かったと思うんですが、これについて何かご意見等ありますでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、アンケートについては百条委員会のほうでされるという判断をされたということです。内容については、取りまとめの段階、中間、それから注書きに、これはあくまで途中段階的なことで、これは事実認定するものではないっていう注記があったということはありますけども、ただ、その内容が報道機関を通じて様々な形で報じられたということは確かにありまして、それが県のほうにもかなり厳しいご指摘があったりとか、私自身も大変そこは厳しい状況があったということは事実ですね。
○増山 誠委員
もう一つ、パワハラや贈答品疑惑について誘導尋問が行われたことの調査検証を求めるということで要望が来ております。これは委員会の公正性を疑われる重大な問題であるというふうに考えておりまして、うそですとかデマをあたかも事実であるかのような前提に立った質問が行われたということも事実であります。
竹内元県議は、姫路ゆかたまつりではパワハラの事実があったとして質問しましたが、地元の方が声を上げてデマであったことが判明しております。
(下線部に関する注記)委員会における竹内元委員の発言に「姫路ゆかたまつりではパワハラの事実があった」という質問は確認できません。増山委員の下線部分の発言は、竹内元委員がインターネットの記事を自身のブログで引用したことを受けて、「竹内元委員が委員会内で質問した」と事実誤認したことによるものです。(令和6年9月6日の証人尋問において、竹内元委員は齋藤知事に対して姫路ゆかたまつりについて質問を行っていますが、質問内容は「パワハラの事実があった」についてではありません。)
※この注記は増山委員本人に事実誤認であることを確認の上、記載しています。
竹内元委員が「姫路ゆかたまつりではパワハラの事実があった」とのデマを拡散したのは、百条委での発言ではなく、竹内氏自身のブログだったいう訂正です。
竹内元県議に関してもう一つ虚偽の事実を持って質問が行われたという事例がございまして、9月6日の百条委員会において、県商工会連合会の専務理事から昼休みに電話があったという竹内氏の発言があり、専務理事が片山副知事にゴルフセットを進呈したと言っているが事実かという内容の質問がされました。
(下線部に関する注記)竹内元委員は「昼休みに電話があった」ことは発言していますが、「県商工会連合会の専務理事から」電話があったとは発言していません。増山委員の下線部分の発言は、竹内元委員の発言の中で、電話の相手について明示されなかったことにより、「専務理事から電話があった」と事実誤認したことによるものです。
※この注記は増山委員本人に事実誤認であることを確認の上、記載しています。
9/6の竹内委員の発言は、以下の内容でした。
「先ほどの休憩で、あなたが答弁した内容についておかしいという電話が私のもとに入りました。県商工会連合会の専務理事があなたにゴルフクラブを渡したと、それを長期貸与というかもしれないと、非常に具体的な電話があったんですけど、これは事実ですか。」
電話が誰から入ったか、確かに明示していませんが、多くの人が「専務理事から電話が入った」と認識し、専務理事本人にも問い合わせが殺到したようです。
ところが、12月24日に委員会で関係者に聞き取り調査をしたところ、専務理事は竹内氏電話しておらず、勝手に名前を出されたというふうな確認がされました。委員会後に、各所から専務理事に問合せの電話が殺到し、迷惑なので、次の百条委員会で訂正をしてほしいと伝えたところ、竹内氏は一旦了承したものの、その後専務理事に電話をかけ、百条委員会に証人として呼び出すぞと脅しをかけたそうです。専務理事は関係のない贈答品の件で百条委員会に出頭することはおかしいというふうに伝えましたが、竹内氏から訂正はしない代わりに百条への出頭要請はしないという約束を強要されたと確認が得られました。
(下線部に関する注記)増山委員の下線部分の発言には誤解を生じさせる部分がありますので、以下、専務理事の聞き取り調査内容を記載します。
「・9月6日の片山元副知事への証人尋問における竹内委員の発言は、証人尋問の休憩中に私が竹内委員に電話をかけたと誤解されるような発言であったため、実際に多くの方から私に問合せがあり非常に困惑した。この件については、後日、竹内委員に電話で問いただし、委員会の場で発言を訂正してほしい旨伝えたところ、本人も次回の委員会で訂正すると言われた。
・また、10月上旬に竹内委員から電話がかかってきた。ゴルフクラブの件について委員会で質問をしたいので、証人として出てくれないかとの依頼であった。私が断ったところ、脅されるようなことを言われたので、発言訂正の件はどうなったのか聞いたところ、それについてはきちんと訂正するので、それを条件に証人として出てもらう話はなかったことにすると言われたが、竹内委員は発言訂正をしないまま議員辞職された。」
この聞き取り調査内容を踏まえると、増山委員の下線部分の発言は事実誤認によるものです。
※この注記は増山委員本人に事実誤認であることを確認の上、記載しています。
増山委員発言の「約束を強要された」は事実誤認でしたが、竹内元委員が百条委員の立場を利用し、専務理事を脅すようなことを言ったことは事実だったようです。
- 竹内氏が発言を訂正することを条件に、証人として百条委に出頭する
- 発言を訂正しない代わりに、百条委への出頭要請はしない
の2択を提示し、専務理事は後者を選択したようです。
誘導尋問、高圧的な尋問、デマに基づく尋問、関係者への脅し・強要、まさに百条委員会の信用を失墜させる行動のオンパレードでありますけれども、これ自体、委員会の公正性を大きく毀損する行為であり、非常に問題であるとは思いますけれども、ここの奥谷委員長はこういった誘導尋問を制止、注意すべき中立な立場であるべきにもかかわらず、片山元副知事に対しても、付箋を投げられたとき、パワハラがあったと思いましたよねなどとの誘導尋問を繰り返しました。
こういった姿勢であったこともしっかりと反省すべきであると考えますけれども、この件について委員会の姿勢等に何かご意見ありますでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、ゆかたの件については公民館に私は行ってもないですし、そういった委員会の皆さんに何か怒号を発したとかっていうこともしてませんので、そういったことがあたかも事実であるかのように元県議が言われたということは、大変、私自身も心が痛みまして、ショックでしたし、これは地元の方もせっかくコロナが終わって、通常のゆかたまつりを開催されるときに、播州織の浴衣を着て知事が出席させていただくということで、皆さん地元の方もやっぱりコロナ後の第一歩ということで頑張ってやっていこうっていうものでしたので、大変そういった意味では私自身も残念だというふうに思ってます。
○増山 誠委員
はい。もう一つ、クーデターについて。話が替わりますけれども、片山元副知事が不正な目的ということでクーデターという話をされておりましたけれども、公用PCの内容を我々確認をして、元西播磨県民局長は、その文書の中で、県幹部を仲たがいさせる具体的な工作を行っていたということが判明いたしました。
令和4年4月、元西播磨県民局長は県幹部に対して投書を送付しています。この文書は別の県幹部3人を批判する文書になっていました。
また数ヵ月後に再度同じ県幹部に対して投書を送付しています。内容を見ると、明らかに悪意を持った文書としか言いようがありません。このような文書について、知事は内容をご存じだったでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
私は全く存じ上げてません。
○増山 誠委員
なかなかこういった詳細の文書を見ないと、クーデター計画というのも判断がつかないかなというふうに私は思っておりまして、もう少し文書の内容を確認すべきではなかったのかなと。そうすることによって片山元副知事が言われてるクーデター計画というような部分がですね、もう少し具体的に知事にも分かったのではないかと思うんですが、この辺についてはどういったご認識を持たれてますでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、私は3月の25日前後のときに、片山前副知事から元西播磨県民局長に関して、クーデターであったりとかっていう発言も出てきてますということは報告は受けてましたので、一瞬耳を疑ったというところもありましたけども、今、委員がご指摘いただいたということは仮に事実であるとすれば、これはやはり大変問題があるということだと思いますし、本来、公務員の皆さんというものは、やはり職務に専念をするということが大事だと思いますので、それをほかの職員の方を誹謗中傷したり、何か分断をさせるような行為をしていたとすれば、それはやはり職務中にやるべきこととしては、あってはならないというふうには思ってます。
○増山 誠委員
はい、ありがとうございます。
〇委員長(奥谷謙一)
はい、副委員長。
○岸口みのる委員
今回の問題で、知事と大きく見解が分かれておりますのが公益通報について、外部通報か否かということです。これは今回の調査について非常に重要な分岐点になる問題かというふうに思ってます。今日の午前中、3人目の参考人からのレクを受けました。またあわせて、先ほどからご指摘のとおり、法改正によって外部通報に当たるのではないかとの指摘があります。この外部通報に当たることによって、不利益の取扱の無効、保護が受けられるのか受けられないのかということが大きく分かれてきます。
知事は3月25日の探索、それから5月7日の人事処分と繰り返しその行為を行われていますけれども、まず、一番原点でありますこの真実相当性、これについて先ほどの議論も踏まえて、率直にどう思っておられるのかをお聞かせいただけませんか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、3月20日時点で把握した文書については、やはりその時点でその文書そのものが、私もそうですけど、県職員や企業、団体名、実名が挙げられて、違法行為に加担してたかのような記述がされたということ、五百旗頭先生が亡くなった原因が、あたかも県の副理事長の人事に起因するかのような記述もあったということなどを含めてですね、明らかにそこは誹謗中傷性の高い文書だというふうに私自身も認識をしていました。
それから真実相当性の要件である客観的な証拠や供述というものも添付されてなかったということもあります。そして3月25日の元県民局長への聴取の中で、うわさ話を集めて作成したということをご本人もおっしゃっていて、その後数回の人事課による内部調査の中でも、そのうわさ話を集めたということを、ある意味、そうじゃなくて、こういった証拠がありますということを具体的に出してこなかったので、やはり外部通報の保護要件である真実相当性というものは満たさないというのが今の見解ではあります。
○岸口みのる委員
知事は終始一貫そのような発言をされておられます。もう一方で、不正の目的、これはずっと片山前副知事が主張されておられたことです。先ほど、増山委員の説明の中でも、クーデターのくだりがありましたけれども、この段階で不正の目的について、片山副知事との間での議論というのはされたんですか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、先ほど申し上げたとおり、公用PCとか、公用メールをある意味調べさせていただく中で、片山副知事からクーデターというような言葉も出てきているということは、たしか3月25日の時点だと思いますけども、そういった報告があったというふうに記憶してますね。詳細までは、もちろん今、増山委員がおっしゃったようなところまで、私はもちろん承知はしてなかったですけども、もしそういった増山委員が説明されたことが事実であるとすれば、職員同士がそういった分断をするような、そういった行為っていうものがあったとすれば大変遺憾だというふうに思ってます。
それがひいては県政全体の土台を揺るがしかねないようなことにつながってたとすれば、大変県政にとってのある意味リスクがあったということだというふうに思いますので、片山副知事はそのあたりを踏まえて私に対して、当時、クーデターという言葉もありましたということを言ったのかもしれないですけど、そのあたりはあの片山副知事の証言が今あるということが今の状況だと思いますね。
○岸口みのる委員
百条委員会の、この委員会で聞き取り調査というのを行っています。12月に入ってから2名の委員が職員に対して聞き取り調査を行ってます。その中で、一つある指摘があります。人事処分についてです
今回、人事処分は四つの非違行為によって構成されているということでしたけれども、これについて、文書の件を外して残り三つだけで処分して、文書の件は公益通報の結果を待って処分すればいいのではないかと提案をした、綱紀委員会ではそれはできないという説明があったということでありますけれども、これは知事はご存じですか。
○証人(齋藤元彦)
そこは存じ上げてません。
○岸口みのる委員
それからもう一つはですね、今回の文書について、文書の配布自体に違法性があるなら続けて調査すればよかったのだが、誹謗中傷性に主眼を置いて対応の方向性を決めてしまったことが最初の問題ではないかと考えているという指摘があります。このことについて知事はどう思われますか。
○証人(齋藤元彦)
もう一度、すみません。
○岸口みのる委員
誹謗中傷性に主眼を置いて、対応の方向性を決めてしまったことがボタンの掛け違いではなかったかというふうな発言があるんですけども、これについては知事は何かご意見ありますか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、今回、ちょっと懲戒処分については、繰り返しになるかもしれないですけど文書の作成、流布以外の三つの非違行為が判明しましたので、これはやはり調査をした結果、認定されましたから、そこは人事当局が手続を経て、今回、懲戒処分として3ヵ月の停職ということにしてますので、そこは全体として私は適切な対応だったというふうに思ってます。
○岸口みのる委員
分かりました。
〇委員長(奥谷謙一)
はい、佐藤委員。
○佐藤良憲委員
今日は総括ということなんですけど、僕、ずっとこの問題って何で起きるんだろうなってずっと考えてきたんですけど、先ほどの知事がこの文書、告発文の中の話で、企業の名前とかいろいろおっしゃってたんですけど、ちょっと僕、ここで一つどうしても疑問に思うのが、この6番のところで優勝パレードの陰でという話があるんですけど、この中である課長が、一連の不正行為と大阪府の難しい調整に○○が持たず、○○を発症して、現在○○○○中。もうこんなこと絶対言ったら駄目だと思うんですよ、ほかの職員のことを。しかも、一連の不正行為って、この人、不正行為してるなんていうことをここに書いてるわけですから、むしろ知事はここを一番怒るべきじゃないかなと思うんですけど、今のお話の中でもここ出てこなかったと思うんですよ。ここに対してはどういうお考えですか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、指摘された課長さんは、たしか資金調達とかではなくて、パレードの運営について、本当に大阪との調整に大変ご尽力いただいたということです。それから、やはり体調を崩されたとかっていうことは、個人情報ですから、それをやはり言及するということ自体も、やはり私は問題があるというふうに思ってます。
○佐藤良憲委員
なので、ここを今先ほど、ほかのメンバーが聞いたときにも、文書のことでご説明されてましたけど、一番最初に僕はここを出して言ってほしい部分だと思うんですけど、ここが何か聞くまで出てこなかったところにちょっと一つ疑問があったのと、あと、今回、先ほど岸口さんも言ってましたけど、聞き取りをしたっていう話をしてたんですけど、正直、知事が選挙される前とされた後で、聞き取りの証言しますって言ってる人がやっぱりしませんとか、変わったりもしてるんですよ。
どうしてもね、知事という立場は職員の皆さん萎縮するので、そこはもう知事もぜひこれからよく気をつけて付き合ってほしいなって思う部分なんですけど。あと、その中でちょっと、知事自身が反省すべきは反省して、これから臨んでいくっていうお話をされてたと思うんですけど、それについてちょっと具体的に教えてもらえますか。知事自身はどこに反省すべき点があって、今後どう改善するのかっていうところ、ちょっとお伺いしたいんですけど。
○証人(齋藤元彦)
先ほどのパレードの担当課長の体調の件については、全ての項目を説明する時間がない中で、具体的なっていうことで一番上の五百旗頭先生の件を説明しましたけども、説明したいということは、議員のご指摘をしっかり受け止めていきたいと思います。すべきということはですね。
それから、反省すべきということで、この間、職員の皆さんに私が不在だった50日間もそうですけども、大変県政については支えていただいたということを感謝をしているということは、私は大前提としてありますし、これからやはり業務上必要なところで注意をさせていただいたりしたっていうのはありましたけども、それとともに、もっと大事なのはやはり職員の皆さんに感謝の気持ちを持って、仕事を一緒にやっていくっていう、やはり風通しのいい職場づくりをしていくということが大事だと思いますし、私自身がもっと言葉でもって、感謝の気持ちを伝えたり、職員の皆さんとのコミュニケーションをしっかりやっていくということがこれからしっかりやっていかなきゃいけない点だというふうに思ってます。
○佐藤良憲委員
私も幾つか既に改善されたという点は知ってる部分もありますので、今の話でよく分かりました。
私は以上です。
○委員長(奥谷謙一)
すみません。時間が経過しておりますので。一旦休憩を挟みたいと思います。10分間休憩したいと思います。再開を4時15分といたします。
休 憩(午後4時3分)
再 開(午後4時15分)
○委員長(奥谷謙一)
それでは委員会を再開いたします。
続いて、公明党さんから。
〇伊藤勝正委員
よろしくお願いいたします。先ほど元副知事にもお伺いしたんですが、まず今回の文書、事実と異なる記述が多いなどなど、いろいろご指摘があるんですけども、そもそもなぜ、私、疑問に思うのが、じゃあ、怪文書として扱ったほうがよかったんじゃないかなと、もう無視してもよかったんじゃないかなと思うんですけども、そうされなかった理由は何でしょうか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、先ほど少し申し上げましたけども、私以外の方も含めて、県職員の実名、企業や団体の実名が挙げられて、これが違法行為に関与しているかのような記述が多々書かれてましたんで、これを放置しておくということはやはりいろんな方への迷惑がかかってくるということで、対応が必要だというふうに判断しました。
〇伊藤勝正委員
この後ちょっと質問するんですけど、この後、職員のメール履歴の調査が始まるわけですけども、その前にそこに出てきている民間企業とか関係者、職員とかに簡単な聞き取りで、もう事実でないっていうのがすぐ分かったんではないかなと、私ふと思うんですが、その確認はすぐされなかったんでしょうか。その出てきてる方に、これは事実かとか、この企業さんに、こういう文書にこう書かれてるけど、どうなんだろうとかいうことは、聞かれなかったんでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、私自身も例えばゴルフアイアンセットをゲットしてるっていうのは、当事者として、明らかにゲットしてないですから、そこは相手に聞くまでもなく、当事者として、これは間違ってるということが分かりますし、それ以外も、ほかの名指しされてる、片山副知事とか含めて確認したところ、事実ではないというふうに確認できましたので、やはりこれは誹謗中傷性の高い文書だということで、対応を進めたということですね。
〇伊藤勝正委員
では、なおのこと21日の時点で無視するという選択肢もあったんじゃないかなと思います。
22日に指示されたあの文書作成に関与したと思われる職員のメール履歴の調査、これ指示されておりますけども、この調査方法を発案されたのは誰ですか。
○証人(齋藤元彦)
たしか21日ですかね、最初の打合せのときにだったと思いますけど、そういった職員がつくられた可能性が高いという話になりましたので、であれば過去の事例とか見ても、そういった場合に公用のメールを確認するっていうことは、可能性としてはあるという話が出ましたということでした。
○伊藤勝正委員
というのを、どなたからこうやりましょうという提案をされたかという質問なんです。
○証人(齋藤元彦)
そこはちょっと記憶にはないですけども、複数の中からこういった方法もあるんじゃないかという話が出たというふうに認識してますね。
○伊藤勝正委員
はい、分かりました。
あとですね、公益通報の議論に移りますけれども、知事は8月7日の会見での、これ元県民局長って保護対象になるんじゃないかという記者質問に対して、3月の時点では外部通報に当たらないとする法的な見解までは有してない。先ほど来出ている。それからそれと合わせて、信じるに足りる相当な理由が存在しないと言われておりますけども、これは今もお変わりないんでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね。真実相当性がないということで、外部通報の保護要件に当たらないというのが私の今の認識です。
○伊藤勝正委員
といいますか、この3月の時点で、そもそも公益通報の議論ってなかったんじゃないかなと思うんですけれども、あったんですか。
○証人(齋藤元彦)
そこは先ほど委員もご指摘いただいたとおり、法的なところまでは検討まではなかったけれども、結果として、やはり外部通報の保護要件には当たらないというところを確認をしてたというところですね。
○伊藤勝正委員
結果としてですよね。ちょっとつながるんですけど、9月6日に私、質問させていただきました。公益通報者保護法の改正内容をご存じですかという質問に対して、詳細までは知らないという証言がありました。その後に知事から、違法性の有無はこれから確認して、必要なら文書で提出しますとおっしゃってます。確認はされたんでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね。やはり文書では提出はまだできてませんけども、内容としては、先ほど委員とのお話の中でも出た真実相当性がないということで、こういう外部通報の保護要件に当たらないということで、今回は誹謗中傷性の高い文書を作成したということで、公益通報したということで処分したのではないということで、そういった文書を作成したことに対する処分だということで、適切な対応だったというふうに考えています。
○伊藤勝正委員
先ほど来、適切っておっしゃってるんですが、12月6日の本会議の答弁で、知事は今後は組織を挙げて必要な措置をしっかり取っていきますという答弁されてる。その割に、ちょっと本当に事実確認とか、改正内容に照らして今回の対応が適切だったかどうか、もう一度聞きますけど、本当に確認されたんですか。
○証人(齋藤元彦)
改正内容を2020年ですか、改正内容までの詳細は承知していないということは申し上げましたが、今2024年ですから、もちろんその改正というものを踏まえて、今の2024年の法律があるので、今の2024年の公益通報者保護法等を踏まえた上で、今回の3月以降の対応については、法的にも含めて問題ないというのが我々の見解ですし、それは県の特別弁護士等の確認でも、やはりそれは今の法律の中で適切だったという見解を得てますから、改正の内容を詳細までを知ってる、知ってないにかかわらず、やはり今の法律の2024年の法律に基づいて、我々は適切に対応してたというのが私の認識ですし、そういった意味で問題ないと思います。
○伊藤勝正委員
分かりました。何回も聞くようで申し訳ないんですが、9月6日に私が質問してから確認されたかどうかという質問なんですけど、それはどうなんでしょう。
○証人(齋藤元彦)
そこは2020年の法改正の内容について、詳細まではまだ確認はしてないというところはありますけども、先ほど申し上げたとおり、2024年の段階ではそこを踏まえた法律の内容になってますから、そこはきちんと法律上も含めて、今回の対応については法的にも適切であったというふうに認識しているという意味では、確認はしています。
○伊藤勝正委員
ということは、私の問いに対しては確認されてないということですね。9月6日以降は。
○証人(齋藤元彦)
ええ。
○伊藤勝正委員
する必要がないという。
○証人(齋藤元彦)
いずれにしましても、先ほど別の委員のほうからありましたとおり、必要があれば文書できちんと提出をするということは検討していきたいと思います。
○委員長(奥谷謙一)
越田委員。
〇越田浩矢委員
はい、ちょっと改めて公益通報に関してお伺いします。
先ほどの結城弁護士の参考人聴取はお聞きになっていたでしょうか。午前中の。
○証人(齋藤元彦)
ライブでは見てません。
〇越田浩矢委員
ちょっと改めてなんですけれども、3月12日に元県民局長がマスコミ等に送付をして、外部通報になるかどうかというところで、知事は20日にご存じになったというところで、公益通報じゃないんだという主張をされてますけれども、改めてなぜ公益通報にならないかをご説明いただけますでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
先ほど来申し上げてますとおり、あの文書については、3月20日時点で把握したときには、内容について私自身のこともそうなんですけど、やっぱり真実でないことが書かれているということ。そしてそういった意味で誹謗中傷性の高い文書だというふうに、まず全体として認識をしていたというところです。
その上で、そこに供述であったりとか、証拠というものも具体的なものが添付されてなかったということです。そして3月25日の元県民局長への聴取以降も、うわさ話を集めて作成しましたという供述を、それをある意味違うと、うわさ話じゃなくてこういったものがあるということを具体的に提出されないまま来てましたので、そういった意味でも外部通報の保護要件には該当しないというのが、私の今の見解でもあります。
〇越田浩矢委員
今おっしゃった理由の中で、証拠がないとか3月25日以降うわさ話を集めたっていうのは、判断する材料としては不適切だと思います。要は文書を見た時点で判断すべきであって、それを後から要は告発者を探索した上で見つけた情報で、今おっしゃってる話だと思いますので、不適切な理由だと思ってます。
最初に言われた真実相当性と誹謗中傷性が高い文書だということで、公益通報じゃないというふうにおっしゃってるんですけれども、結城弁護士がおっしゃったのは、まず公益通報かどうかの判定として、真実相当性は要らないとおっしゃってます。
公益通報者保護法第2条に書いてある6項目を満たしていれば、公益通報として扱うべきであって、真実相当性は保護要件として働くんだということでありますので、まずは公益通報として認識すべきだったということであろうと思うんですけれども、その点はどのようにお考えでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
私があの文書を見たときに、あの内容からですね、これは全体としてやはり誹謗中傷性の高い文書だと、これは個人や団体の実名が挙げられている中で、違法性に関与したかのようなことがるる書かれているということで、やはりこれは誹謗中傷性が高い文書だというふうに判断しているということですね。
〇越田浩矢委員
じゃあ真実相当性は、今の証言だと関係ないということをお認めいただけるということでよろしいんでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
そこに客観的な証拠、それから供述がなかったということですし、それから3月25日でも、うわさ話を集めてつくったという供述がありましたので、これはその後も変わることがなかったということですから、これは外部通報の保護要件に当たらないというのが私の見解であります。
〇越田浩矢委員
客観的証拠は、多分、文書作成時点、通知時点では必要ないというふうに言われております。誹謗中傷性についても、これ百条委員会の中で、総務部長と県民生活部長が県警に行って文書を見せて、これ名誉毀損になるのかというご相談をしているという中で、これは名誉毀損として受理できないという結論も出ているかと思うんですけれども、そういった意味においては誹謗中傷性も、そこまでの名誉毀損に当たるような文書ではないということが、もう既に明らかになってます。
ということからするとですね、真実相当性が公益通報となる要件ではない。更に誹謗中傷性もないということがある意味証明されている。この百条委員会の中で証明されている事実だというふうに認識しているんですけれども、それでも公益通報に当たらないということは言えないというふうに思ってるんですが、いかがでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
それは委員の見解は様々あると思いますけども、警察が受理する、しないというのはあくまで警察の判断で、こちらとしては誹謗中傷性がある文書だというふうに判断してますから、その上で、先ほど申し上げたとおり真実相当性を満たす供述、証拠、それからうわさ話を集めたものではないというところが欠けてましたので、外部通報としての保護要件に当たらないというのが、私の認識です。
〇越田浩矢委員
真実相当性に関しては、百条委員会の中で様々な証言を得られております。
その中で例えばパワハラに関していうと、業務に必要な範囲の指導とは思わなかった、理不尽な叱責を受けたと感じているとの証言ですとか、県職員になって、これまでにないというぐらいの叱責を受けたという証言ですとか、自分の部下のいるところで大声で怒られており、指導の域を超えたパワハラだったと思ったというような証言が出ております。
これはもう、明らかに社会通念上一定レベルを越えた叱責があったということで、知事自身も大きい声で厳しく注意したことで、職員が不快に思われたのであれば反省し、機会があれば本人に直接おわびしたいというような証言もなされております。
さらにチャットでの時間外、休日における指示もたくさんあったという証言もありましたし、コーヒーメーカーの件は告発の内容どおり、県庁内にこのコーヒーメーカーが保管されていたという事実が明らかになっており、県として外形的には受領しているという状態であったという事実も分かっております。
政治資金のパーティーの件については、今日議論にもなっておりましたけれども、信用保証協会の理事長名の名刺を持って、パーティー券の購入依頼に行ってるというような状況も明らかになっているということからするとですね、7項目のところで全く真実相当性がないと言い切れることではないということが、この百条委員会でも明らかになっていると思うんですが、それでも真実相当性がないというふうにおっしゃるんでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね。一つ一つのコーヒーメーカーとかについて反論するということは、時間の関係もありますけども、コーヒーメーカー自体も私は一切使ってもないですし、受け取ってもないということです。それ以外にもやはり事実でないことが多々書いていた。そして公益通報については、パワーハラスメントがその対象になるのかどうかという議論もあると思います。
いずれにしましても、先ほど来申し上げましたとおり、私があの文書を把握した時点での状況を見ますと、真実相当性はないというふうに私は考えています。
〇越田浩矢委員
これ法解釈の問題でもありますので、ただこれ可能性としては、やっぱり公益通報者保護法違反の可能性があって、そういう指摘が様々なされている中で、更に言うと専門家、今回参考人で呼んだ3名の方は、3名とも基本的にはこれは法律に反しているんではないかという指摘もいただいております。
そういったことからするとですね、やはり誹謗中傷性が高くて真実相当性がないから、公益通報じゃないんだと言い切ってしまうのは、県のトップとしてやっぱりふさわしくなくて、もう少し慎重に公益通報、内部通報の制度の趣旨からすると、いろんな不正を内部でしっかり酌み取って改革していきましょう、よくしていきましょうという制度の趣旨からすると、誹謗中傷性が高いから、探索していいんだというスタンスではなくて、しっかりと受け止めて事実かどうかを調査した上で判断していくというのが、本来の県としての在り方ではないかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
そういった指摘もあろうかと思いますけど、一方で別の観点から今回について対応に問題はないと、真実相当性含めて公益通報に当たらないという専門家の方、弁護士の方もおられるということだと思います。
先ほど、増山委員がおっしゃったクーデター云々という指摘もあるとすれば、不正目的であったりとか、そういうことも勘案して、我々としては真実相当性がないということを今申し上げてますけども、その辺りを含めて判断していくということが大事だと思っています。
〇越田浩矢委員
今、不正目的ということをおっしゃいましたけれども、人事当局の証言として、不正な目的であったというふうに、明確に内部で判断したということはないですという証言があります。知事としても不正な目的の文書であったという判断はされてないということでよろしいでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
片山副知事からの3月末頃のときに、クーデターという言葉を私も聞きましたので、これ
は本当の話じゃないなということは、私自身は認識はしていました。
〇越田浩矢委員
不正な目的をもし法的に争うんであれば、県側がそれを立証する責任がありますし、不正な目的は、そう簡単に法律的には専らという文言がない要件だというふうに、先ほどの参考人の話もありましたので、非常にそこは論点になるところかなと思うんですけれども、とはいえ公益通報者保護法に違反している可能性があるという時点で、非常にゆゆしき状況に今あるというふうに思っておりますので、いろんな体制の義務も法定指針で定められている中で、しっかりこの状態を見直す、県としてもその体制整備の不備もたくさんあろうかという状態だと思ってますので、見直していただきたいなというふうに思っております。
あと1点だけ、まとめさせてもらう。あと情報漏えいに関してなんですけれども、これ、元総務部長が情報漏えいしてるんじゃないかと、週刊文春の記事になりました。これ7月の時点で藤原弁護士に相談をしてまして、第三者委員会を立ち上げて調査しましょうというふうな話になっている記録が提出されております。
そこから、もう半年近くたっている状態でありますけれども、第三者委員会を立ち上げるという中で、まず客観性を担保し調査をされてるんだと思うんですけど、どういう体制で誰に頼んでるのかって分からないですし、これを今後どういう形で公表して、発表していくのかという道筋とかですね、どういう調査状況にあるのかというところを、ちょっとお聞かせいただけますでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
その辺りは、今、担当部局のほうで7月以降報道がなされた後に、弁護士にご依頼をして調査を今進めているということは報告として受けています。
これがどのような形で進められていくかとか、今後どのようになるか、どういうメンバーかということも含めて、担当部局のほうで今対応をしているというところですので、今、私はちょっと手元に資料等がございませんので、また追ってそこは説明できるものは説明させていただくということだと思います。
〇越田浩矢委員
その後の情報漏えい、総務部長の話だけではなくて、今回、立花氏を通じて情報が漏えいしているとかですね、そのあとの続きがあるような状況でありますので、早急に調査をして、もし本当に情報漏えいしてるんであれば、その漏えいを削除要請するなり、県としてしっかり対応していく必要もあると思いますので、しっかりこの漏えい問題に対応していただきたいと要望しておきます。
○委員長(奥谷謙一)
県民連合、上野委員。
○上野英一委員
まずパワハラ体質について伺います。
選挙中の知事の演説をYouTubeで見てみますと、知事はパワハラは行っていない、20メートル歩かされて怒ったりしませんよというふうに述べられています。また、これは選挙中の話ではないんですが、先ほども越田委員が言いましたけれども、もしも私の言動で不快な思いをさせたことがあったならば謝罪をしたいというような、そういう発言もされていますが、それだけを見れば、パワハラはやってないですよというふうにおっしゃってるように聞こえるんですが、その点についていかがですか。
○証人(齋藤元彦)
東播磨県民局における私が注意をしたということについては、20メートル歩かされたことで怒ったんではないですと、円滑な動線をしっかり確保できてなかったということに対して、私は当時の認識で注意をさせていただいたということでありました。それを述べさせていただいたというところです。
厳しく注意や指導を業務上必要な範囲でさせていただくということはありました。これはあくまで、いい県政を進めていきたいという思いでさせていただいたということです。ただ、社会通念上の範囲を度を越えて、暴行罪などに該当するようなことはしてないという意味で、私としては発言をしたということですね。
○上野英一委員
たしか公益通報制度の中で、いわゆる刑事事件に相当するようなパワハラではなかった
ら、綱紀委員会としては扱わないという、そういうふうな情報があるかと思うんですが、そ
ういう意味で、知事はそこまではやってないという意味での今の発言ですか。
○証人(齋藤元彦)
いずれにしても、業務上必要な範囲で指導や注意をさせていただいたということはあります。これは特には厳しく強くさせていただいたこともありますけども、これがハラスメントに認定されるかどうかということは、最終的には司法の場の判断にもなるかと思いますけど、私としては業務上の必要な範囲で指導等をさせていただいたというスタンスではいます。
○上野英一委員
知事は再選後ですね、職員との信頼回復をしていきたいというふうに述べられておりますし、そのことには期待をしたいというふうに思うんですが、私は信頼回復を行おうと思えば、かなり知事が謙虚にこの自分はパワハラ体質があるというふうなことを認識されんと、なかなか難しいんではないかなというふうに思うわけです。
それでその20メートルの話ですが、確かに動線の確保ができていないというふうに、ぱっと行ったら見えるというふうに思うんです。しかし、そこで動線の確保ができてないからということで、かなり厳しく叱責をされて、業務の範囲の指導やというふうにおっしゃいましたけれども、私なら仮に動線の確保ができていないというふうに思ったとしても、その場では指導しないで会議が終わった後で、なぜあそこに車止めが置いてあったのかというふうに聞けば、ほとんど怒るような必要性もなかったん違うかなというふうに思うわけです。
そういうことで、知事はある意味3月27日の記者会見もそうですが、あのときはかなり激しい口調でおっしゃってましたけども、知事の体質の中にいわゆるすぐに激高する、あるいは切れるというような、そういうふうな体質があって、それが全ての原因となっとうように私には思えてならないんですが、そういう認識についてどう思われますか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね。やはり県職員の皆さんも一生懸命やっていただいてるという感謝の気持ちをしっかり持っていきたいというふうに、これからも思っています。
その上で、業務の中で必要な指導であったりとか注意というものは、やはりこれは県政をよくしていきたい、いいパフォーマンスを発揮していきたいという意味で、私もさせていただいたりしてるということがありますけども、そういったやり方については、いろんな方法があるという委員のご指摘だと思いますので、そこは真摯に受け止めて、これからやはり新たに県政を進めさせていただく上で、職員の皆さんと一緒になっていい仕事ができるような、風通しのよい環境づくりをしていきたいと思っています。
○上野英一委員
大いに、その辺りについては期待をしたいなと思います。職員に対して感謝の気持ちを持つということがどういうことなんかということを、改めて認識していただきたいなというふうに思います。
次に、公益通報者保護法、今、越田委員も言われてましたけども、私自身も公益通報者保護法違反やなというふうに考えているわけですが、その中で得た個人情報の漏えいについて、とんでもないことではないかなというふうに思うんです。いわゆる行政として秘密の保持は、最重要事項やというふうに考えるわけですが、その認識について知事のお考えをお伺いしたいと思います。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、やはり県であったりとか、行政機関が職務の中で保有した情報の取扱については、適切にやっていくということが大事だと思っています。
○上野英一委員
私たちの調査では、4月初旬から中旬にかけて、元総務部長が複数の女性職員や県議に見せて回ったというふうな証言があります。週刊文春にもそのような報道がありました。それに対して知事は、そのことをいつ認識されてどのように対応されたか教えてください。
○証人(齋藤元彦)
私は最初、週刊誌の報道で、そういった内容を把握したということです。本人も含めて内容を確認したら、そういったことはしてませんということをおっしゃってました。その後、先ほども話が出ましたけれども、弁護士のほうに調査をお願いしているというところですね。
○上野英一委員
従来から、本人にも確認したけども、本人はそういうことをやってないということで、職員を信じたというふうに、そういう答弁やと思うんですが、私は随分この告発文書のときの扱いと、異なり過ぎる対応ではないかなというふうに思います。
違法な調査で取得した個人情報漏えい問題は、元総務部長が漏えいしたことは事実でありますし、4月の初旬、中旬の話ですよね。県民の個人情報を扱う総務部のトップが漏えいしてるんですよね。県としての信用、一番守らなければならない個人情報保護ですよ。今もう既に12月です。
知事は第三者委員会の設置を検討してと言っていらっしゃいますが、トップとしての認識、ちょっとあまりにも認識度合いが、私は低いんではないかなというふうに思うんですがいかがですか。
○証人(齋藤元彦)
元総務部長の行為が、どのようなことをしてたかということをも含めてですね、これやはり慎重にしっかり確認をしていくということが大事だと思います。
そういった意味で、弁護士に調査をお願いしているというところでございますので、現時点で何かやったかとかという断定をするということが、適切なのかどうかというのがありますけども、やはりそこは弁護士を入れた中でしっかりと事実関係を調査していくということが、私としては大事だというふうに思ってます。
○上野英一委員
私は本来でしたら、それこそ今も言いましたように、総務部のトップがそういうことを行ってるんですから、知事は適切にすぐに刑事告発する立場にあるんではないかなと思うんですが、その点についてはいかがですか。
○証人(齋藤元彦)
今進められてる弁護士を含めた調査を、しっかり進めていくということが大事だというふうに思ってますし、今後、県保有文書の問題についても、第三者委員会の立ち上げを今準備してますから、そこで事実関係を調査しながら適切に対応していくということが大事だと思っています。
○上野英一委員
私からは、次、代わります。
○委員長(奥谷謙一)
それでは、北上委員。
○北上あきひと委員
3月21日、文書問題の取扱をめぐって、知事と幹部職員4人が会合を持たれています。改めてそのことについてお伺いします。
知事はですね、徹底した調査を指示されているわけでありますが、徹底した調査というのは事実関係も含めて内容の調査を求めたのか。あるいは誹謗中傷の文書なので、誰がどのような目的で出した文書なのか、そのことを調べろというふうに指示されたのか。その辺はいかがですか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、3月20日前後に文書を把握して、内容が先ほど申し上げたとおりですけども、個人名や団体名が出て、誹謗中傷性高い文書と認識しましたから、やはりこれは県職員の方がつくった可能性があるという話にもなりましたので、しっかりやっぱりここはどなたがつくったのかということを調査する、調べるということは大事だというふうな話合いの中で、しっかり調査をしてほしいということを私から指示をしたということですね。
○北上あきひと委員
文書問題の取扱をめぐる会合、あるいは実際調査に当たられた方、これらが告発文書で、不正の疑惑をかけられている職員であります。そのことについて私は不適切ではないかと思うんですが、その辺の認識はいかがですか。
○証人(齋藤元彦)
最初の3月21日からの段階では、片山副知事も元県民局長の事情聴取などに対応したということです。これは先ほど申し上げた誹謗中傷性の高い文書をつくって、やっぱり流布される可能性が高いですから、早く対応するという必要がある中で、そういった対応をしたということです。
4月以降については、元県民局長の文書に関しての人事課の内部調査については、片山前副知事や元総務部長など、当事者、私も含めてそこは関与してないということですね。
○北上あきひと委員
改めてお聞きしますが、この不正の目的ということをおっしゃってますが、このことを認識されたのはいつのタイミングですか。
○証人(齋藤元彦)
3月25日だったと思いますけども、片山副知事からだったと思いますが、クーデターという言葉も出てますというふうな話を聞いたということが私の認識ですね。
○北上あきひと委員
それで告発文書について、事実無根などと発言をされていますが、この意味は事実でない部分があるということなのか。真実、事実が全くない、そういう文書なのか。その辺はどのように認識されているでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
当時から申し上げているとおり、核心的な部分ということで、例えば、商工会に訪問したということは事実ですけども、ただ、そこで次の知事選挙の投票依頼したということは全くありませんので、そういった意味でも、そういった文書が意図してるような、本当に重要なポイントが事実と異なるという意味で申し上げています。
○北上あきひと委員
先ほどから指摘があるように、パワハラかどうかということは判断があるかと思うんですけれども、社会通念上ですね、相当の範囲を超えた叱責であるとか、厳しい口調などですね、そういうことが明らかになっていますし、物品の受領につきましても、利害関係者から受け取った。あるいは無償貸与を受けたという事実が明らかになっていますが、それでも核心的な部分は事実ではないというふうにおっしゃるのはなぜですか。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、強く指導をさせていただいたり、注意したということがありますけども、20メートル歩いただけで、歩いたことをもって注意したわけでもないですし、その中で、暴行罪やそういった傷害に当たるような、社会通念上度を越えて極端なことをしたということではないです。
ここはハラスメントについては、客観的な認定がされるものだというふうに思ってますし、物品の受領についても、あたかも私が使ってもないのにゲットしたとかですね、そういったことが明確な証拠や供述もない中で書かれてた文書だというふうに今も考えてますので、そういった意味でも誹謗中傷性の高い文書だというふうに考えています。
○北上あきひと委員
先ほどからですね、真実相当性は認められないので、保護要件は満たしていないというふ
うに発言されていると思うんですが、公益通報に該当するが、保護要件は満たしていないと
いうことなのか。そもそも公益通報に該当しないという認識のもとで、一連の対応をされて
きたのか。いかがですか。
○証人(齋藤元彦)
そこは、まずは3月の時点で判断したものとしては、誹謗中傷性の高い文書だということ
で対応したということです。その後、真実相当性というものが処分まで確認されませんでし
たので、公益通報の保護要件には該当しないというふうに認識してます。
○北上あきひと委員
保護要件に該当しないということは分かりました。公益通報に該当しないという判断のも
とで、一連の対応をされてきたのかどうかはいかがですか。
○証人(齋藤元彦)
そこは繰り返しになりますけども、当時、法的な見解までは有してなかったですけども、結果として真実相当性を有しないということの判断ができましたし、そもそもが誹謗中傷性の高い文書だと、それを職務中に業務端末でつくったということを含めて、四つの行為をもって懲戒処分をさせていただいたということです。
○北上あきひと委員
ということは、一連の対応は公益通報に該当しないという認識のもとで進められてきたということですか。
○証人(齋藤元彦)
公益通報の保護対象には当たらないということで、適切に対応してきたというところです。
○北上あきひと委員
保護対象に該当しないということは分かりました。そもそも公益通報に該当するかどうか
という認識をお聞きしています。
○証人(齋藤元彦)
そこは我々としてはちょっと繰り返しになりますけども、誹謗中傷性の高い文書だったということで、今回公益通報をしたことに対して処分ではなくて、誹謗中傷性の高い文書を作成したことに対する処分をしたということです。
○委員長(奥谷謙一)
そろそろまとめてください。
○北上あきひと委員
上野委員からもありましたが、一連の調査の中で、県が保持した個人情報が漏えいしたということがあります。このことについては、今も拡散が続いているということであります。
私は刑事告発するべきだと、それがやはり県民の膨大な個人情報を預かる県知事としての責務だというふうに思います。刑事告発をされるべきだと思いますが、いかがですか。
○証人(齋藤元彦)
はい。県保有文書の問題については、今指摘されている面については、その文書の同一性を含めて、弁護士など客観的に調査を確認してもらう必要がありますので、早急に第三者委員会の立ち上げに向けて今準備をしているところです。そこでしっかりと調査をして適切に対応していきたいというふうに考えています。
○北上あきひと委員
職員が漏えいしたという可能性もありますし、外部からの不正なアクセスということもありますし、間違いなく個人情報の漏えい、あるいは虚偽の情報拡散によって、県の名誉を著しく傷つけているという側面があって、第三者委員会とかというレベルではなく、速やかな刑事告発をすることが、私はやっぱり県民の個人情報を預かる県の知事としての責務だというふうに思いますが、改めて見解をお伺いします。
○証人(齋藤元彦)
繰り返しなりますけども、今、第三者委員会の立ち上げに向けて準備を早急にしてますので、そこでしっかり調査をしていただいて、適切に対応していきたいというふうに考えています。
○委員長(奥谷謙一)
それでは共産党、庄本委員お願いします。
○庄本えつこ委員
財務部が4月4日に受理した職員の公益通報事案についての調査結果の概要が示されました。パワハラや贈答品については、是正措置等の要請を知事自ら発表されました。
これは県民局長の通報、3月12日の通報によるもので、知事が3月20日に受け取ったとされる告発文書とほぼ同じ内容の物でございます。これまで何人かもおっしゃってますけど、百条委員会でも例えば考古博物館前での叱責、これは本当に強い叱責で、当事者は頭が真っ白になるほどの理不尽な叱責だったという証言もありますし、ロードバイクの無償提供などの問題も確認されています。
これらの事実から、告発文には真実相当性、公益性が見られ、知事が3月27日の記者会見で、告発文に対し事実無根、うそ八百と発したことは誤りだったということが確認できておりますけれども、今の時点で知事の認識を改めて伺います。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、4月4日になされたとされる公益通報について、是正措置がありまして、物品の受領や、研修制度、外部通報窓口化という是正措置が出ましたので、そこはしっかりと対応していきたいというふうに思ってます。
一方で、公益通報、内部通報された4月4日の内容というものは、原則としてどういったものが通報されたということは、行政内部も含めて非公表という形になってますので、そういった事実もあるということです。
それから、県の公益通報制度と公益通報者保護法の対象というものは、若干異なるものでございまして、県の公益通報制度というものは法律よりも広いものが対象になってますので、それは県政をよりよく推進していくために、是正措置を講ずるということもありますから、そこで一定の是正措置を講じられたということが、3月の文書がどういうふうに扱われるかということについては、最初に申し上げた、そもそも4月4日の公益通報がどういったものが通報されたということが明らかになってないということと、公益通報者保護法と県の公益通報制度の対象の違いなどを踏まえると、そこは一概につながるものではないというふうな認識が、一般的には言えると思います。
○庄本えつこ委員
私たち3回も参考人の方に、専門家からいろいろお話も勉強もしましたけれども、共通して3月12日の告発文そのものは、2号、3号に該当し、27日に直接人事異動の通知のときに、事実をきちんと確認してほしいという本人からの申出については、もう1号だと、それはそのとおりだというふうに、お三方ともおっしゃっていますので、それを踏まえた上で3月20日に知事が受け取った告発文を、初動で公益通報として扱わないでうそ八百と決めつけた、告発者探しを命じたことが、片山副知事をはじめ県人事課などによる違法的な調査が行われ、関係のない個人情報の流出など、その後の混乱につながったと思っています。
知事は初動の対応がこの大きな混乱を引き起こしたという、知事としての責任を自覚することが必要だと思いますが、いかがですか。
○証人(齋藤元彦)
3月の文書発覚後の対応については、先ほど来申し上げているとおり、繰り返しになりますけども、初動の対応を含めて適切に対応してきたというふうに考えています。
○庄本えつこ委員
今の時点でも適切だというふうな認識だということですね。
○証人(齋藤元彦)
はい。
○庄本えつこ委員
それでは、パワハラの問題なんですけれども、上野委員もおっしゃってましたけど、選挙中には知事はパワハラはなかったと、ご自分の言葉でおっしゃっています。明言されていました。
しかし、私たち百条委員会の場では、パワハラかどうかを判断されるのが百条委員会の場であるという、そういう発言をされています。つまり選挙中の自身の言明と百条委員会の証言は矛盾しています。この百条委員会での知事の発言というのは虚偽ですか。
つまり百条委員会でパワハラかどうかは判断されるのに、ということをおっしゃってるのに、選挙中にはパワハラはなかったというふうに、ご自分で言ってるということはそごがありますので、そのことについての質問です。
○証人(齋藤元彦)
最終的にパワーハラスメントかどうかというのが認定されるのは、司法の場などだというふうに思ってます。私としては東播磨県民局の件についても、先ほど上野委員のご質問にお答えしたとおり、20メートル歩かされて怒ったという意味ではないということと、やはり指摘されてたような過度な、社会通念上の度を越えていたことはないという意味で、暴行罪であったりとか、そういった意味での行動はしてないという意味で、そういった発言をさせていただいたという趣旨です。
○委員長(奥谷謙一)
そろそろ締めてください。
○庄本えつこ委員
パワハラというのは暴行とか傷害ではなかったということではなく、例えば、部下の前で上司が叱責されるとか、それも強い口調で、強い口調じゃなかったとしても、そういうこともパワハラなんです。だから暴行や傷害、社会通念上度を越したということではなく、今でもつまり知事は強い口調で言ったこともあるけれども、それはパワハラではなかったというご自身の認識ですか。
○証人(齋藤元彦)
私としては、業務上必要な範囲で必要な指導はさせていただいたということです。社会通念上の度を越えた暴行罪のようなことまではしてないという認識ではいますけども、しっかりと風通しのよい職場づくりに向けて自分自身の言動についても、これからしっかりと対応していきたいと思っています。
○委員長(奥谷謙一)
よろしいですか。では丸尾委員。
○丸尾まき委員
先に、ここにいる全員が賛成して実施した県職員アンケートがありました。私も同じ形式、記名・無記名の選択式で、事実確認はできていないということで明記をして実施をした。参考になるものもありましたし、参考にならないものもあったということで、そういうことも含めていろいろ調べた中で、公益通報について質問したいと思いますが、2人の証人尋問などから、4月5日、総務部長、理事が知事協議に入り、内部公益通報の調査結果が出るまで処分を待つスケジュールが手渡されて、2人は知事が了解したというふうに受け止めています。
2人の話を聞く前は、知事は2人の話は記憶がないとしているんですが、4月から5月末までに公益通報のスケジュールが記載された、そういう資料を手渡されたことは覚えていますか。
○証人(齋藤元彦)
全く覚えてないですね。
○丸尾まき委員
2人ともに知事が了解したと受け止めているんですが、どのように記憶されてますか。
○証人(齋藤元彦)
調査というものが、内部調査が一定時間かかったりするという話は聞いたことがあるというふうに記憶してますけども、公益通報を待って対応すべきだったとか、そういった進言は受けた記憶は全くないです。
むしろ、先ほども申し上げましたけれども、公益通報が何がなされたかとか、特に内部通報については、原則として行政内部では共有されないということになってますから、論理的にも公益通報の結果を待ってということをすると、そういった処分も含めた対応ができなくなる状況が続くというふうに思いますので、そういった対応がそもそもできないということの中で、私としてはやはり県の当局からも聞いてましたけども、調査の結果、懲戒処分に該当するような非違行為が判明した場合には、やはりそこはきちんと処分を適切に手続に則ってしていくということが、人事行政としての対応だということを伝えられてましたし、それは5月の人事当局の懲戒処分の発表に当たっても、そういったことは申し上げてたというふうに思っています。
○丸尾まき委員
4月15日、元総務部長井ノ本さんによると、知事が元総務部長に先ほどありました風向きを変えたいと言って、元総務部長はそれを指示と受け止めたと。人事課は公益通報を待たずに処分をと受け止めたんですが、知事は総務部長にその風向きを変えたいというやり取りしたときに、井ノ本さんに伝えた内容というのを覚えてますか。
○証人(齋藤元彦)
私はそういった風向きを変えたいというような発言をしたという記憶は全くないです。やはり調査の結果、非違行為、懲戒処分に該当する行為が判明すれば、人事行政として手続に則って処分をしていくというのが、自然な流れだということだというふうに思ってます。
○丸尾まき委員
井ノ本さんの証言ですけど、その後も知事は、井ノ本総務部長に風向きを変えたいと何度も言って、いつぐらいにしたらいいだろうと、その処分を総務部長の井ノ本さんに相談をしているというふうに言われてますが、覚えていますか。
○証人(齋藤元彦)
調査をしながら認定された場合には、手続を経て綱紀委員会等を経て調査、処分をしていくということになりますので、もちろんその処分の時期というものはどのようにしていくかということは、多分相談もあったと思いますけども、何かを待ってとか、何かを踏まえてとか、公益通報の結果を待ってとか、そういった進言を受けた記憶は全くないですし、人事行政としては非違行為が判明した以上、きちんと手続をして処分をしていくということが当然であるというふうな進言も受けてました。
○丸尾まき委員
総務部長や人事課が、結果として公益通報を待たずに処分を、あるいは処分を急げというふうに受け止めてるんですが、そのことについてどのように考えていますか。
○証人(齋藤元彦)
懲戒処分というものはご案内のとおり、規程に基づいて綱紀委員会も含めた手続を経て、内容、手続とともにやっていくというのが原則になります。これは人事委員会や訴訟にもなり得るということですから、内容、手続ともに適切にやっていくということが当然ですので、何かを待ったり、何かを急がしたり、何かの手続を抜いたりしてやるということは基本的にはないですし、規程等に基づいて適切に対応していくという結果、5月7日になったということだと思います。
○丸尾まき委員
総務部長は、具体的に懲戒処分をする日を知事と協議をして、懲戒処分の日が相談するごとに早まっていると、懲戒処分の日程を具体に井ノ本さんと協議したことは覚えておられますか。
○証人(齋藤元彦)
処分の発表日をどのようなタイミングでするかということは、恐らく協議をしたり話をしたという記憶は、報告があったということはあると思いますけども、それは何か急がせたりとか、手続を抜いてやるというような指導、指示をしたことは一切ないですし、人事課のほうが適切な手続に基づいて5月7日に対応したということです。
○丸尾まき委員
井ノ本さんは、4月17日に24日に処分ができないかと指示があって、井ノ本さんからですね、24日に処分できないかという職員への指示ですね。5月17日案を提示して5月10日、17日案を提示し、24日に井ノ本総務部長から5月7日に処分日が決定されたと、これは職員とのやり取りですね。井ノ本総務部長は、逐次、知事に伝えていたと証言してますが、そのやり取りは覚えていますか。
○証人(齋藤元彦)
詳細は覚えてはないですけども、処分のタイミング、発表のタイミングをどのようにするかという相談、報告はあったと記憶をしています。
○丸尾まき委員
総務部長はですね、5月7日にしたのはもう知事しか分からないと思うんですけど、その中で一番早い日を選ばれたという思いはありますという証言をしてます。なぜ5月7日にしたんでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
そこは5月7日にするということも含めて、最終的には総務部長含めた人事当局の中で、適切な手続をしてやれるタイミングで処分をして発表するということを決めたと、それを私自身も報告を受けたということです。
○委員長(奥谷謙一)
そろそろまとめてください。
○丸尾まき委員
先ほどの公益通報の手続が5月末で終わるような予定で出されてるんですが、5月7日に懲戒処分を決めたというのは、それよりも先にやはり判断を出そうというような意図があったんではないでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
そういう意図はないと私は認識してます。あくまでこれは公益通報の調査を待つ、待たないというよりも、人事課が内部調査をして内容認定を経て手続をしたという、適切なタイミングでやっていたということだと思います。
○丸尾まき委員
最後ですね、最後に片山元副知事にも聞いたんですが、関係者からの話として、県民局長のUSBデータがPCに入ってたということが言われてます。それはPCデータ、その後だからPCデータを職員のPCに移したときに、タイムスタンプがついたというふうに聞いてるんですが、そのUSBデータが県民局長のPCに入ってたのはご存じでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
分からないですし、知らないです。
○丸尾まき委員
分からない。もう一点最後に。先ほどあった個人情報の漏えいの話ですね、刑事告発をすべきだという意見の中で、具体的なことは知事はお答えになられなかったですが、その刑事告発、第三者委員会の判断が出たときに、刑事告発も選択肢に入るというふうにお考えですか。入るか、入らないか。
○証人(齋藤元彦)
そこも含めて、そこは第三者委員会をこれから早急に立ち上げをしていくという中で、調査をしながら、どのような対応をするかということは考えていくということだと思います。
○委員長(奥谷謙一)
それでは簡潔に、松本委員。
○松本裕一委員
簡潔にちょっと三つほど伺います。
まず3月20日に知事は文書を入手されたと、民間の方から入手されたということですけれども、今日は公開の場ですので、個人情報があるからということだと思いますけども、この方はいつどこからこの文書を入手したというのは聞かれていますでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
それは知らないです。
○松本裕一委員
どういった形でこの文書を渡されたということですか。
○証人(齋藤元彦)
データとしていただいたということですね。
○松本裕一委員
その方が、その文書をデータとして誰かから入手したということですか。
○証人(齋藤元彦)
データというか、そうですね、いただいたということです。
○松本裕一委員
知事は入手経路等はご存じないということですね。
○証人(齋藤元彦)
はい。
○松本裕一委員
分かりました。
それから退職保留について伺いますけども、この退職保留に関しては、これまでの証言の中で、片山副知事の進言やったかな、というところから退職保留することになったと思うんですけども、これ退職保留をすると、当然それ以降の給料も発生するわけですし、これ後に処分する方法、退職金減額等できたかと思うんですけども、この辺りのその進言されたときに、幾つか方法があってというような説明を受けたのか。退職保留しないと人事権が及ばないという説明だけを受けたのか。どちらでしょうか。
○証人(齋藤元彦)
恐らく退職保留をすることによって、懲戒処分に該当する可能性が高かったので、その後の調査をしていく意味でも、退職保留にするということがいいという話を受けて、それで了承したというふうに記憶してます。
○松本裕一委員
いいという進言を受けて、知事が受け入れたという理解でよろしいですね。
○証人(齋藤元彦)
そうですね。退職保留はそういった意味で受け入れたということです。
○松本裕一委員
分かりました。
次に、先ほどから公益通報者保護についていろいろ議論がされてますけども、これは一定、今結論が出ることではない中で、ただ知事は先ほど現行法に基づいて判断をしたと。現行法によりますと、保護要件に該当しない場合でも、体制整備義務の中でやはり探索は禁止されてるんです。
まずそこは押さえておいていただきたいということと、一旦それも置いておいて、一般論としてのお話になるんですけども、通常、県には誹謗中傷の文書も含めて、いろんな告発であるとか、意見であるとかいうのが、メールであったりとか、文書で届くというふうに思います。年間にすると100で利かないような、100、200、300そういったものが届くと思うんですけども、通常そういった場合でも、通報者の探索はしないのが普通だというふうに認識をしています。
それは二つ理由があって、一つはそもそも匿名の文書に関して、よっぽど具体的に書かれていないと特定がしにくいということがまず1点。もう一点は、その通報が公益通報に当たるかどうか分からないもの、当たるかもしれないもの、当たらないもの、どちらにしてもそこでリスクを取って、わざわざ特定することを行政は一般的にしないというふうな考え方ということを、県の中で長く人事労務に関わった人がそういう証言をされてます。
では、なぜ今回このような通報者の特定から入ったのかとなったときに、それはやっぱりトップダウンで指示が来たからというような指摘があります。なおかつ、それは告発文に書かれている当事者の方の指示によってこれが行われた。これは公益通報とは別に、これを権力者としてそういった指示を出すことが、そもそも問題やという指摘があるんですけども、この件に関しては知事はどのように今認識されてますか。
○証人(齋藤元彦)
3月20日に把握した時点で、あの文書の内容を見たときに、やはり私もそうですけど、先ほど来申し上げさせていただいてますが、県職員であったりとか、企業や団体の実名が出てた。そして名誉を傷つける内容が書かれてた。職員の方の体調に関するプライバシーのことも明記されたということで、これはやはり看過できる状況ではないと。
これがSNS等で広がることによっての影響もあったということで、やはり誹謗中傷性の高い文書だというふうに判断しましたから、やはりこれが職員の内部の方がつくったという可能性が高いというふうに推定される中で、やはり対応としてはどなたがつくったということを調べさせていただいて、その過程でパソコンの中に四つの非違行為に結び付くものがありましたので、懲戒処分をさせていただいたということです。
○松本裕一委員
懲戒処分の話は別だと思うんですけども、これ通報者を特定していないと、例えばこれの拡散とかが止まらないというふうに考えたということですか。
○証人(齋藤元彦)
やはり影響が大きく出る内容だというふうに判断しましたから、やはりどなたが作成したのかということを含めて、しっかりと調査をするということが大事だというふうに判断しました。
○松本裕一委員
一定通報者を特定したとしても、それをいわゆる範囲外で共有する必要があったのかどうかについて、知事の認識を教えていただいていいですか。
○証人(齋藤元彦)
通報者の特定ではなくて、誹謗中傷性の高い文書をつくった方がどなたかということを調べさせていただいたということです。
○松本裕一委員
だから、それを公表せずに拡散を止めていくという方法もあったかと思うんですけども、これをいわゆる会見の中で公表されたわけですけども、その必要性があったのかどうか。これ公益通報とは関係ない観点であったのかどうかという観点で、ちょっとご認識をお伺いしたいと思いです。
○証人(齋藤元彦)
県の幹部に関する人事になりますので、人事課が一定発表するということになります。その後に開かれた会見の中で聞かれましたので、あの文書の内容の影響度を含めて、私のほうから説明をさせていただいたというところです。
○松本裕一委員
最後です。
これ一般論として、これ県庁で言いましたら知事ですし、企業で言いましたら社長であったりオーナーであると思うんですけども、そういう方が自らこの通報者の探索であるとか、その指示を出すことというのが、本当にいいのかどうかという議論はこれから必要だと思うんです。
今後、県庁内においても、いろいろと是正していくという観点で考えたときに、一定この初動に関しては100%適切だったかどうかということは、改めて考えるべきところであると思いますし、知事が一定そこは受け入れていただいたほうが、今後スムーズにいろんなことが進むのかなと思うんですけども、その辺りについて多少でも受け入れることができるかどうか。最後、知事の見解をお聞かせいただきたいと思います。
○証人(齋藤元彦)
今回の初動も含めた対応については適切だったというふうに考えています。
今回、公益通報の是正の中で、公益通報の窓口を外部に置くということも指摘されましたので、そういったところをまずやりながら、どういった今後の法改正も含めて、公益通報の在り方、これは県の公益通報制度もどうあるべきかということは、しっかりと議論していくということが大事だと思っています。
○委員長(奥谷謙一)
それでは、増山委員。
○増山 誠委員
丸尾委員の質問にちょっと関連して、何度も4月4日の公益通報の絡みでなぜ処分を急いだんだというお話が出ていますので、ちょっと整理したいと思うんですけど、まず前提として、4月4日に内部公益通報された文書というのは、財務部長が責任者となって、財務部の公益通報担当職員のみが通報内容について知っている状態ですと。
元西播磨県民局長の処分内容を決める綱紀委員会において、複数の委員から内部公益通報の結果を待ってから処分すべきではないかという意見が出たところであるんですが、本来このような話というのはあり得ないと思うんですね。
なぜならば、知事、副知事、綱紀委員長である総務部長は、本来、内部公益通報が誰によってなされたか、どのような内容でなされたかというのは知る由もないわけですね。3月の告発文と内部公益通報の内容は全く違う可能性もあって、かつ、内部公益通報はその結果が発表される仕組みになっていないと。
この前提に立つと、3月の告発文への処分を内部公益通報の結果を待つというのは、全く関係ない事象とされるべきものに、人事処分が影響されてしまうということになるのではないかというふうに思っておりまして、例えば、誹謗中傷文書の流布したものが、何らかの文書を内部公益通報を行った旨発表すれば、永遠に処分されないという事態を招きかねないというふうに思っております。
この辺、先ほどから知事がこういう回答をされているにもかかわらず、何か皆さんが同じような質問をされてると思うんですけど、この認識についてどういうふうに思われてますでしょうか。整理して。
○証人(齋藤元彦)
そうですね、同じ認識です。
公益通報というものは、内部にされたものというのは、基本的に行政内部含めて、非公表、非共有という形になってますので、その調査を待って例えば処分を待つべきだという点については、それをやってますと、ある意味ずっと処分ができないということになるということですから、この辺りは人事当局のほうも分かっていたというふうに思ってますけども、私としてはやっぱりそこは、やはり公益通報の在り方としては、そういった観点というものはやっぱり押さえておくべきだというふうに思っています。
○増山 誠委員
ありがとうございます。
○委員長(奥谷謙一)
北上委員。
○北上あきひと委員
丸尾委員の指摘されたことなんですけれども、懲戒するべき事案があれば、法に則って何かを待つということではなく、綱紀委員会も含めて粛々とやるんだということをおっしゃってると思うんですけど、公益通報者保護法は、その組織の懲戒権を制限してでも公益通報者を保護する、そのことによって国民が享受する社会の利益を守ろうとする、そういう法律だと私は認識します。
懲戒処分の必要性と公益通報の保護が競合した場合は、公益通報者を保護する必要があるのではないか。少なくとも公益通報者保護法によって不利益処分禁止の適用対象外と確定した後、処分するという方法もあったと思うんですが、そのことについての検討はなされたのか、なされていないのか。いかがですか。
○証人(齋藤元彦)
もちろん先ほど増山委員のご指摘にも答えたとおり、公益通報というものはどういったものが通報されたということが、ある意味、対外的には非公表、行政内部でも共有されないというものになってますので、そこを待って処分をするということは、論理的にはつながらないということだと思います。
一方で、県の人事行政としては、やはり今回については誹謗中傷性の高い文書を作成した。告発をしたということに対する処分ではなくて、誹謗中傷性の高い文書を含めた四つの非違行為が判明した、認定された以上ですね、これは手続を経てきちんと処分するということは、人事行政としては適切にやっていくということが大事だということで、これは人事当局にも5月7日の会見のときにも言ってますし、私はそれはそのとおりだというふうに認識してます。
○北上あきひと委員
その公益通報者保護法の不利益処分禁止の適用対象であるかないかということは、検討せずに処分を出されたということだと、今のご答弁を受け取ってよろしいですか。
○証人(齋藤元彦)
外部通報の保護には当たらないと、真実相当性を欠くということで、外部通報の保護要件には該当しないということも踏まえてですね、これは公益通報の先ほど申し上げた処分を待ってということだと、それは公表されないという原則がありますから、そういったところもあって、その辺を踏まえて、5月7日に懲戒処分させていただいたということです。
○委員長(奥谷謙一)
よろしいですか。藤田委員。
○藤田孝夫委員
守秘義務違反、それから情報漏えいの件ですけれども、最近SNSで出ていることについて触れるというのは、アンケートとSNSが一緒みたいな委員からの発言もありましたが、これは全く別物ですから、それを無尽蔵に持ってきて、ここで議論するということは本来この会では避けるべきと私は思っています。
けれども、今度のデータファイルの流出と、それから紙ベースのファイルの流出両方があって、そしてフォルダーのアクセス権の問題やら様々なことがありますけども、両方ともこの発端というのは、県の人事課の要するにデータの管理に問題があったということにつながります。そういう面では全国の自治体で、仮にこういうことがあるのではないか。つまり人事処分をしたときに出てきた違う情報、プライバシーやら関係のない情報が流布される可能性があるとなると、これ全国の自治体はたまったもんではなくて、多分この県のこの今回の事件を発端として、様々な臆測が飛んだり、またそれを、言わば悪用するようなケースが出かねません。
そんな意味では、非常にこれは県だけで収まればいいんだけども、余計、県だから、兵庫県はそのことを確実に対処するということが求められると思うんですけれども、その件に対して知事の見解をお聞きします。
○証人(齋藤元彦)
県保有情報の問題については、先ほど来申し上げてますとおり、まずは弁護士を入れた第三者委員会でしっかり同一性含めた事実関係を調査していくということだと思います。その上で、委員ご指摘のような情報管理の在り方について、やはり改善すべきところがあれば、しっかりと対応していくということをやっていきたいと思います。
○藤田孝夫委員
確認するというのは何を確認されるんですか。
○証人(齋藤元彦)
ご指摘されている資料やデータという物が、県が保有されてる物と同一性のある物かどうかということを含めて、これは客観的に確認をしていかなきゃいけないというふうに思ってます。
○藤田孝夫委員
客観性の確認というのは裁判と一緒で、これ二、三年ぐらいかかる可能性すらあるんですけれども、そのぐらい待つということにつながりませんか。
○証人(齋藤元彦)
それは早急に第三者委員会を立ち上げて、弁護士のほうにできるだけ早く調査をしてもらうようにお願いをしようと思ってます。
○藤田孝夫委員
調査権のある機関ですぐにやる。あるいは当該者の、例えば井ノ本さんになると思うんですけど、パソコンの捜査をすぐするということはされましたか。井ノ本さんのパソコンの捜査はされましたか。
○委員長(奥谷謙一)
あまり個人名は。
○藤田孝夫委員
はい。
○証人(齋藤元彦)
いずれにしましても、私はその捜査をしたか、してないかというのは存じ上げてませんが、いずれにしても、その件についてはまずは第三者委員会を立ち上げて調査をしていくと、事実関係を確認しながら対応していくということが大事だと思ってます。
○藤田孝夫委員
それは3年かかっても構わないという意味ですか。
○証人(齋藤元彦)
できるだけ早く対応していくという。
○藤田孝夫委員
できるだけではなくて、これは所管のトップが知事ですから、事の重大性に鑑みれば、即、調査権のあるところに依頼してしかるべき、こういう重大な案件だと思うんですけれども、その認識はないということでよろしいですか。
○証人(齋藤元彦)
しっかりと調査していくという意味では、委員と一緒だというふうに思ってます。第三者委員会を弁護士入れて立ち上げて、ちゃんとできるだけ早く調査していくということだと思います。
○藤田孝夫委員
この間それが流布されることによって、被害者が出ているということについてどう思うかも含めて、すぐにすべきと言ってるわけですから、待つ意味が。長ければ長いほど、これは被害が広がっていくということですから、即止めてというのが正しい判断だと思うんですけど、そうは思われないということですね。
○証人(齋藤元彦)
これから第三者委員会を立ち上げて、できるだけ早く対応していくということです。
○藤田孝夫委員
もう結構です。
○委員長(奥谷謙一)
じゃあ最後、すみません。
○庄本えつこ委員
今のことについては、藤田委員と同じ思いを持っているということを申し上げたいと思います。
先ほど私が申し上げた3月12日の告発文が出されたときには、2号、3号になると。27日直接本人が県当局にしっかりと事実を確認してほしい、それから処分とかそういうことも含めてというふうなことも、本人が言ってるということについて、もう1号通報というふうになると、3人の参考人が全てそうおっしゃっています。
そのことを踏まえますと、告発者が誰か、こんな文書を書いたのは誰かということを探すのではなくて、客観的に書かれているその告発されている中身、事実を確認していくということが本来求められていたにもかかわらず、そのことをしなかったということに、兵庫県の最高責任者としての知事の責任の在り方が問われると思っていますが、いかがですか。
○証人(齋藤元彦)
先ほど来申し上げましたとおり、3月の文書発覚時点で誹謗中傷性の高い文書だということで、やはりこれは影響が大きいということで、どなたがつくったということ、まず、これは県の内部の方がつくられた可能性が高いということで、どなたがつくられたかということを調べさせていただいたというところです。
○庄本えつこ委員
公益通報の関係でいうと、それをやってはいけないということなんです。うわさ話とか臆測をもとにしているからといって、不正目的があるとは認定もされませんし、真実相当性があるかないかで、公益通報者保護の問題にしないということは、その認識が間違っているということを申し上げたいと思います。
以上です。
○委員長(奥谷謙一)
それではお時間が参りましたので、これをもちまして証人尋問を終わりたいと思います。
齋藤元彦証人におかれましては、お忙しい中ご出席をいただきましてありがとうございました。ご退席いただいて結構でございます。
(証人退室)
それでは、証人尋問を終わりたいと思います。
閉 会(午後5時29分)


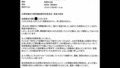

コメント